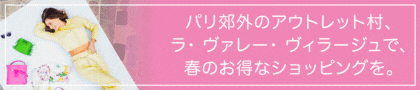海外県グアドループで、本土より1.6倍以上の物価高に対する怒りのゼネストとバリケード闘争が1月20日から44日間続いた。2月5日以降マルチニーク島とレユニオン島にも飛び火した。
3月5日、グアドループの49組合の集合団体LKPのドモタ代表と政府・県とが、LKPが要求してきた165項目に合意。最低賃金SMICの1.4倍以下の低所得者5万所帯に向こう3年間200€の特別手当、県は8万の貧困所帯に援助金100€給付、水道・ガソリン・交通費などを10~20%値下げ、若年労働者8千人の雇用計画、家賃凍結など。仏経団連MEDEF支部は賃上げなどに同意していないが、LKPは突破口を開き、次の段階を目指す構えだ。
グアドループ島は1947年に海外県となったが、今日経済の90%を奴隷所有者の子孫たちベケ(人口の1%)が牛耳るネオコロニアリズム体制に。長期ゼネストの根底には経済・社会問題の他に、人種差別を伴った植民地遺産が横たわっている。
フランスは1635年にカリブ海のグアドループ(今日約45万人)とマルチニークを植民地にし、白人はサトウキビ増産のため原住民の他にアフリカからも黒人を輸入した。白人と黒人の混血ムラート(メティス)の中にも奴隷所有者がいた。しかし彼らは白人社会から締め出され、白・褐色・黒の社会的ヒエラルキーに組み込まれる。1791年、仏革命の余波を受けて、現ドミニカ共和国とグアドループで奴隷制が廃止されたが、当時英国支配下にあったマルチニークでは奴隷制が維持された。
ところが1802年にナポレオンが奴隷制を復活させたためグアドループは騒乱状態に陥る。この動乱期にグアドループのかなりの農園がマルチニーク出身のベケたちの手に渡る。今日もグアドループとマルチニーク両島民の間に残る相互猜疑心はこのへんに根ざしているよう。 1848年、ついに政府は奴隷を解放し、その代わりに元奴隷所有者に多額の賠償金を支払った。彼らはさらに富を増し、私有地を拡大していった。政府は海外県にサトウキビの単作栽培と本土との独占貿易を課し、本土依存型経済を定着させた。そして戦後、仏北部に砂糖大根の栽培を奨励し、サトウキビを切り捨て、代替産業を助成させなかったことも島の貧困化の一因に。
1848年、ついに政府は奴隷を解放し、その代わりに元奴隷所有者に多額の賠償金を支払った。彼らはさらに富を増し、私有地を拡大していった。政府は海外県にサトウキビの単作栽培と本土との独占貿易を課し、本土依存型経済を定着させた。そして戦後、仏北部に砂糖大根の栽培を奨励し、サトウキビを切り捨て、代替産業を助成させなかったことも島の貧困化の一因に。
失業率23%(ゼネスト後30%、25歳未満55%)という高い失業率のためだけでなく、本土の大学を出ても肌が黒いためにまともなポストにありつけないのが現状(企業幹部は全員白人)。政府の温情主義政策により海外県の公務員給与は本土の1.4倍、3人に1人は公務員だ。国が支払う公務員給与が支える人工的消費社会をなしている。
1970年の県民投票でグアドループ住民の70%が独立への道よりも仏国民であり続けることを選んでいる。「フランス人であってフランス人として扱われない」彼らの中から仏版オバマが生まれるにはかなりの時間がかかりそうだ。(君)
(写真:合意書にサインするLKPのドモタ代表と県知事。(France 2より))