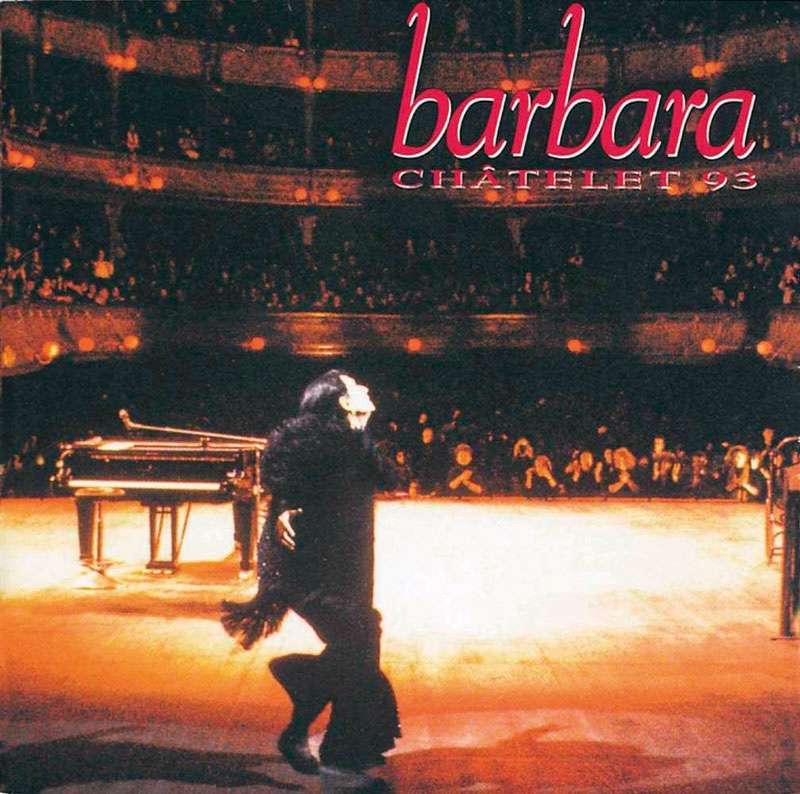遺伝子組み換え技術
 遺伝子工学は、近年、ヒトの存続そのものにかかわるような極めて重要な役割を演じようとしている。遺伝子工学の意味するところは文明論的な問題にぶち当たるのである。それは、生態系の根本原理に介入しようとしているからである。
遺伝子工学は、近年、ヒトの存続そのものにかかわるような極めて重要な役割を演じようとしている。遺伝子工学の意味するところは文明論的な問題にぶち当たるのである。それは、生態系の根本原理に介入しようとしているからである。
地球上に生物が誕生してほぼ35億年と言われる。あらゆる生物の祖先である遺伝子DNAを持った単細胞が複合細胞となり、気の遠くなるような歳月を費やして、複雑な遺伝子構造が自然淘汰のうちに改良され、この地球上に無尽蔵の多様な生物を育んできた。その数、数百万から数億と推測されているが、生態系は絶えず変化しているため実数は掴めない。それらは、ある同一種の結合・交尾により、子孫を産み続け発展生成してきた。
新世紀に移行する今、生態系の悠久な時の流れのなかで、必然と偶然がせめぎ合う過程を通して進化してきた生物のもっとも核心的な部分、遺伝子構造に人間が介入しようとしている。人間は今や不可侵の領域に関与する技術を手中にした。そのことが人間の生存にとって極めて重要なのは、遺伝子が人為的に操作された場合、それによって及ぼされる直接的な影響や生態系への影響がどのようなものであるかを、人間は現在のところ、総合的に予知する能力を保有していないということだ。
アグリビジネス (農業関連産業)
このようなテクノロジーが新手の商品技術となり、新しい経済領域として発展する可能性によって、遺伝子操作の進行が促進されている。特に、アグリビジネスの世界では、80年代前半に種苗産業へ大手の多国籍企業が参入し、「種子戦争」ともいわれる状況を呈するようになった。「ハイブリッド」、「一代雑種」をキャッチ・フレーズとして、収穫の飛躍的増大を宣伝した。
世界的農業関連企業のモンサントやノヴァルティスはこう主張する。「農業の遺伝子操作は、害虫に強い農作物を作ることによって、数百万の人々を飢餓から救う方法だ」と。相当数の飢えた第三世界の民衆を救済すると主張した。だが、遺伝子組み換え作物 (OGM)
は「ターミネーター」と呼ばれる技術によって種子を残すことができないように遺伝子操作されており、育てたものから種をもらい、その種をまた蒔いて新しい収穫を得るという従来の農耕循環ができなくなる。あるいは「ハイブリッド」技術は、遠縁の種を掛け合わせて、両系譜の優性を引きだすことにあったが、その長所は一代しか持続せず、確かに一代目の収穫高はいいが、二代目は形が不揃いであるといったように、一代目の長所が引き継がれない。つまり、毎シーズンごとに新しい種子を買わなければならない仕組みにされているのだ。
多国籍企業の戦略
もう一つの問題は、これら大手の国際企業が合併、集合を繰り返しながら市場を独占しつつあることだ。そして彼らはその戦略にたいへん長けている。こうした企業は遺伝子組み換え種子を売ると同時にその種子に見合った農薬も一緒に販売するのである。つまり除草剤耐性品種と農薬とをワンセットで売る、まさに一石二鳥の戦略である。言い換えれば、農家が代々受け継いできた知的遺産をことごとく破壊することであり、農業従事者の自主的判断と知恵によって農業を変革することはほとんど不可能になる。大企業が売りつける種子と農薬を一緒に買わざるをえないという状況が遠からず出現する危険性が高いのである。だが、利潤のみを追及する企業にとっては、これほどうまい話はない。
具体的な例を挙げてみよう。遺伝子工学に参与している多国籍企業の大半が化学系の会社で、莫大な利益を得ている。しかも上位10社が世界のほぼ30%にあたる輸出種子を製造しており、そのうちの化学系5社[モンサント (米)、アヴァンティス (仏)、アストラ・ゼネカ (英)、デュポン(米)、ノヴァルティス(スイス)]が、遺伝子組み換え種子市場をほぼ独占している。しかし、例えば、化学・アグロ化学系の会社の中でも、モンサントほど遺伝子工学に投資している会社はほかにない。同社はベトナム戦争時に使用された非常に毒性の強い枯葉剤の製造会社である。この枯葉剤に含まれていたダイオキシンが原因で、撒かれた地域に先天性奇形、流産、死産が多発したのはあまりにも有名だ。
同社が製造している「ラウンド・アップ」という除草剤は同社の売り上げの15%で、主要商品である。この除草剤は、種の区別なくすべての植物を枯らせてしまう。しかし、モンサントはラウンド・アップに耐性のある品種を作り、その種子をセットで売ろうとしているのである。そして、この除草剤は人体に無害どころか、これを使用している農業従事者が農薬による病気にかかっている。
遺伝子の特許化?
三つ目の問題は、遺伝子を含む生物の特許化である。自由経済の論理に立てば、当然、何でも売買の対象にして当たり前だという考えが出てくる。しかし、何千、何億年とかけて進化形成されてきた遺伝子の集合を今日、解読しつつあるのは確かだが、こうした「ときの流れ」のすべての情報を内包している遺伝子は、遺伝子技術者によって作られたわけでも発明されたわけでもない。
従来、品種保護制度は、普通の特許制度とは分けて考えられてきたが、この制度も世界貿易機関によって特許制度化されようとしているのである。分離され配列解析がなされれば、遺伝子さえ特許の対象になるということだ。シアトル会議はまさにその攻防戦であった。
最後の問題は、いかなるリスクがあるのかという点である。「予防原則」の根本は、何よりも健康第一ということである。しかし、このあまりにも明白な原則が、経済原理の陰でなおざりにされている。「予防原則」に立つ限り、このような予測不可能な分野は、一度してしまえば不可逆的な領域となる。生命の存続に関わっている領域に根源的で決定的な影響を与えるだろう。それゆえ、その操作で生まれた品種を作ることによって莫大な利潤が生まれるにせよ、遺伝子操作に着手することは、未知の巨大な冒険といわざるをえないだろう。
だが、実際には、遺伝子組み換え農産物はすでに作られ、販売されている。組み換え食材によるビスケット、クリーム類、マーガリンなど枚挙にいとまがない*。しかし、このテクノロジーを使うと、自然界では絶対に起こりえない異種間の結合が起こりうるのである。典型的な例を挙げるなら、イチゴのある種には、輸送の途中に凍らず形の崩れないイチゴにするために、魚の遺伝子が組み込まれた。だから、アメリカではこれらを「フランケンシュタイン・フード」と呼んでいる。
昨年、フランスでは、カナダの企業アドヴァンタから輸入され植えられた菜種が遺伝子組み換え品種であることが分かって大騒ぎになった。これは、農薬に強い遺伝子を組み入れた菜の花の種を、普通種の中に誤って混入したのが原因だ。仏政府は600ヘクタールの菜の花畠を全部破棄することに決定したが、満開の時期は過ぎ、花粉はミツバチによって持ち運ばれているかもしれない。この点に関しては、ドイツはイエナ大学のミツバチ研究グループによって、遺伝子組み換え菜の花粉を食べたミツバチの腸をバクテリアに食べさせると、組み換え遺伝子がバクテリア体内にも取り込まれることが判明した。
英国はローウェット研究所のプシュタイ博士率いる研究班が、マツユキソウから取りだしたレクチンという蛋白質を作る遺伝子を抽出し、ジャガイモに組み込んだ。それを実験用ラットに食べさせたところ、脳、肺、腸などの重量が減少し、免疫システムにも障害を起こした。
遺伝子組み換え技術が、生態系に決定的な悪影響を与えかねない重大な問題を含んでいることは今や疑問の余地がない。とりわけ、組み換えが行われたトウモロコシや大豆が植えられたとき、周囲の生態系にも大きな影響をもたらすことが観測されている。またそれらを食べ続けたとき、自然に人間が有していた自己治癒能力や抗体などに与える影響が非常に懸念される。ある種の遺伝子組み換え食品はアレルギーを発生させるリスクがある。アレルギーは時には死さえもたらす。様々な食品でアレルギーをおこす人は約2%いるという。マンゴー、イチゴ、キウィ、魚なども、アレルギー症の人たちにとっては、怖い食品だ。ましてやそれらの作物の遺伝子が、本来自然条件の元では結合されるはずのない遺伝子同士が無条件に組み換えられた場合、どのようなアレルギー症候群が多発するかもわからないのである。(プチ・ポア)
*エコロジー団体 Greenpeace Franceでは、遺伝子組み換え作物を使用した食品のリストを作成している。インターネットのHPで入手できる。http://www.greenpeace.fr/