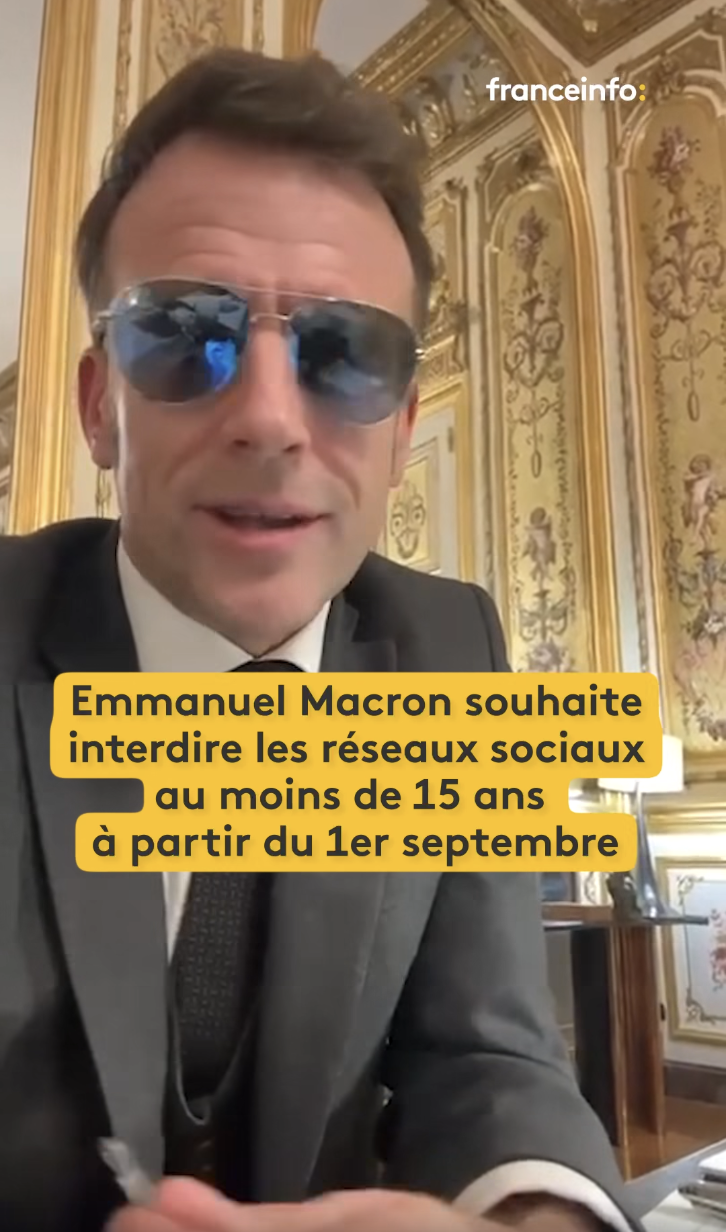6月5日付ラ・クロワ紙。上陸作戦ー書き続けられる歴史。
ノルマンディー上陸を記念する6月6日(D-デイ)の式典は、当初は作戦に参加した連合国首脳のみの戦勝祝いだったものが、ミッテラン時代に平和を再認識する欧米サミットに、シラク時代にドイツ首相も参加するEU結束の場に、5年前のオランド時代にはロシア、ウクライナも招待し、国際平和会議の様相を呈していた。75年記念になる今年は、冷え切った米仏関係や出口の見えない英EU離脱(Brexit)を反映してか、白々しく寂しい式典に終始した。
毎年の恒例で米映画『史上最大の作戦』がTVで再放映されたが、リベラシオン紙は「ハリウッドスター総動員のプロパガンダ映画の功罪」を説く。Ifop社のアンケート「どの国がドイツ敗戦に最も貢献したか?」に対し、1945年5月にはフランス人の57%がソ連、20%が米国、12%が英国と答えていたのが、2015年には54%が米国、23%がソ連と全く逆転しているのだ。
そのような認識の変化と並行するように、今回の記念式典にはプーチン大統領が招待されず、フィガロ紙やマリアンヌ誌が「2700万人の犠牲を出してナチスと戦ったロシアを呼ばず、40万人の戦死者だけの米国はおもてなしか?ロシアが東部戦線で健闘してくれなかったら、上陸なんて有り得なかったのに」と揶揄した。

毎年6月6日前後に放送される、『史上最大の作戦』(1962)。ジョン・ウェイン、ロバート・ミッチャム、ヘンリー・フォンダらが出演。
米兵の武勇伝ばかりの『史上最大の作戦』のシナリオを読んだドゴールが怒って「仏国内での撮影一切禁止」を命じたため、慌ててレジスタンスが輸送列車を爆破するシーンを加えて撮影許可を得たと言う。作戦参加兵士の総数は、米軍より英軍の方が多いことも、作戦の詳細は英軍が立てたことも、この映画は語らない。地元民たちが米軍ジープを大歓迎するシーンは全く史実に反している。独軍の補給路を断つために上陸に先立って大爆撃を受けたノルマンディー地方は、連合軍の攻撃による死傷者が圧倒的に多く、地元民のほとんどは怒りと恐怖と沈黙で上陸軍を迎えたのが現実だ。軍隊が通るところ性暴力事件は絶えず、被疑者は、即刻軍事裁判の上、被害者の目前で銃殺刑に処された。性犯罪は最悪だが、血まみれのオマハを辛うじて生き延びた若者たちがその数十㎞先で銃殺されたのは忍びない。
P・ロットマン作のドキュメンタリー『1944年夏』は、アイゼンハワーは上陸完了後大量のドル札を持ってフランスに渡ったと語る。それを知ったドゴールは米軍が独軍に取って代わらないよう自由フランス軍によるパリ解放を急がせる。独占領軍司令官フォン・コルティッツは連合軍ではなく自由フランス軍に降伏させなければならない。「米軍の兵士と物資も、ソ連の資金で動く仏レジスタンスも必要だが邪魔者」と微妙な態度のチャーチル。三者三様の冷徹なシニシズムに学ぶところは多い。と同時にコルヴィル米軍墓地に限りなく立ち並ぶ白い十字架は、実はこのシニシズムの犠牲者、英雄という名の捨て石の感は拭えない。(森)