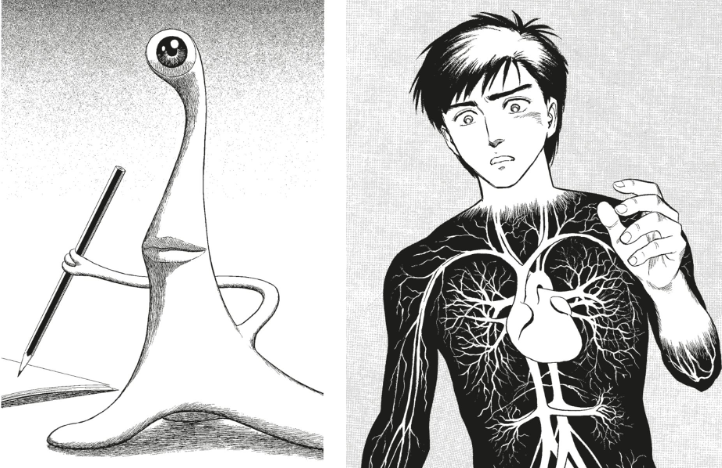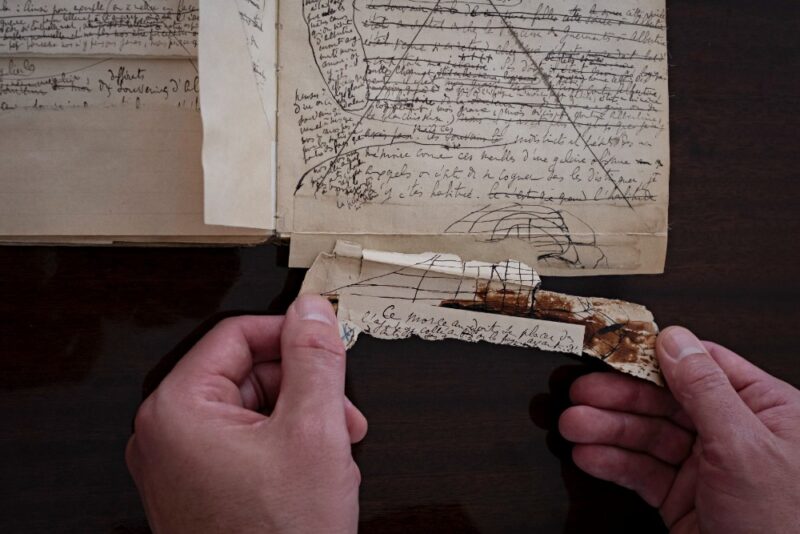9月3日付レゼコー「仏消費者の新たな顔」
「déconsommation」という言葉を最近時折り目にする。低経済成長、資源問題、環境汚染が云々される時世での消費主義の後退を意味するらしいが、ここでは仮に「脱消費主義」と呼ぶことにしよう。経済紙レゼコー9月2日のネット版に「生活必需品にも脱消費主義が定着」という記事が載っていた。フランスの大型小売店における大衆向け食品・日用品などの販売数量は2019年上半期中に1%減ったが、販売金額は1.5%上がったという。消費者は以前より量を少なく買う代わりに、有機食品、地元産などよりよい品質のものを買う傾向が強まったと記事は分析する。
ネット経済紙ラ・トリビューンの20日付では世論調査を基にフランス国民の消費減退の傾向を詳しく報じている。2017年にはフェアトレード商品、エコマーク商品などの「オルタナティブな消費」を心がける人が38%だったのが19年では23%に減少し、全体的に消費を減らそうとする人が14%から27%に増加した。また、約90%の人が消費に重きを置かない社会に暮らしたいと答え、約50%が「永遠なる成長」という神話に基づいた経済モデルを見直すべきと回答した。実践面では、44%の人が新商品を買い控え、70%が化粧品や衛生製品の消費を抑えていると回答。こうした消費行動の背景には環境問題への関心がある。地球温暖化、プラスチックごみ問題など地球の将来を考えて行動することが急務と答えた人は60%に上る。過剰消費を煽る大企業の態度を嘆き(88%)、小規模商店や生産者からの直接購入を好む(36〜41%)傾向が高まり、持続可能な商品を購入基準にする(38%)。生産者から消費者への直販システム(AMAP)が普及し、量り売りの食品店、肉や調理済み食品の買い控えなど様々な現象も報じられている。
消費を減らす傾向には、人によって購買力の低下、環境保護、消費主義に背を向けるライフスタイルなど様々な理由があるだろう。前述の調査では、ドイツ、スペイン、英国、スウェーデンでも消費主義に支配されない社会を望む人が8割という結果が出ており、過剰消費に背を向ける傾向は欧州先進国にじわじわと広がっている。もしこの傾向が今後も強まっていくとしたら、消費を助長し新製品を次々と売り出す従来の経済モデルは、持続可能開発を可能にする新たな経済モデルに取って代わられるのだろうか?経済成長が鈍れば経済が停滞して失業者が増えるという従来の考え方は見直される時期に来ているのかもしれない。(し)