●La Cloture
パリの道には名前がついている。中でも歴史に残る人物の名前がついているものが多いが、その中の一つ、パリの北東部、La Porte de Saint-OuenとLa Porte d’Aubervilliersの間を環状線と平行する通りは、ナポレオンに仕えていたネー元帥からその名がとられている。
この小説は、この将軍の物語と、彼の名を持つ通りで現代を生きる人々の物語から構成されている。
このパリの北東、18区と19区の周縁。地理的にはパリだが、パリに入る者たちとパリから出る者たちが「パリから出ることもパリへ入ることもできない」というPorte de la Chapelleに象徴されるように、ある意味最もパリらしく、パリらしくないゾーン。民俗学的なフィールドワークによって、そこで生きる人々の生が記されている。環状線の下のキャラバンカーで生活するジェラール、元ザイール軍の兵士でパリに亡命し、クリニャンクールのマクドナルドで警備を務めるリト、東欧から流れ着く少女たち…。
パリで最も荒れ果てている地区で生きる人々の人生や風景、出来事が淡々と綴られるこの小説、そこには社会への糾弾もなければ批判もない。哀れみも、嫌悪もない。客観的な現実記述?
否。これは小説であってドキュメンタリーではない。パリジャンでもほとんど足を踏み入れることのない地区と、出会うことのない人々の生活をかいま見る、というような読者の「覗き見趣味」「エキゾチシズム」を満足させるのではない。この小説が読者へ伝えるのは、世紀の転換期である現代、パリの深淵に蔓延る存在感だ。この小説は現代のパリの社会・現実を描くというよりも、小説として、「今の」存在を語っている。読者がその想像力で体験するのは、未知の現実ではなく、秘められた(secret et inavoué)存在の感覚だ。(樫)
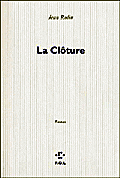

Jean Rolin, P.O.L.,
2002, 248 p. 16,50€







