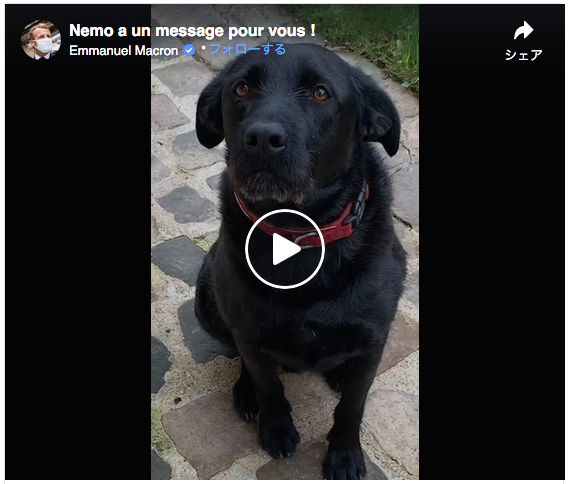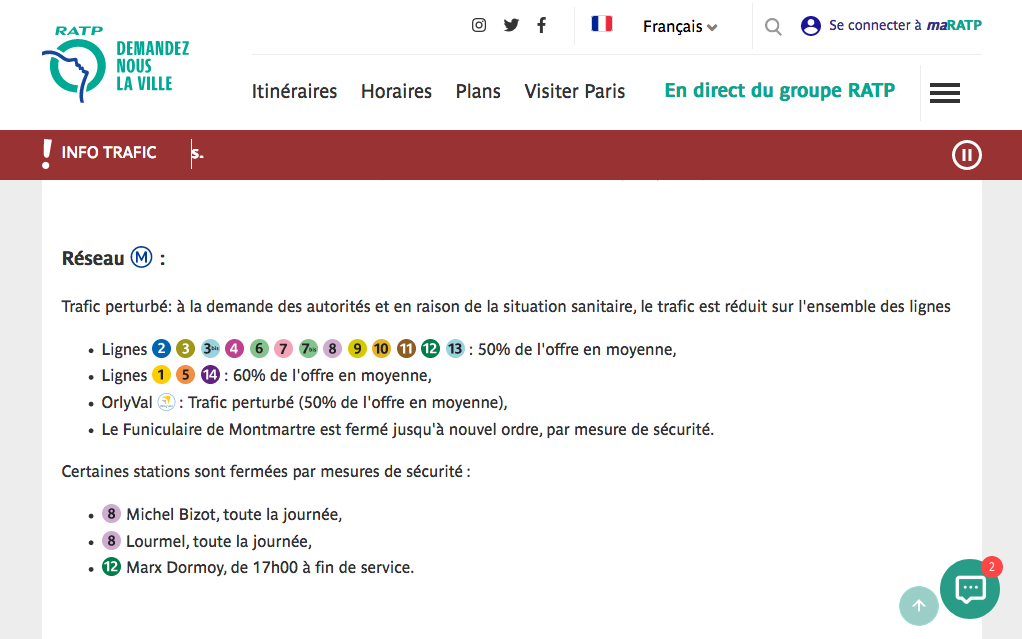かつてプロレス界にフレッド・ブラッシーというレスラーがいた。日本でも力道山やアントニオ猪木などと対戦し、その猟奇的な噛みつき技で怖れられた。血まみれの試合を見た観客が何十人もショック死したという伝説さえ残っている。
今年6月のフランスは「ブラッシー病」が蔓延(まんえん)したかのように、警官への噛みつき攻撃が相次いだ。4日にはルーアン近郊で職務質問しようとした警官が、コンサート帰りの酔っ払いの飼い犬の返り討ちに遭った。12日には、娘に噛みつかれたジャン=マリ・ルペンの裁判を取材していたAFP通信の女性記者が、もみ合いになった警官を噛んで逮捕された。そのわずか3日後の15日には、パリ17区のバティニョル通りで、違法駐車していた愛車をレッカーで撤去されそうになった老人が同じ暴挙に出た。すでに吊り上げられていた車の運転席に飛び乗って立てこもった挙句、無理やり引きずり出されてガブリとやったというのだから、凄い執念だ。
警視庁舎でレイプ事件が起きる。押収した麻薬が大量に横領される。警察トップが捜査情報を洩らしていたことが発覚したと思えば、ディスコ帰りの警官はパトカーを飲酒運転ですっ飛ばして信号無視を繰り返し、配達中のパン屋を轢(ひ)き殺す。「窮鼠(きゅうそ)猫を噛む」ではないが、日刊紙 『パリジャン』が、17区で逮捕された老人を「反逆じいちゃん」などと称しているように、一連の噛みつき事件の報道を見ていると残虐性よりも、不祥事が絶えない警察への不満を発露するように、滑稽味や痛快さが勝っているように思える。(浩)