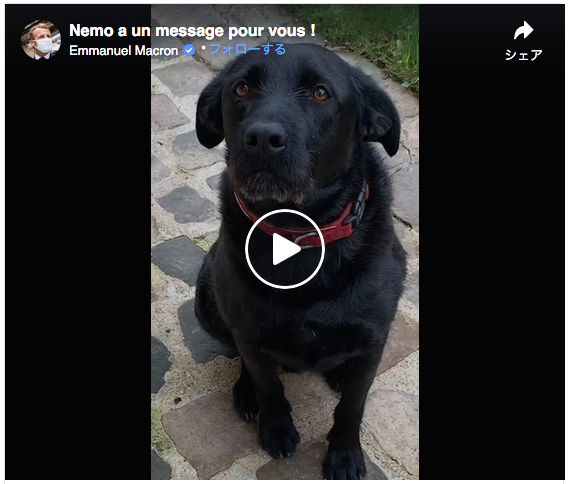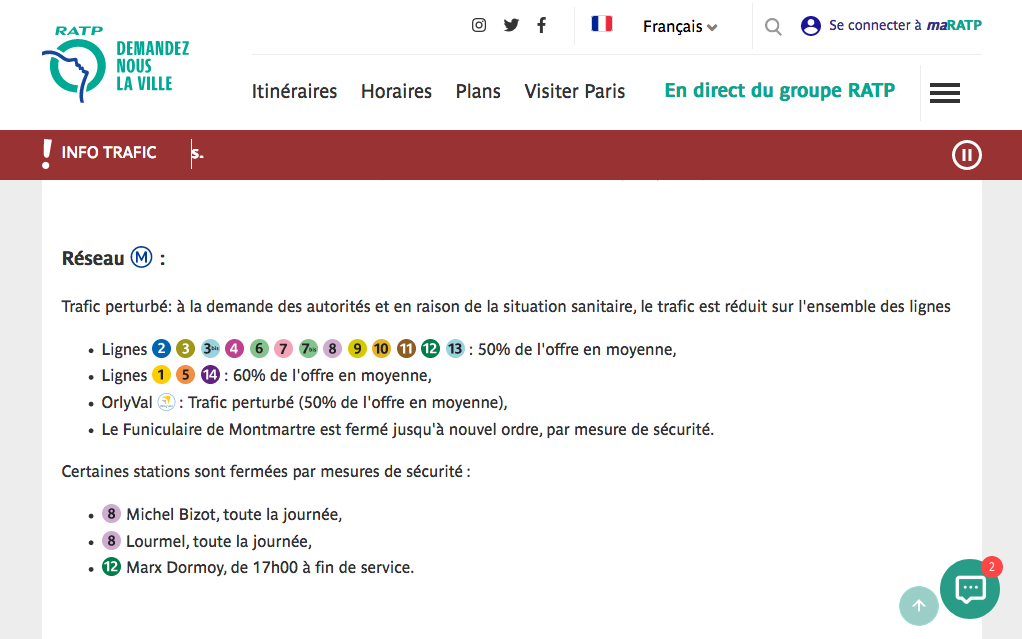『忠臣蔵』といえば、日本では年末年始の時代劇の定番となっているが、かの福沢諭吉は『学問のすすめ』で、赤穂浪士の討ち入りを野蛮な因習として批判した。しかし、彼が文明国として憧れたフランスでも、昨年の年末は、とある「あだ討ち」事件がメディアをにぎわせた。
フランス南西部にあるペルピニャン市の重罪裁判所で、リブザルトという町に住んでいるジャン・パストゥイルという89歳の老人に対して、娘婿を殺害した罪で、禁固10年の判決が下った。
事件雑誌『Le Nouveau Détective』12月17日号に掲載された裁判の傍聴記によると、彼は公然と被害者を「ケダモノ」呼ばわりし、自らの行為に「悔いはない」と断言した。猟奇的な復讐心をあらわにした言葉だが、彼は精神異常者でも犯罪常習犯でもない。むしろ、「Jeannot(ジャノ)」という愛称でみんなから親しまれ、かつて見向きもされなかった町の土地にムスカデ種のブドウを初めて植え、甘口ワイン「ムスカ・ド・リブザルト」の生みの親として尊敬されていた。そんな好々爺(こうこうや)がなぜ人を殺したのか。異例にも法廷は、脳こうそくが原因とされていた2008年8月の娘の死の真相を語ることを、被告に許した。そして、異様な事実の数々が明るみに出た。
夫の浮気を知った娘が別れ話を突きつけていたこと、死亡時に救急車が呼ばれなかったこと、遺体の枕元には薬品のアンプルが置かれていたこと、そして麻酔医である婿が早々と同僚に死亡診断書に署名させ、埋葬という家族のしきたりを無視し、遺体を火葬したこと。これだけ不可解な点を残しながらも、娘の死は「病死」として片づけられ、自分が娘に贈与した家は、そのまま彼女を殺した男と彼女の夫を寝取った女の愛の巣となった。腸が煮え返らない方がおかしい。娘の変死から2年目の夏、火消し装束をまとう大石内蔵助のように、ジャノは覆面をして戦闘服を着込むと、ライフルを手に婿の元に乗り込んだ。合計4発。とどめの1発は至近距離から喉元に撃ち込んだ。
証言台に立った警部は娘が亡くなった時点で介入すべきだったと、当局の不備を悔いた。愛娘の怨念は晴れたものの、司法制度は残忍にもジャノにのしかかる。禁固10年の判決。被告席のジャノは、「武器をよこせ」と叫び、傍らの警官が腰に帯びていた拳銃を奪って自決しようとした。しかし直ちに制せられ、切腹で本懐を遂げた赤穂浪士のようにはならなかった。(浩)