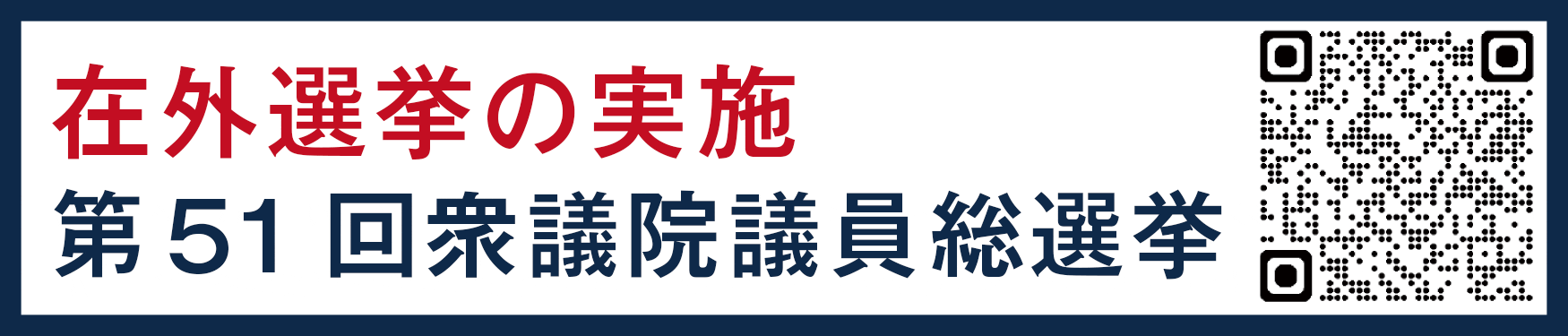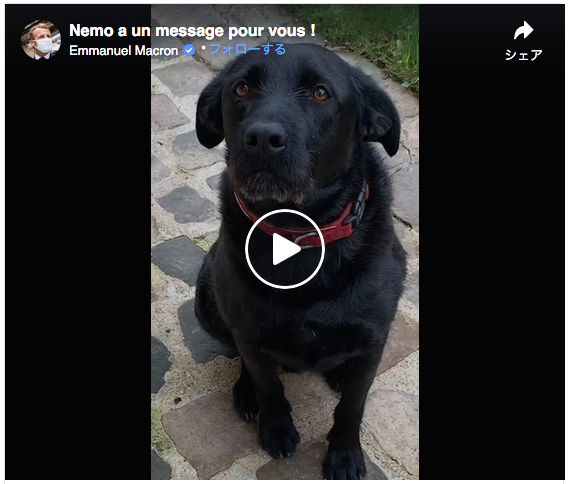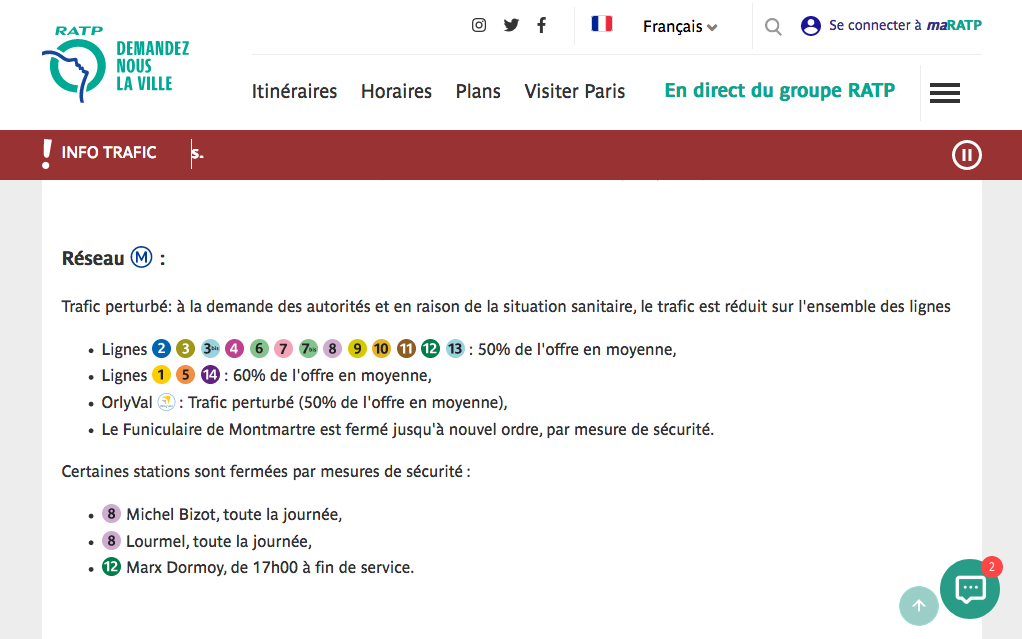強烈な色彩の綿菓子やかき氷、射撃の空気銃の音や呼び込みの口上、そしてジェットコースターの乗客の叫び声。パリのヴァンセンヌの森のルイイReuilly緑地で毎年春先から6月まで開かれるラ・フォワール・デュ・トローヌLa Foire du Trône。古くは957年に始まり、50年前に今の場所に移ってから何世代にもわたって、パリっ子たちの子供時代の思い出のページを彩ってきた。この欧州最大の移動遊園地が今、危機に瀕(ひん)している。毎年百万人単位の来場者があるというから、客足が遠のいて閑古鳥が鳴いているのではない。日刊紙パリジャンによると、むしろその集客力のせいで、近隣のサンモーリスやシャラントンといった自治体の市長から立ち退きを要求されているというのだ。とくにサンモーリスのカンボン市長は「パリの新市長もこの緑地に植樹して森林化することに努めてほしい」と手厳しい。
それとは逆に日本では、会社更生法の適用を受けて存続を危ぶまれた浅草の花やしきのために、住民が奮闘したり、地元の台東区が債権者に「再生要望書」を提出したり、地方でも映画やドラマのセットを自治体が観光資源化するなど、むしろ外から客が集まることはよいこととみなし、住民と自治体が一丸になって応援する風潮が見られる。
この二つの自治体が立ち退きを要求している理由として、騒音や治安悪化、ゴミの散乱や交通渋滞などが遊園地によって引き起こされることがあげられる。パリのイダルゴ市長は、時期がすでに遅く、今年は別な場所に立ち退かせることは不可能としているものの、半ば、次回は別の場所への移転を検討すべきだろうとしている。しかし、移転先でも同じような立ち退き要求が持ち上がるのは必至だろう。
かつては遊園地は、町のシンボルでもあった。近くに住んでいる人は、自分の住んでいる場所を説明するのに遊園地を引き合いに出していたのではないだろうか。だが、次第にBOBOと呼ばれる豊かな中間層が定住するにつれて、夜中の0時まで営業している遊園地は「うるさい」と邪魔者扱いされる。まがまがしい盛り場など要らず、もはや「メトロ、仕事、睡眠(Métro, boulot dodo)」、仕事と自分たち家族だけの静かな生活さえ保証されればよい、というのがパリっ子の良識になってしまった、というのが現実なのかもしれない。
今年のジェットコースターの叫び声を聞いていると、どことなく「古き良き時代」の最後のうめき声のようなものを聞いているような気にもなる。(康)