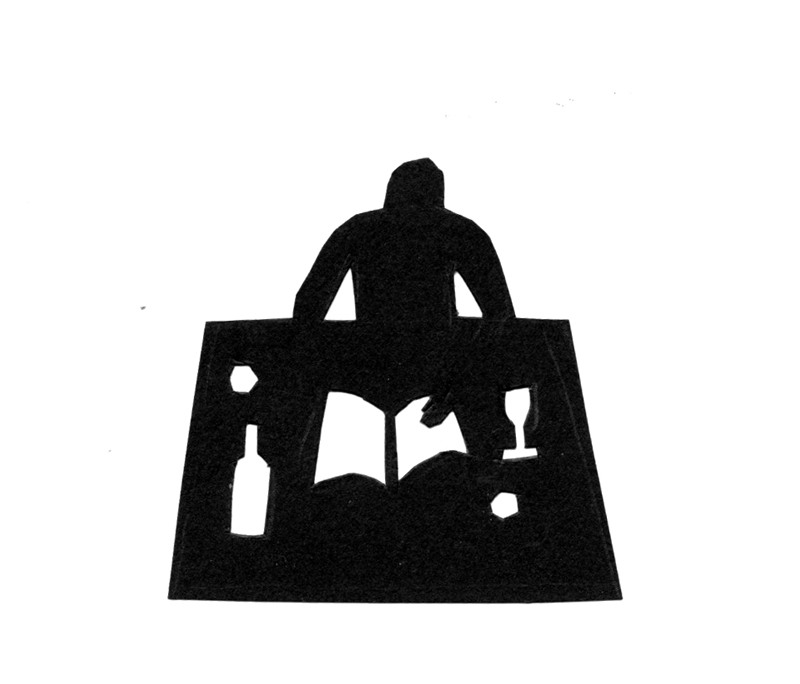18世紀の哲学者ルソーの人生を振り返ると、その複雑怪奇な性格や、行動の矛盾に気づかざるを得ない。その中でも特に驚かされるのが、後に多くの貴族も手本としたといわれる教育書『エミール』(1762年)を書いておきながら、自らの子どもを実に5人とも孤児院に入れたという事実。
もっとも、18世紀後半のフランスでは子どもを育てる財力や環境を持たない親が孤児院に頼ることは珍しくなく、年に6000人近くもの赤ん坊が孤児院に入れられている。晩年まで楽譜写しをして生活費をまかなっていたルソーにしても、物質的に豊かでもなければ信頼できる家族に恵まれていたわけでもなく、健康にも問題があり、孤児院というのは苦渋の決断でもあった。
ただ、どんな事情があったにせよ、複数の子どもを捨てたのは事実。同時代の作家ヴォルテールは、そのスキャンダルを公にしてルソーを糾弾した。子どもが嫌いなわけではないルソー自身、自らの行動を後悔する日もあったようだ。しかし「Vitam impendere vero(人生を真実に捧げる)」をモットーに我が道を突き進み、陶酔感のうちに『エミール』の最終巻を書き上げたルソーのこと。やり直せるチャンスがあったとしても、思索を妨げる環境からは断固として身を守ったに違いない。
暮らしをシンプルに保とうとするルソーの態度はあらゆる分野で一貫しており、食の嗜好にもそれは如実に表れている。「味覚についてはいつも自然にきいてみよう。料理ではいつも自然が真心こめて支度してくれたもので、食卓にならべられるまでにできるだけ人の手をかりなくてすむものをもとめよう。ごまかしのまぜものをつくらせるようなことはさせないで、自分で楽しみの用意をすることにしよう」。(今野一雄訳)ぜいたくな食べ物には縁がなかったルソーだけれど、食がもたらすふわりとした快楽はしっかり味わっていた。(さ)