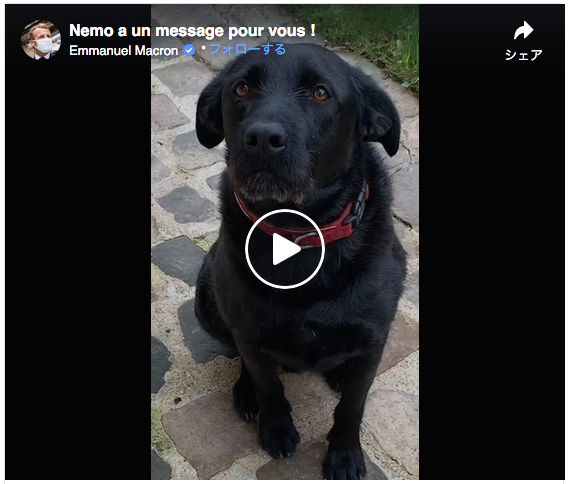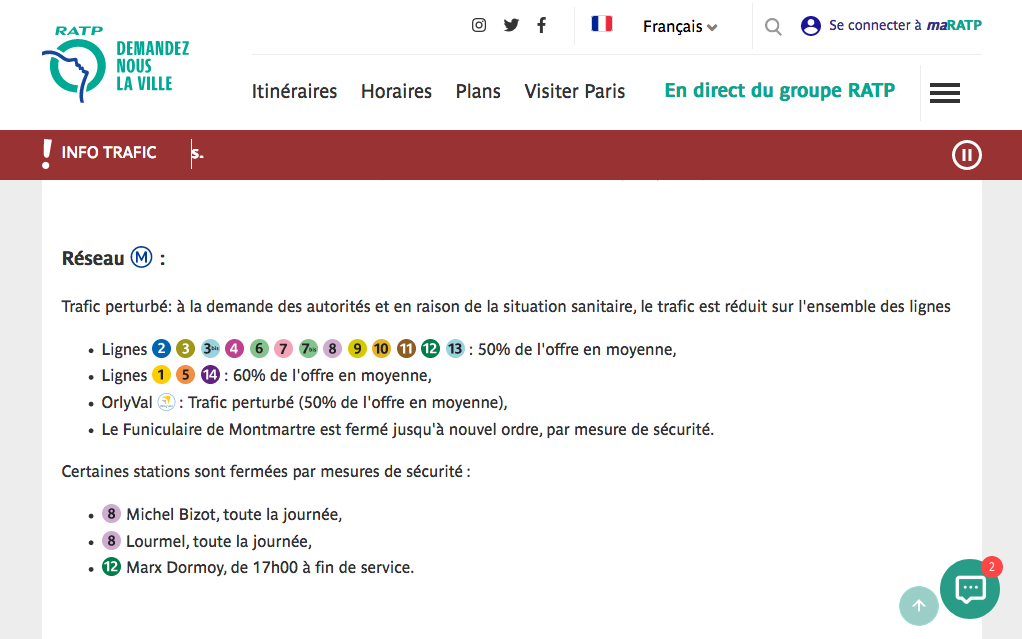1960年代から70年代にかけて、孤児1615人が、インド洋に浮かぶレユニオン島から強制的にフランス本土に移送され、労働を強いられた。2月18日、国民議会はこの過去の政策の道徳的責任を認め、元孤児たちが人生を立て直せるような措置をとるとの採択を下した。しかし、かつての孤児たちの多くはすでに還暦を超えており、これまで彼らの訴えを退け続けてきた国や欧州人権裁判所への批判も高まる。
「黄金の30年」と呼ばれた戦後のフランスでは、第2次大戦の復興と経済成長の中で労働力が不足し、とくに過疎化の進んだ農村部では深刻な状況にあった。一方で開発の遅れた海外県のレユニオン島では高い出生率を誇っていた。
そんな中、レユニオン選出議員で後に首相にもなったミシェル・ドブレは、島の孤児たちをフランスの過疎地に送れば労働力不足も解消でき、同時に子供たちに本土で充分な教育を受けさせることができると考える。こうして乳児から18歳までの子供たちが飛行機に乗せられた。
リベラシオン紙が伝える証言によると、9歳でフランスに連れてこられた男性は、オルリー空港から教会関係の孤児院、保健局の施設、勤労青年宿舎などをタライ回しにされ、羊飼い、パン屋、左官などの仕事をさせられた。「私には青春なんてものはなかった」という。驚くべきことに、たとえ実の親が見つかった場合でも「被後見未成年者」として親の親権は喪失したものと見なされていたというのだ。明らかに奴隷といっても過言ではない。
「文化」や「教育」をえさに、貧困圏から労働力を供給するというのは、フランスがとってきた常套手段だ。第1次世界大戦で大量の若い労働力を失った直後にも、「勤工倹学(働きながら勉強する)」というキャンペーンを打って中国から大量の「留学生」を受け入れた。たが、実際は彼らの多くが大学に入れぬまま、ただ工場や炭坑で働かされるばかりだったという歴史もある。
今回の国民議会の採択ではUMPなどの右派が反対票を投じた。彼らの「ドブレ氏の政策はレユニオンの福利厚生のためだった」などという言葉を目にすると、一方では自由、平等、人権の尊重などをお題目に掲げながら、もう一方では、経済的に貧しい国や地域は、豊かな国に無理矢理でも教え諭されてしかるべきだという、植民地主義の押しつけがましい論理が、この国には歴然と残っているように思えてならない。(康)
画像:1965年撮影の、カンタル県ケザック町の学校のクラス写真。
レユニオン島の孤児たちの顔が見える。