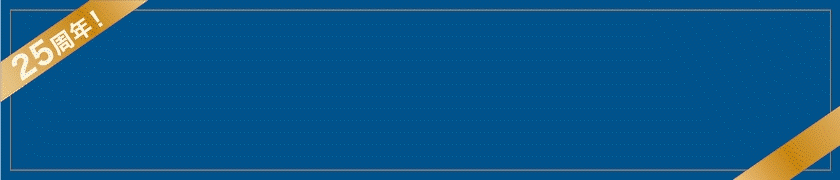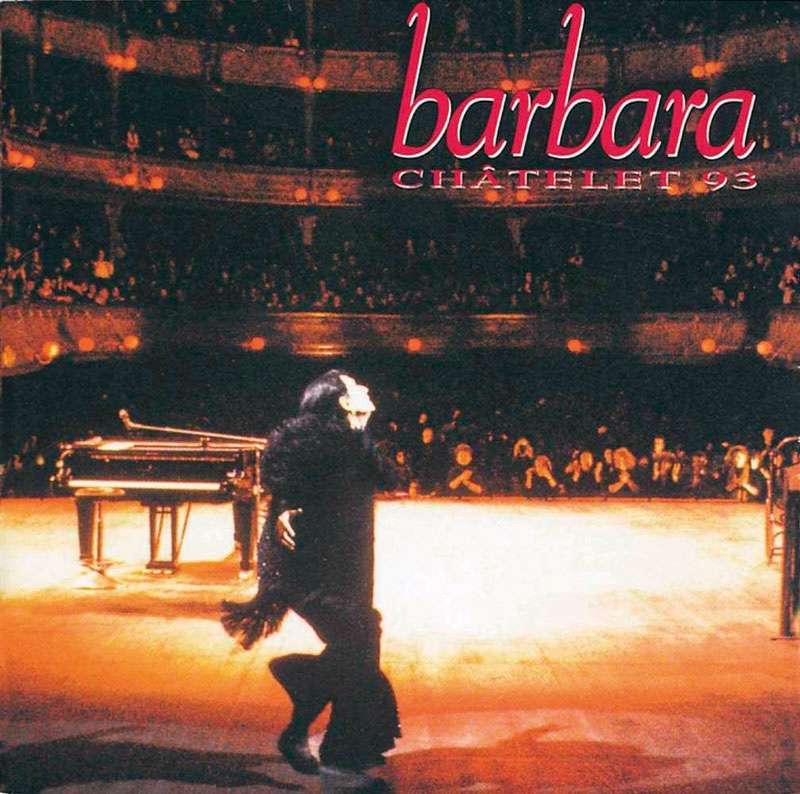最愛のトリュフォー映画
Les Mistons あこがれ 1957 南仏ニームの並木道。木漏れ陽をさっそうとくぐり抜けるのは、自転車に乗る若い女性。まばゆいばかりのベルナデット・ラフォン、当時18歳だ。白いシャツは風に膨らみ、黒いスカートは宙にひらりと舞い上がる。そして円形闘技場跡やテニスコート、森林、映画館と至るところで、人目も気にせず恋人ジェラールとベタベタ戯れている。彼女に憧れ、嫉妬に駆られる5人の悪ガキ軍団は、後をつけてはひやかしたり、邪魔をしたり…。勢い余って自転車のサドルの匂いをかいだりもする。みずみずしいモノクロ映像は青春の輝きに満ち溢れ、人生の無防備ではかない一瞬が美しく切り取られる。恐れを知らぬ26歳のトリュフォーもまた心は悪ガキ軍団とともにあるようで、彼が敵視していたジャン・オーランシュ&ピエール・ボストの脚本家コンビが手がけた映画のポスターを、子供に破らせるという大胆なシーンを挿入した。
南仏ニームの並木道。木漏れ陽をさっそうとくぐり抜けるのは、自転車に乗る若い女性。まばゆいばかりのベルナデット・ラフォン、当時18歳だ。白いシャツは風に膨らみ、黒いスカートは宙にひらりと舞い上がる。そして円形闘技場跡やテニスコート、森林、映画館と至るところで、人目も気にせず恋人ジェラールとベタベタ戯れている。彼女に憧れ、嫉妬に駆られる5人の悪ガキ軍団は、後をつけてはひやかしたり、邪魔をしたり…。勢い余って自転車のサドルの匂いをかいだりもする。みずみずしいモノクロ映像は青春の輝きに満ち溢れ、人生の無防備ではかない一瞬が美しく切り取られる。恐れを知らぬ26歳のトリュフォーもまた心は悪ガキ軍団とともにあるようで、彼が敵視していたジャン・オーランシュ&ピエール・ボストの脚本家コンビが手がけた映画のポスターを、子供に破らせるという大胆なシーンを挿入した。
 南仏ニームの並木道。木漏れ陽をさっそうとくぐり抜けるのは、自転車に乗る若い女性。まばゆいばかりのベルナデット・ラフォン、当時18歳だ。白いシャツは風に膨らみ、黒いスカートは宙にひらりと舞い上がる。そして円形闘技場跡やテニスコート、森林、映画館と至るところで、人目も気にせず恋人ジェラールとベタベタ戯れている。彼女に憧れ、嫉妬に駆られる5人の悪ガキ軍団は、後をつけてはひやかしたり、邪魔をしたり…。勢い余って自転車のサドルの匂いをかいだりもする。みずみずしいモノクロ映像は青春の輝きに満ち溢れ、人生の無防備ではかない一瞬が美しく切り取られる。恐れを知らぬ26歳のトリュフォーもまた心は悪ガキ軍団とともにあるようで、彼が敵視していたジャン・オーランシュ&ピエール・ボストの脚本家コンビが手がけた映画のポスターを、子供に破らせるという大胆なシーンを挿入した。
南仏ニームの並木道。木漏れ陽をさっそうとくぐり抜けるのは、自転車に乗る若い女性。まばゆいばかりのベルナデット・ラフォン、当時18歳だ。白いシャツは風に膨らみ、黒いスカートは宙にひらりと舞い上がる。そして円形闘技場跡やテニスコート、森林、映画館と至るところで、人目も気にせず恋人ジェラールとベタベタ戯れている。彼女に憧れ、嫉妬に駆られる5人の悪ガキ軍団は、後をつけてはひやかしたり、邪魔をしたり…。勢い余って自転車のサドルの匂いをかいだりもする。みずみずしいモノクロ映像は青春の輝きに満ち溢れ、人生の無防備ではかない一瞬が美しく切り取られる。恐れを知らぬ26歳のトリュフォーもまた心は悪ガキ軍団とともにあるようで、彼が敵視していたジャン・オーランシュ&ピエール・ボストの脚本家コンビが手がけた映画のポスターを、子供に破らせるという大胆なシーンを挿入した。 山田宏一氏が指摘するように、女性と子供が極めて魅力的に描かれており、17分という短編ながらもトリュフォー映画の原点がぎゅっと詰まった必見の逸品だ。原題の『Les Mistons』とは「いたずら小憎たち」の意。トリュフォーは本作への賞賛を追い風に、ほどなく『大人は判ってくれない』で長編デビューを飾ることに。やがて黒いドレスに身を包むベルナデットの顔に無邪気な笑顔が消えたように、トリュフォーもまた、監督として無邪気に振る舞える時代も間もなく終わりを迎えるのだった。(瑞)
Les Quatre cents coups 大人は判ってくれない 1959
 いつ観ても何度観ても新鮮に感動する。出くわした状況に呼応するアントワーヌ・ドワネル少年(ジャン=ピエール・レオ)のみずみずしい表情。その真実。それを決して見逃さないカメラ。レオの息吹きでトリュフォーの分身ドワネルが、監督自身の少年期を映画の中によみがえらせる『大人は判ってくれない』。(口はばったい言い方だが)映画芸術を一新させたヌーヴェル・ヴァーグの先陣を切った記念碑的作品。記念碑だけど、この映画は今日も明日も永遠に生きている。それはそこに(口はばったい言い方だが)真実が刻まれているからだ。
いつ観ても何度観ても新鮮に感動する。出くわした状況に呼応するアントワーヌ・ドワネル少年(ジャン=ピエール・レオ)のみずみずしい表情。その真実。それを決して見逃さないカメラ。レオの息吹きでトリュフォーの分身ドワネルが、監督自身の少年期を映画の中によみがえらせる『大人は判ってくれない』。(口はばったい言い方だが)映画芸術を一新させたヌーヴェル・ヴァーグの先陣を切った記念碑的作品。記念碑だけど、この映画は今日も明日も永遠に生きている。それはそこに(口はばったい言い方だが)真実が刻まれているからだ。 学校では、いつも悪いクジを引いて先生に頭ごなしにしかられる。母は自分の都合でしか息子を見ていない。親友と学校をさぼって楽しく遊び回る。言い逃れで口をついて出る虚言。家族で映画を観に出掛ける一時の幸せ。バルザックに熱を上げ奉りボヤ騒ぎを起こす。家出して親友の家にかくまってもらう。タイプライターを盗んだのがきっかけで少年院送りになる。義父は可愛がってはくれていたけどお荷物になればそれまでだ。母は義務的に息子を訪問する。本当に会いたいのは親友だ。海を見たことがなかったドワネル君は、少年院を脱走して海辺まで走りつづける。併走するカメラ。この長い長いトラベリングショットに観客の気持ちも寄り添う。波打ち際のドワネル君の顔のアップでカメラは止まる。彼の将来を思う。私の映画史の記念碑。(吉)
La Peau douce 柔らかい肌 1964
 トリュフォーはカラーで撮るようになってから駄作もあるが、初期のモノクロ作品は大好きだ。中でも『大人は判ってくれない』とこの一作。25歳で事故死したフランソワーズ・ドルレアックが美しい、というのが理由だが、ストーリー展開のうまさにも感心する。
トリュフォーはカラーで撮るようになってから駄作もあるが、初期のモノクロ作品は大好きだ。中でも『大人は判ってくれない』とこの一作。25歳で事故死したフランソワーズ・ドルレアックが美しい、というのが理由だが、ストーリー展開のうまさにも感心する。 中年の評論家ピエール(ジャン・ドサイ)は、若いスチュワーデス、ニコル(ドルレアック)に一目ぼれ。そこから、彼の平穏な生活が狂い始める。パリでは二人でゆっくりできる場がない。講演旅行にニコルを連れて行くが、浮気がばれることにヒヤヒヤしっぱなしで、ニコルに失望される。ようやく小さなホテルで愛し合う二人、と、どこにでもありそうな浮気話だが…。
冒頭から、ジョルジュ・ドルリューの暗く沈んだ音楽が流れ、作品の基調を作っていく。撮影は『突然炎のごとく』も撮ったラウル・クタールで、オールロケ、高感度のフィルムで余分な照明は避けているから、強いコントラストはないが、グレーのトーンが限りなく豊か。そのカメラがアップでとらえる、眠っているかのように無防備に横たわるドルレアックの体、その肌のかすかなふるえがこちらまでに伝わってくる。
ラストで、カフェのテーブルについているピエールは妻の猟銃で射殺される。二人の視線のやりとりだけで緊張感を伝えるわざは、トリュフォーが尊敬していたヒッチコックゆずり。いろいろな女を愛したトリュフォーが、彼自身の分身ともいえるピエールを、冷酷に瞬時に殺しているのは、いさぎよい。(真)
Baisers volés 夜霧の恋人たち 1968
 トリュフォーの最高傑作だとは思っていない。でも初めて観た時期が私自身のパリ生活の初期にあたっていた、つまり主人公ドワネル同様に私自身が大人と青春期をさまよっている時だった、という偶然の一致が、私がこの作品へ共感を抱く重要な要素となっていることは間違いない。
トリュフォーの最高傑作だとは思っていない。でも初めて観た時期が私自身のパリ生活の初期にあたっていた、つまり主人公ドワネル同様に私自身が大人と青春期をさまよっている時だった、という偶然の一致が、私がこの作品へ共感を抱く重要な要素となっていることは間違いない。 ドワネルは、兵役を免除されてからホテルの夜警、私立探偵、そこから派生する靴屋での見習い、そしてテレビのSOS修理工というように、短期間に様々な体験をしつつ大人社会に足を踏み入れる。私たちもこの人生見習い生ドワネル=作家トリュフォーの視点を借りながら、当時のパリ、そこに生きる人々やファッション、風俗に開眼していく。
やはりこの作品好きの相棒と何度一緒に観たことだろう。毎回あのすてきなシーンと出会う度に私たちは苦笑してしまう。ドワネルは、あこがれの年上女性(デルフィーヌ・セリーグ)と食後のコーヒーを飲むチャンスに恵まれる。ところがすっかりあがってしまったドワネルは、女性から「あなた音楽は好きなの?」と質問され「ウィ、ムッシュー」と返答した直後、すべてを投げだし階段を一挙に駆け降りる。たとえそのあとのシーンで、セリーグが「私たちは皆唯一の存在なの…」と素晴らしく感動的な台詞を吐きドワネルとしばしの時を過ごすとしても、私と相棒の感動は、端から見ても恥ずかしいほど新鮮なドワネルの動揺から始まっている。(海)
Domicile conjugal 家庭 1970
 『大人は判ってくれない』で始まるアントワーヌ・ドワネルシリーズの第4作目。良家の娘と無事に結婚したアントワーヌだけれど、相変わらずどこかずれていて、とぼけていて、やることなすこと面白おかしい。妻は立派にヴァイオリンの教師として働いているのに、彼は、中庭でせかせかと怪しげな仕事に励んだり、たいして収入がないくせに知り合いにお金を貸したり、日本女性のキョーコと浮気をしたり。アントワーヌの変わらない駄目男ぶりに、このシリーズのファンは思わず目を細めることになる。そう、この映画の何よりの魅力はユーモアだ。フランス映画というと、どこか深刻だったり、キザでロマンチックなイメージがあるけれど、この映画にはくだらないギャクが満載。例えば、キョーコに「もしもし」の意味を教わったアントワーヌが、「じゃあ、『Allo, allo』は、『モシモシ、モシモシ』なの?」と聞くところなどは思わず爆笑。女性を愛してやまなかったトリュフォーのこと。日本人の彼女たちを、こうやって笑わせていたのかもしれない。
『大人は判ってくれない』で始まるアントワーヌ・ドワネルシリーズの第4作目。良家の娘と無事に結婚したアントワーヌだけれど、相変わらずどこかずれていて、とぼけていて、やることなすこと面白おかしい。妻は立派にヴァイオリンの教師として働いているのに、彼は、中庭でせかせかと怪しげな仕事に励んだり、たいして収入がないくせに知り合いにお金を貸したり、日本女性のキョーコと浮気をしたり。アントワーヌの変わらない駄目男ぶりに、このシリーズのファンは思わず目を細めることになる。そう、この映画の何よりの魅力はユーモアだ。フランス映画というと、どこか深刻だったり、キザでロマンチックなイメージがあるけれど、この映画にはくだらないギャクが満載。例えば、キョーコに「もしもし」の意味を教わったアントワーヌが、「じゃあ、『Allo, allo』は、『モシモシ、モシモシ』なの?」と聞くところなどは思わず爆笑。女性を愛してやまなかったトリュフォーのこと。日本人の彼女たちを、こうやって笑わせていたのかもしれない。 そして、注目すべきはジャック・タチの出演! たった一瞬だけれど、タチ演ずるユロ氏がメトロのホームに登場する。また、息子が生まれた時にアントワーヌが電話をかける相手は、あのジャン・ユスターシュ。この映画は、カイエ・デュ・シネマ誌の批評家であり、骨の髄までシネフィルだったトリュフォーの交友録にもなっている。(さ)
L’Argent de poche トリュフォーの思春期 1976
 舞台は、オーベルニュ地方の小さな町だ。乳児から思春期までの12人ほどの子供たちの日常生活が描かれている。トリュフォーは、「子供たちとの撮影はとても難しいけれど、驚きにあふれている。成功したときは、シナリオよりも6倍はよいシーンができ上がる」と言ったそうだけれど、確かに、この映画には子供ならではのセリフ、リアクションにあふれて生き生きしている。
舞台は、オーベルニュ地方の小さな町だ。乳児から思春期までの12人ほどの子供たちの日常生活が描かれている。トリュフォーは、「子供たちとの撮影はとても難しいけれど、驚きにあふれている。成功したときは、シナリオよりも6倍はよいシーンができ上がる」と言ったそうだけれど、確かに、この映画には子供ならではのセリフ、リアクションにあふれて生き生きしている。 僕がこの映画を初めて観たのは、12歳くらいのとき。映画の中の子供たちと同じくらいの年齢だったので、すっかりのめりこんでしまった。なんといっても強烈な印象を受けたのは、登場人物のひとり、パトリック。親友の家に食事に招かれてご馳走を平らげた彼は、気のきいたお礼を言おうとするあまり、淡い恋心を抱いている友だちの母親に、「Merci de ce frugal repas(簡素な食事を、どうもありがとうございました)」と言い間違えてしまう。このセリフがすっかり気に入って、子供の時に何度も繰り返した。今でも人に招かれると、冗談でこのセリフを使ってしまうことがあるほど。
そして、誰からも愛されず、家族から虐待されているジュリアンの存在も忘れることができない。作品のラスト、教師が、現実の世界で生きていかなくてはいけない子供たちに「困難な子供時代を過ごした人は、保護され、愛された人たちより、大人の世界によりうまく直面できる」と語りかける。この言葉は、そのままトリュフォー自身のメッセージ。愛情の大切さについて、そして、人生の厳しさと不思議さについての率直なスピーチには、子供でなくても思わずハッとさせられる。(エ)
L’Enfant sauvage 野性の少年 1970
 大好きなこの作品も、トリュフォーだけでなく僕の人生にとっても傷つきやすい一時期である、子供時代についての映画だ。この作品で心を打たれるのは、森の中で発見され、ジャン・イタール博士に教育された子供の実話「アヴェロンのヴィクトール」を映画化する時の、トリュフォーの心遣い。だが、歩く、きちんと食べる、服を着る、ベッドで眠る、ものを見分ける、それを言葉で言う、と延々と繰り返される教育のシーンは、退屈であるかもしれない。しかし、この作品を見ていると、自分の子供時代に戻っていき、おそらく、今の私たちにはごく「自然」になったものが、じつは学んだものである、ということが見えてくる。
大好きなこの作品も、トリュフォーだけでなく僕の人生にとっても傷つきやすい一時期である、子供時代についての映画だ。この作品で心を打たれるのは、森の中で発見され、ジャン・イタール博士に教育された子供の実話「アヴェロンのヴィクトール」を映画化する時の、トリュフォーの心遣い。だが、歩く、きちんと食べる、服を着る、ベッドで眠る、ものを見分ける、それを言葉で言う、と延々と繰り返される教育のシーンは、退屈であるかもしれない。しかし、この作品を見ていると、自分の子供時代に戻っていき、おそらく、今の私たちにはごく「自然」になったものが、じつは学んだものである、ということが見えてくる。 トリュフォーは、自身が演じる博士が書いたことを正確に追っているのだが、この野生児のまわりに巨大な夢を張りめぐらす。冒頭シーンはトリュフォーの想像だ。木の枝に高くとまっている人間の夢、空気のように軽やかな夢、そこから野生児は引き離され、ハンターに捕らえられる。イタールは、自身で抑圧している野性を夢見る。その夢を映像化しながら、トリュフォーも夢見る。1968年以降の私たちは、言語や理性以前の、あらゆる社会が私たちの欲動を抑圧する以前の、人間の中にあった真正なもの、それを探し出すという夢を追い続けたのではなかったか? それがこの作品の言いたいことであり、だから、僕は、この名作を二度見ただけだが、記憶の奥深くにしっかりと残っているのだ。決して忘れてはいけない宝のように。(ク)
La Chambre verte 緑色の部屋 1978
 物語が終わっても、ジュリアン(トリュフォー)とセシリア(ナタリー・バイ)のどちらに軍配が上がったのか判らない。俳優として見ても、この二人の対決に決着を付けるのは難しい。
物語が終わっても、ジュリアン(トリュフォー)とセシリア(ナタリー・バイ)のどちらに軍配が上がったのか判らない。俳優として見ても、この二人の対決に決着を付けるのは難しい。 最愛の妻ジュリーを亡くしたジュリアンは、妻の写真や遺品を飾った部屋に閉じこもり、亡き妻を愛し続けることを誓う日々を送っている。薄暗い部屋でローソクを灯し、椅子に腰掛ける「取り残された」ジュリアンの背中に、トリュフォー本人の「癒されない孤独」を見るようで胸がつまる。その姿は、まるで仏壇の前で無心に祈るかのような静寂すらたたえている。生と死という重いテーマを掘り下げ、しかも、他の役者の姿を借りず、トリュフォー自身がその孤独を引き出しているところに、深い感動を覚える。
一方、セシリアは、死者を尊重しながらも、「生」に前向きである。美しくても、時間の止まってしまった写真の中のジュリーとは対照的に、ジュリアンに惹かれながらも、彼の死に対する考え方に戸惑い、自分の昔の愛人の死に涙し、それでも孤独の中にいるジュリアンに愛を告白するセシリアは、その「瞬間」を生きている。最後に倒れるジュリアンを彼女が胸に抱く姿は、廃墟だったチャペルの中に放置されていたピエタ像と重なる。生と死、永遠の愛と拒絶。しかし、全てを超越して「今、包み込む」という究極の慈悲を、セシリアは教えてくれる。(尾)
1 2