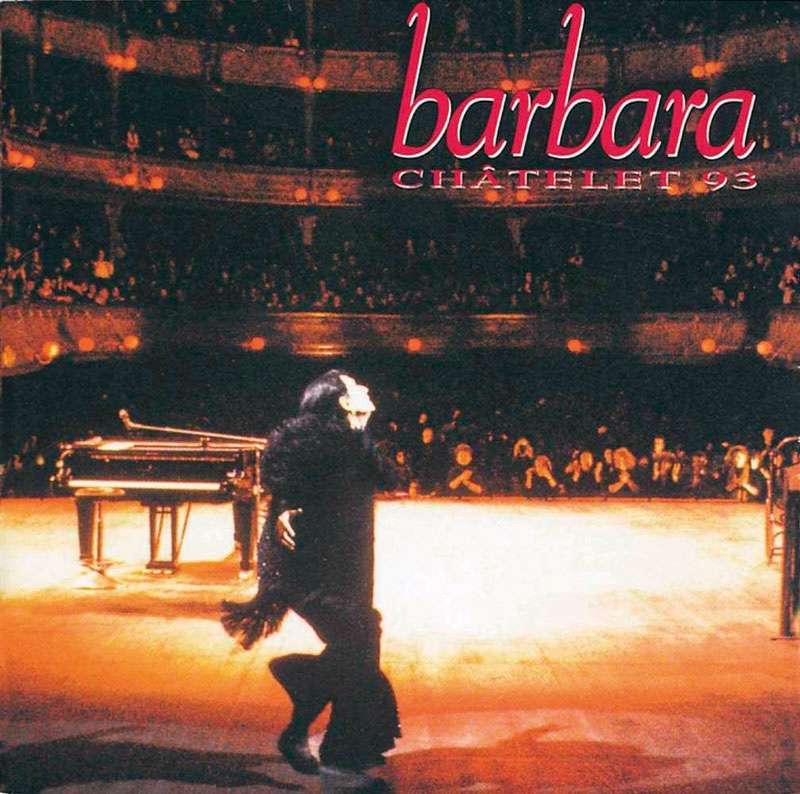「ポタージュこそフランス国民食の根底をなすもので…」
ちょっとした食いしん坊の本棚には、ブリア= サヴァラン(1755-1826)の『美味礼賛』が必ずといっていいほどある。宗教ではつつしむべき大罪のひとつとされている「美食」だけれど、これを読むと、食べることがいかに人間らしい知的な行為かがとうとうと述べられていて痛快である。そんなサヴァラン氏は、トリュフやチョコレートなど官能的な食べ物だけでなく、ポトフやブイヨン、ポタージュについてももちろん言及している。いわく、「よきブイヨンを得るためには水を徐々に沸きたたせなければならない。(…)人は味をよくするためにブイヨンの中に葉だの根だのを入れる。(…)これがいわゆるポタージュである。ポタージュは軽くて栄養のある健康な食品であって、だれにでも向く。それは胃を喜ばせて、食物を受け入れそれを消化する用意をさせる。(…)まったく、ポタージュこそフランス国民食の根底をなすもので、数世紀の経験がわが国のポタージュをこれほど完全なものにしたのだと思う。」(関根秀雄訳)
栄養たっぷりのブイヨンやポタージュは、確かにフランスが誇る国民食なのかもしれない。それを証明するかのように、バルザック(1799-1850)の『人間喜劇』には、「スープ」または「ポタージュ」が実に65回も出てくる。それは温かかったり、冷たかったり、牛のすね肉入りのボリュームたっぷりのものだったり、シンプルなハーブのスープだったりする。それは毎日の食卓によくのぼるもの、そして病人や落ち込んでいる人にもつくられる、人をホッとさせてくれるもの。今も昔も変わらないスープの役割を確認できる。
田舎詩人のリュシアンが主役の『幻滅』の冒頭部では、愛情にあふれたポタージュスープが登場する。敬愛する兄リュシアンのため、妹のエーヴは、かまどの火でつくったスープを兄にさしだす。「『ぼくたち、みんな幸せになれるんだよ』リュシアンは言い、ポタージュスープを大さじですくって飲みこんだ。」(野崎歓訳)。このときのリュシアンは、田舎の下町で暮らす純真な青年。パリでの生活や未来の栄光に胸躍らせていた。「大さじですくって」という表現からは、健康的な食欲が感じられてたのしくなる。
でも、この小説を読み進める読者は、都会のパリに出てからの、この青年のすさまじい変化を知ることになる。生活のためにしがないジャーナリストとなった彼は、家庭の温かいスープの味、そして優しい妹のことまですっかり忘れてしまう。その代わり、舞台がはねた女優や、記者仲間たちと通う、パリのレストランでの豪華な「souper」(夜食)に夢中になっていくのだ…。(さ)