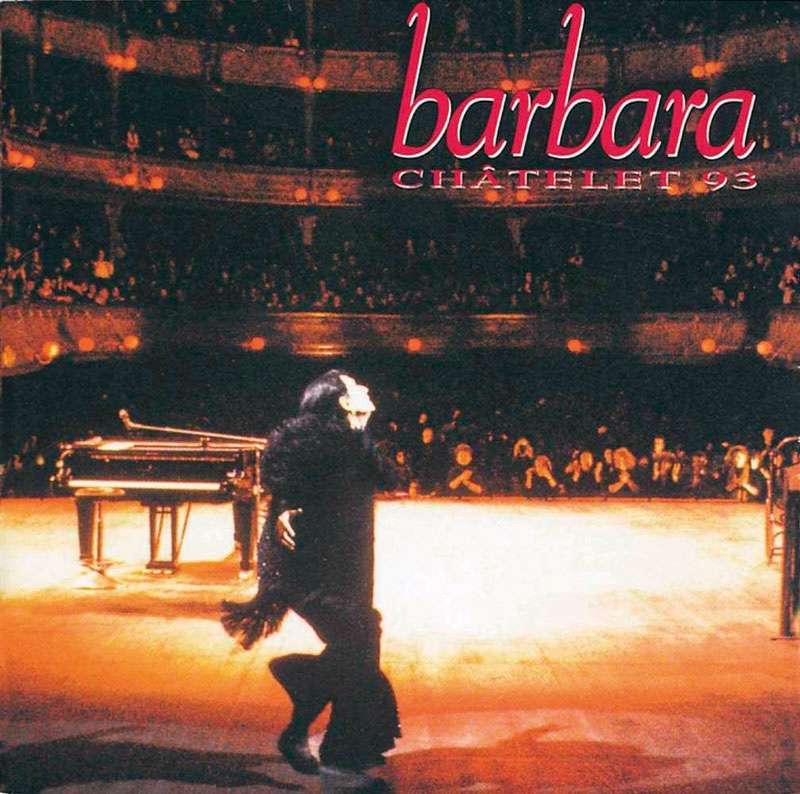Catherine Jahan -textiles peints-
「光に強く、色落ちもしないこの技術を身につければ画家のように自由にイメージを投影できる」
かつてはファッション誌の編集者や撮影スタイリストといった肩書きを持って活躍していたカトリーヌさん。常にモードと隣り合わせで仕事をしてきたが、工場で規則的に処理された「血の通っていない色やモチーフの連続」には、いつも飽き飽きしていたという。
ある日、ふらっと出かけたパーティで、「布地本来の持ち味を活かした着色技術」を、ロンドンで指導しているイギリス人女性に出会う。フランスでは学べない技術だ。「光に強く、色落ちもしないこの技術を身につければ、画家のように自由にイメージを投影できる」。そう直感した彼女は、すぐにイギリスへ渡る。「自分が本当にしたいことのため、仕事もクライアントもすべて捨てた」。当時35歳だったカトリーヌさん、ゼロからの再出発だった。
その後は無事に留学を終え、パリに戻る。異国で学んだ技術をベースに、今度は自らわき出る発想で、より個性的なアレンジを試すようになっていく。18年経った今では、ディオール、ラクロワ、バレンシアガ、エルヴェ・エル・ルルーなど名だたるブランドが、彼女の秘技のおこぼれにあやかろうと、コラボレーションを望んでくる。それにもかかわらず、決して成功の上にあぐらをかくことのない彼女は、「いつも自分にとって新しいことを探し続けていて、満足することはまれ」と笑う。
さて、ひと言でオートクチュールの仕事といっても、クリエイターごとに、仕事の仕方がまったく異なるという。「クリスチャン・ラクロワなら、テーマは例えば「花」といった方向性を立てたら、あとは双方向で提案し合い、模索しながら進んでいく。一方ジョン・ガリアーノの場合は、彼の頭の中で精密な世界観が出来上がっているから、それにどれだけ近づけるかがポイント」だという。仕事の度に、クライアントの方法論に従わねばならないのは、相手が一流デザイナーでも個人客の場合でも一緒。とはいえ、オートクチュールで働く魅力は、それぞれのブランドが独自で入手するレアな素材が存分に使えることにある。「モンマルトルのマルシェ・サンピエールでは絶対に手に入らないわ!」
そんなカトリーヌさんだが、将来は、自分のブランドを立ち上げたいと意欲を語る。「手作業だからひとつとして同じものが存在しない洋服よ」。いつも彼女が立ち戻るのは、やはり血の通った洋服作りだった。(瑞)
クリスチャン・ラクロワのドレス。
シルクオーガンジーのスカーフ。「どんな方法で模様を入れたかわからないような作品が好き」だとか。
画家のように筆を使いながら、布地に模様を描いていく。
模様を描き終わったら、長い棒に布を巻き付けていく。
巻き付けた布を、特製の高温保湿機に入れ、色を布に定着させる。
シルクスクリーン、リノカット(版画技法のひとつ)、ステンシル…。いろんなテクニックを応用し、世界でひとつのテキスタイルを創り出していく。