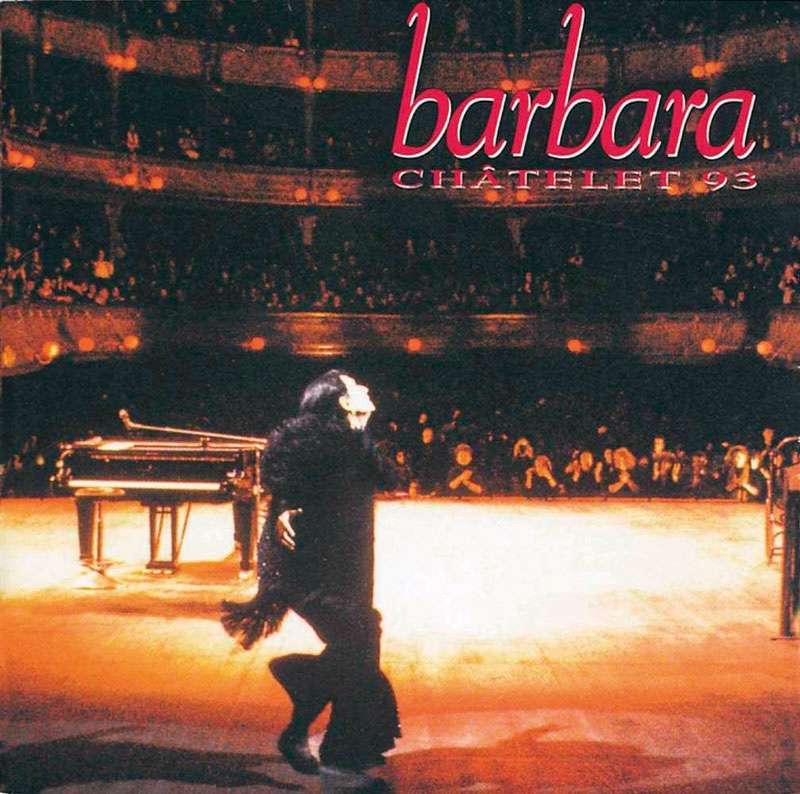フランスの核開発とその実態
フランスの原子力の歴史は、核兵器の開発から始まったといえる。原子力全般の管理当局である原子力庁(1)は核兵器製造を管理するものとして発足した。つまり、民事核と軍事核は表裏一体である。核戦略に関しても、その後の原子力エネルギー政策に関しても、国民議会でまともに討議されたことは一度としてなかった。 フランスは周知のごとく、ド・ゴール政権以来、米ソの核の傘下に入らずに独自の核抑止力によって自国の主権を守ることを国策としてきたから、日本のような核兵器廃絶運動は希薄だった。フランス人の大半が核兵器を当然のことと受け止める反面、放射能の危険性に関しては極めて曖昧な知識しか持っていなかった。サハラや太平洋モルロア環礁における核実験もほとんど真相は明らかにされずにきたが、今年2月に「ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール」誌(2)は、軍部が初めて公開した資料に基づき、惨憺たる事実を明らかにした。 核産業の出発点であるウランの採掘開発から再処理工場に至るまで、フランス核燃料公社コジェマ社(3)が一手に引き受けている。鉱山の大半はフランスのほぼ中央部にあるリムーザン地方にあり、現在ではそのほとんどが閉山され、ウランはアフリカなど諸外国から輸入されている。しかし残土や残滓物を廃坑の穴に野ざらしに放置しており、人形峠(4)よりも無惨な状態である。ウラン坑で働いていた労働者は、放射能の危険性について無知のままだった。現地での残土の野ざらし放置に対する住民の告発と反対運動が組織され始めたのは、やっと80年代の後半から90年代に入ってからである。 1958年、南フランスのマルクールに最初の核兵器用プルトニウムの抽出工場が完成、操業してきた。ノルマンディー上陸作戦の展開されたコタンタン半島、ミレーの「晩鐘」でも有名な岬には、ラ・アーグ再処理工場があり、1966年以来使用済み核燃料の再処理を行っている。

反対運動のはじまり
地元には、当初から建設に反対し、闘ってきた市民団体クリラン(5)が現在も反対運動を続けている。彼らは同時期に建設されたフラマンヴィル原発にも反対してきた。当時、再処理工場がどのような作業をする工場なのか、住民に充分な説明がされたことなどなかった。300人近い漁師や反対派市民たちが結束して反対運動を展開したが、政府は3千人の機動隊を送り込み、鎮圧した。 60年代には、サハラ砂漠や仏領ポリネシアで核実験が盛んに行われたが、現地では、旧東ドイツを思わせる徹底した諜報活動と、軍・警察の検閲と規制で、反対派、独立派はおろか、本土から来た記者なども完全に封じ込められてきた (2)。
速増殖炉「スーパーフェニックス」 フランス本土の反対運動のなかで、もっとも大きな展開があったのは、スーパーフェニックス高速増殖炉(SPX)の反対運動だった。1977年7月31日、建設予定地のクレイ・マルヴィルで全国から10万人近い反対派の市民たちが結集した。近隣のスイスやドイツ、ベルギー、イタリア、スペインの反核派も集まった。SPXが東部の国境に近かったこと、また高速増殖炉が事故になった場合の脅威を知っていたからだった。しかし、それに対しフランス政府はまたも大量の機動隊と騎馬隊を投入し、催涙弾を水平撃ちするなどして極めて過酷な弾圧を行ない、死者1名、重傷5名、負傷100名を出した。 SPXは、兵器級プルトニウムを大量に抽出し、核兵器の生産を容易にする軍事的な影の任務を帯びていたため、仏政府は専制的な手段で、この中性子高速炉計画を貫徹しようとする政治意志を持っていたのはうなずける。だが、この危険極まりない原子炉はほとんどまともに機能したことがなかった。10年間にたったの半年くらいしか稼働しなかった。「もんじゅ」以上のナトリウム漏れ事故を数度起こしているが、発見が早かったため、大事には至らなかっただけのことである。しかし、この弾圧を境に大きな反対運動のうねりは退いていった。現地はラ・アーグと並んで過疎地であるにもかかわらず、地元の自治体には多額の税金が落ち、高給取りの職員が二千人以上定着したのである。 SPXを含む原発反対運動は、だからといってそう簡単に霧散霧消したわけではなかった。1976年から始まったブルターニュの西部先端、フィニステール県の岬に近いプロゴフの原発計画には、78年9月の最初の反対デモに5千人、一週間後のブレストのデモには1万5千人と膨れ上がった。それからというもの80年まで、数千人から数万人のデモが毎回組織され、同年2月、3月は、毎日のようにデモや建設予定地でのピケが繰り返された。3月16日の反対集会には6万人近い反対派市民が集まった。火炎瓶と催涙弾の応酬や、度重なる機動隊との衝突と弾圧で逮捕者を数多く出しながらも、反対運動は決して収束しなかった。法廷でも激しい支援闘争が展開された。プロゴフ原発計画は中止され、ついに反対運動は勝利したのだ。 その後、昨年6月1日に行われたロワール河河口のカルネ原発計画の反対集会でも地元の住民たちが2万人も結集し、この地方の反核精神の強さを見せた。結局、この原発計画も白紙撤回に終わったのである。
SPXを含む原発反対運動は、だからといってそう簡単に霧散霧消したわけではなかった。1976年から始まったブルターニュの西部先端、フィニステール県の岬に近いプロゴフの原発計画には、78年9月の最初の反対デモに5千人、一週間後のブレストのデモには1万5千人と膨れ上がった。それからというもの80年まで、数千人から数万人のデモが毎回組織され、同年2月、3月は、毎日のようにデモや建設予定地でのピケが繰り返された。3月16日の反対集会には6万人近い反対派市民が集まった。火炎瓶と催涙弾の応酬や、度重なる機動隊との衝突と弾圧で逮捕者を数多く出しながらも、反対運動は決して収束しなかった。法廷でも激しい支援闘争が展開された。プロゴフ原発計画は中止され、ついに反対運動は勝利したのだ。 その後、昨年6月1日に行われたロワール河河口のカルネ原発計画の反対集会でも地元の住民たちが2万人も結集し、この地方の反核精神の強さを見せた。結局、この原発計画も白紙撤回に終わったのである。
論調の変化 その背景には様々な要因が挙げられる。今日、フランス電力公社は、電力を過剰生産しており(電力の75%以上が原子力により生産され、フランスは電力の輸出国だ)、当分、新しい原発は必要としてないこと、廃炉にかかる費用や廃棄物の処理費用などを考慮すると、原発の経済性は明確ではなくなってきている。エネルギー政策を原子力一本槍でいく時代は過ぎ、推進側内部でも天然ガスや他の再生可能エネルギー(風力、太陽熱など)の可能性を真剣に検討する時代になってきている。そして、左翼連立政権に代わり、緑の党党首が環境大臣に任命されるという大転換期にきている。
独立放射能研究所の誕生 1986年のチェルノブイリ事故は、フランスにおいては、日本のような反原発運動の大衆的なうねりを生まなかった代わりに、アクロ(6)とクリ=ラッド(7)という二つの独立放射能研究所を生んだ。フランス政府の「チェルノブイリの放射能の雲はフランスには来なかった」という虚言を暴いたのも、これらの創設に参加した科学者たちである。 アクロは、とりわけラ・アーグ再処理工場を中心に西部地域の放射能監視を行ない、コジェマが提出している資料の欺瞞性や不完全な調査、放射能汚染を指摘してきた。クリ=ラッドは、ラ・アーグも含めマルクールの核施設周辺やリムーザン地方の放射能測定と分析を行い、前者は周辺地域のカマルグ地方でプルトニウムが検出されたことを明らかにし、後者は、廃坑に棄てられた残土の中に強い放射能を検出しており、さらに一部にはチェルノブイリ級の線量を示す場所などを報告している。またチェルノブイリの放射能の雲によって、フランス東部国境一帯やコルシカ島に極めて強い汚染地帯があることを厳密な測定分析によって明らかにしている。 アクロとクリ=ラッドの研究分析作業に対し、もはや核ロビーも反論しえなくなり、両者とも公認された信頼性のある独立研究所の地位を獲得している。これは問題意識を明確に持った、各地の国立大学の研究者や教授たちが、真実の追及に努力を重ねてきた結果といえる。 フランスでは、これら民間の手で設立された放射能研究所が、政府の核タブーの壁に与えたインパクトは重要だ。政府関係諸機関は虚言を言い続けることができなくなったばかりでなく、核当局は情報公開をせざるをえなくなってきており、今年2月2日の政府閣内委員会の声明でも、情報の透明性を高めるために、政府の外部に独立した諮問機関を設ける方針を打ちだしている。 また、ワイズ・パリ(8)のような民間情報機関が83年に設立以来、果たした役割も大きい。同機関はラ・アーグ再処理工場などに関するレポートや、モックス核燃料の将来についての総合分析を日本の原子力資料情報室等と国際的なチームを組んで行い、非常に高い国際的評価を受けている。
核産業の不透明性 このような民間機関の大きな役割が意味を持つようになった背景には、企業・政府が一体となった産政共同体があり、軍事組織のような機密と検閲に守られた産業構造があることを見逃してはならないだろう。企業が巨大になり、生産や生産物の危険性が高まるほど、機密機構がより強固になり、そこでの業務は全体主義的管制システムによって管理されるから、民主的公正さからはますます遠ざかることになる。どこの核施設も、ナチスの強制収容所を連想させるような鉄条網や電流を流した鉄線を幾重にも張り巡らし、物々しい警備のもとに作業が行われている。 この業界では、監督する側が監督される企業側に天下りしたり、同じ学閥の仲間が重要なポストに就いたりする癒着関係ができ上がっていることを、市民が察知しはじめている。人類の未来を決定してしまうほどの重要な事柄が、一部の核官僚の手にのみ握られているということは、民主主義の原則からいっても許容しがたい。 二年前、マンシュ中・低レベル核廃棄物貯蔵所から、プルトニウムを含む高レベルの放射性核種が検出されて大問題になった。これは市民団体クリランと独立放射能研究所アクロ、クリ=ラッドなどの運動と監視があって初めて明るみに出された事実で、「ル・モンド」、「リベラシオン」など全国紙が大きく取り上げている。完璧な管理を謳っていたコジェマ社と、放射性廃棄物管理庁アンドラ(9)の運営管理のずさんさが公になりはじめた。 核廃棄物の問題は産業廃棄物の問題の中でもっとも厄介なものである。処分方法を持たずに、生産ばかりが先行するゆえに、原子力産業は「トイレなきマンション」とも呼ばれる。原発が稼働し続けるかぎり、永遠に核廃棄物は増え続けることになる。核廃棄物の中には24万年以上の長い半減期(放射能量が半減するのに必要な歳月)を持つものもある。増え続ける核のゴミをどうするのか、明快な解答はいまだない。
二年前、マンシュ中・低レベル核廃棄物貯蔵所から、プルトニウムを含む高レベルの放射性核種が検出されて大問題になった。これは市民団体クリランと独立放射能研究所アクロ、クリ=ラッドなどの運動と監視があって初めて明るみに出された事実で、「ル・モンド」、「リベラシオン」など全国紙が大きく取り上げている。完璧な管理を謳っていたコジェマ社と、放射性廃棄物管理庁アンドラ(9)の運営管理のずさんさが公になりはじめた。 核廃棄物の問題は産業廃棄物の問題の中でもっとも厄介なものである。処分方法を持たずに、生産ばかりが先行するゆえに、原子力産業は「トイレなきマンション」とも呼ばれる。原発が稼働し続けるかぎり、永遠に核廃棄物は増え続けることになる。核廃棄物の中には24万年以上の長い半減期(放射能量が半減するのに必要な歳月)を持つものもある。増え続ける核のゴミをどうするのか、明快な解答はいまだない。
白血病多発の恐れ? 1996年12月、医学研究分野で信頼性の高い雑誌 « 英国医学ジャーナル」に、フランスのブザンソン大学医学部の統計疫学専門家ジャン=フランソワ・ヴィエル教授の、ラ・アーグ再処理工場周辺の子供の白血病に関する研究(10)が掲載され、発病の増加を示す示唆的な数値が発表された。それは工場周辺に生活する子供たちが海岸を散歩したり、魚介類を定期的に摂取すると、生物連鎖によって濃縮された放射能が体内に吸収され、白血病が発病するリスクが高くなることを示したものだ。 この話題はすぐフランスに伝わり、大きな反響を呼び起こした。現地では猛烈な議論が沸騰し、連日、新聞はこの問題を報じた。地元の30人以上の母親たちが「怒れる母親の会」を結成し、すべての情報の公開と放射能排出ゼロを求めて立ち上がった。 当時のジュペ内閣は、パリ大学薬学部長スーロー教授を座長とする科学委員会に調査を命じたが、この報告(11)は調査期間の短さと内容からいっても、また核産業側と政府機関からの代表が大半を占める科学委員会のメンバーの構成からいっても、公平と客観性に欠くものだった。 同じころ、再処理工場の排水パイプが干潮時に海面に露出し、通常値の3千倍に及ぶ高い放射能がクリ=ラッドによって測定された。コジェマ社は、パイプ内の残滓物を棄てないことを条件に排水パイプの洗浄作業を行うことにしたが、グリーンピース国際チームは研究船を出し、作業を監視するとともに、排出口の沈殿物を採集し調査した。同社の清掃作業はいい加減で、多くの残滓物が海に放出されたことが判明した。このような状況の中で、テレビでも海洋ドキュメンタリー番組として知られているフランス第3チャンネルの「タラサ」がラ・アーグ問題を扱い、民放TF1も反対派、推進派両者を招いて討論番組を放映した。ここに至って、環境派市民たちと核産業側との戦争といってもいいほどの対立が表面化した。
地に墮ちた超不死鳥とその後 一方、SPXは度重なるトラブルのために停止していたが、経済的効率があまりにも悪く、投資額とバランスがとてもとれないと、保守・革新両政権から判断されてきて、98年2月2日ジョスパン現政権が最終的な閉鎖を再確認した。この最終決定に至った裏には、昨年の総選挙前に社会党と緑の党の間で合意されていたとはいえ、20年以上も継続されてきた粘り強い反対運動の歴史がある。大集会が度々開かれ、全国行進も行われてきた。こうした運動を多くの科学者がサポートしてきたし、マルヴィル委員会をはじめとする現地の運動の実に根強い闘いがあったばかりでなく、緑の党やグリーンピース(12)、ヨーロッパ人反対委員会(13)などのラディカルなアクションもあった。SPXが経済的な破綻を起こしたのも事実だが、空気や水に触れるとすぐ爆発を引き起こす 6トン近い液体ナトリウムを技術的に完璧にコントロールできないこと、ましてや操業の結果として極めて毒性の高い放射性核種プルトニウムが作り出されることに、エコロジストたちが反対する大きな理由があった。 ところで、SPXのある現地では、閉鎖決定後、日常生活の社会的雰囲気が非常に悪化している。地元での圧倒的多数派である推進派が、SPX閉鎖に絶対反対を唱えて、連日、激しい閉鎖反対運動を展開している。それに肩入れしているのは、与党であるはずのフランス共産党やその影響の強いCGT系労働組合である。村の道路という道路は、「閉鎖反対」のスローガンが書かれた張り紙で埋め尽くされている。閉鎖に賛成しようものなら、恐喝電話や手紙がくるという。民主主義の国フランスにおいてさえ、こうした状況の中で、現地ではほとんど自由に自分の意見を述べることができないほどの隠微な雰囲気が支配しているのである。 しかし、ヨーロッパで最後までフランスが固執していた高速増殖炉計画が破綻し、撤退した事実だけは揺がないだろう。