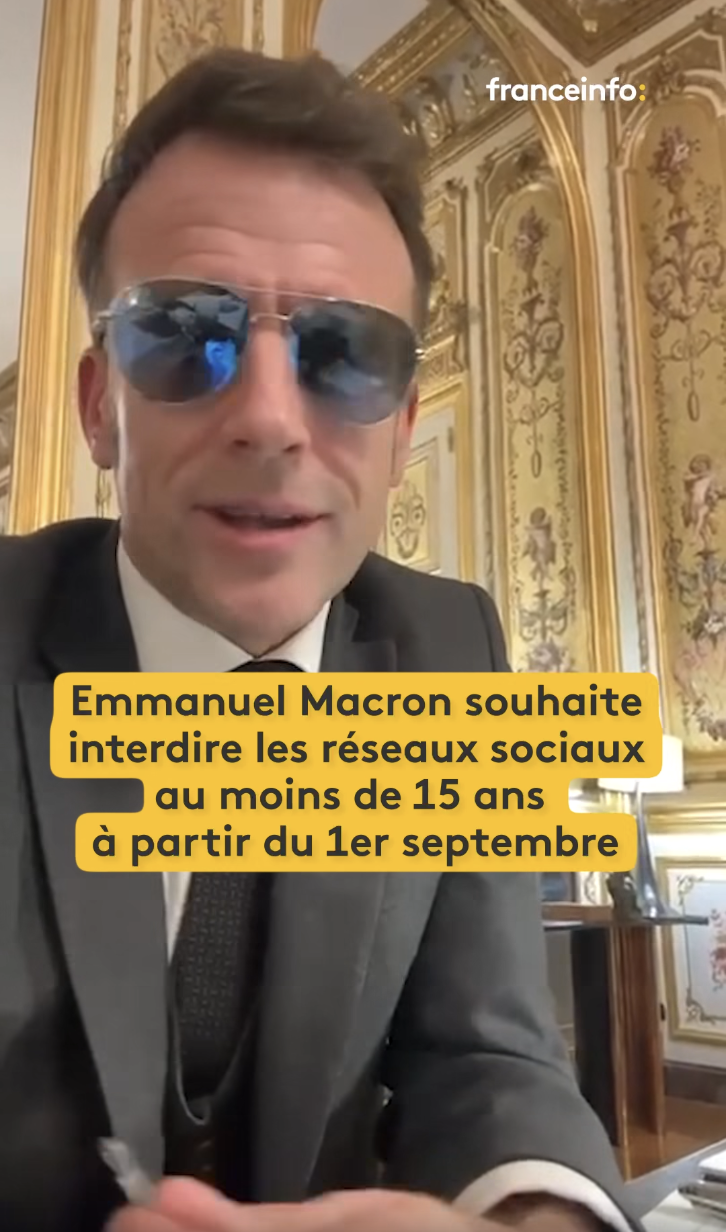大統領への権力集中を進めたマクロン政権のもとで、フランスの民主主義は後退した。それを表わす現象として、極右イデオロギーの蔓延・一般化がある。日本の「ネトウヨ」と同様、フランスでもネット上で差別発言やヘイトスピーチが交わされる「ファッショ領域 fachosphère」が以前から活発だったが、紙媒体の雑誌や地上デジタルのテレビ局でも、差別発言やヘイトスピーチに近い表現や内容の言説が目立つようになった。
なかでも衝撃的だったのは、去る(2021年)4月21日に超保守(極右)週刊誌に掲載された声明だ。退職軍人ら約100人が大統領・政府・議員にあてて、「イスラム原理主義と郊外の暴徒たちや、一部の反レイシスト達によって、フランスは分裂の危機にある。手遅れになって市民戦争が爆発し、我々の文明の価値観を守るために現役の仲間たちが出動する前に、手を打て」と訴えた。60年前の同じ日付にアルジェで、ド・ゴール大統領のアルジェリア政策に反対し植民地維持をめざすフランス軍の将軍たちがクーデター未遂を起こした史実を踏まえ、軍の反乱を示唆する内容だ(写真下)。早速、国民連合RN(国民戦線FNから改名)党首マリーヌ・ルペンなど極右の政治家たちは、声明の内容に賛同を示した。ところが、大統領、政府、防衛大臣は沈黙したままだったため、4月26日に左派野党「屈服しないフランス」は記者会見を開き、同党議員23名がパリ検事正に告訴を要請したと告げ、現役軍人の声明署名者の処罰を防衛大臣に求めた。

実際、独立インターネット新聞メディアパルトは昨年7月と今年3月、ネオ・ナチのシンボル(ハーケンクロイツなど)をネット上で示す軍人数十人の存在(14の連隊に所属)を確認したと発信している。また、警察内の極右思想の影響についても以前から、独立メディアによる調査が報道されている。しかし、レイシズムの発言や行為の内部告発がなされても、監察機関(IGPN)は警察内の組織のため、問題にされた警官がほとんど処罰されない(稀に処罰されても軽い)のに対して、逆に内部告発者が処罰を受けたケースが複数ある。
言論の領域にとどまらず、しばらく前から極右団体による脅しや示威行為が増えている。難民救援を行う市民に対する威嚇アクション、反ファシズム本屋や運動家への攻撃に加え、今年の3月25日、20世紀前半に活発だった極右・王党派団体アクション・フランスセーズがオクシタニー地域圏議会に侵入し、「イスラムー極左はフランスの売国奴」という巨大垂れ幕を会議場の床に広げた。議会侵入という行為は、アメリカ大統領選後のバイデン当選を承認中の1月6日、トランプ支持者(極右・白人至上主義者)がアメリカ合衆国議会議事堂を襲撃した事件(クーデター未遂)を思い起こさせる。トランプ政権のもとで広まったアメリカの「オルト・ライト(オルタナ右翼)」(反多文化主義・反移民、反フェミニズム、陰謀説など)が、フランスの「伝統的」極右にも影響を与えているようだ。
たとえば昨年6月、アメリカの警官によるジョージ・フロイド殺害事件の後、フランスでも警察の暴力に抗議する反レイシズムの大きなデモが何度も行われたが、6月13日のレピュブリック広場での集会では極右団体のメンバーたちが広場に面した建物の屋根に上り、「反白人レイシズムの被害者に正義を!」と書かれた大きな垂れ幕を掲げた(冒頭写真)。パリ警視庁はなぜかこの明らかな挑発行為(「反白人レイシズム」はオルト・ライトの表現であり、屋根の上に登るのは基本的に禁止)に対してすぐに対応しなかったため、建物に住む市民が窓から垂れ幕を引きちぎり、数名のデモ参加者が屋根に上がってこの挑発を中断させた。

マクロン政権と「左翼」政党の右傾化
極右イデオロギーの急激な一般化は、マクロン政権が昨年秋以降、国民連合RN(国民戦線FNから変名)党首マリーヌ・ルペンのメインテーマである「治安」をフランス社会最大の問題点に据えたことに起因している。2022年大統領選挙に向けて、高い支持率を保つ対抗候補ルペンの土俵に乗り、ルペン支持者にアピールして得票しようという魂胆からだ。同時に、コロナ危機やその結果の経済危機、とりわけ貧富の差を拡大させた経済政策への批判を封じ、現実の社会問題から市民の関心をそらそうという策略である。
折しも10月にイスラム原理主義者による中学教師殺害事件が起きて、多くの主要メディアでは治安やイスラムについて「脅威」を強調する報道が加熱化した。24時間テレビ局の一つC Newsでは、難民やイスラム教徒に対するヘイトスピーチで有罪になったことがあるコメンテーターのエリック・ゼムールをレギュラーで起用し、他のメディアでも差別やヘイトすれすれの直接的ではない表現や、事実を曲げた言い方をするコメンテーターやジャーナリストが増えた。極右の差別思考が広まる現象は「ルペン化」と呼ばれていたが、ルペンの治安偏重と移民・イスラム敵視路線は、主要メディアでメインストリームになってしまったのだ。
マクロン政権内でも、ダルマナン内務大臣やブランケール教育大臣などがイスラムを敵視する発言を繰り返した。また、ジョージ・フロイト殺害事件の後、フランスでも抗議が強まった「警察による暴力」問題においても、ダルマナン内相は警官の不当な暴力やレイシズム発言・行為の事実を認めない主要警官組合に同調し、政府主導の「グローバル治安」法案が練られた。
警官の映像・画像の撮影・流布の禁止、ドローンやカメラによる市民の監視、顔認証システムの全般化など、市民の自由を侵害し、社会運動の弾圧と監視を強化する内容で、ジャーナリストや弁護士をはじめ、大勢の市民が反対デモを繰り返した。この法案は内外の人権団体だけでなく、国連人権理事会や欧州評議会の人権委員会からも、報道の権利と市民の自由を侵害すると糾弾された。事実、ジョージ・フロイト殺害事件と同様、ビデオのおかげで警官による不当な暴力が証明されたケースは多い。法案は今年4月に最終採択された後、憲法評議会から自由侵害度の最も高い条項を棄却されて最悪の事態は免れたが、市民の自由の制限は2015年テロ後の「緊急事態」(社会党オランド政権)以来、じわじわと進んでいる。
政府は続いて、「共和国の原理尊重の強化 renforcement des principes républicains」という妙な呼称の法案を提出した。イスラム教徒・イスラム系フランス人の「分離主義」を仮定し、市民団体などを規制しようとする内容で、それを機に法律で禁止されている一夫多妻制や、個人の自由として禁止できるはずがない公共空間でのヴェール着用を問題にしたりなど、イスラム系フランス人への偏見と敵意に満ちた発言がメディア空間を覆った。また、差別を受ける非ヨーロッパ系の女性を対象にしたワークショップを催す学生組合を、メディアが「白人と男性を除外する差別」と騒ぎ立て(これは前述したオルト・ライトの手口)、それに極右、保守、与党のみならず社会党の政治家までが声を揃える異常な出来事も起きた。
政権とメディアの「ルペン化」や、ネットの「ファッショ領域」と極右団体の活動の激化に対する批判の声は、主要メディアではほとんど聞かれなくなったばかりか、昨年の秋以降は「屈服しないフランス」や緑の党(EELV)の政治家を「イスラムー極左 islamo-gauchistes」と呼び、彼らをイスラム原理主義テロリストの「共犯」であるかのように攻撃するバッシングが始まった。前述した声明の退職軍人が「一部の反レイシスト」を非国民扱いしたのと同じ思考構造であり、歴史的には「ユダヤーボリシェヴィキ」という第一次・第二次大戦の間の時期に流布された反ユダヤ・反共産主義の差別表現と同様の思考構造から生まれた中傷である。
ところが、ヴィダル高等教育大臣は今年の2月、「『イスラムー極左』の影響が増大して大学における学問の自由が危うくなったため、国立科学研究センターに調査を依頼する」とテレビで発言したのだ。国立科学研究センターと学術界は早速、「イスラムー極左」という言葉も実体も社会科学において存在しないと抗議し、大臣の発言は政治による学問の統制(マッカーシズム)だと反発した。その後、調査について大臣は沈黙しているが、「イスラムー極左」という実体のない言葉と「過激な極左研究者の悪影響」というイメージは、メディアのせいで広まってしまった。調査が行われなくても、研究費用や職を必要とする研究者を萎縮させる効果は、すでに出ているという。
民主主義の防波堤の決壊と市民の奮起
さて、4月にパリ近郊のランブイエで、イスラム原理主義者(精神傷害もあったらしい)による警官殺害事件が起きたために、警官組合や右派のメディアは「警察に対する攻撃・暴力の激化」を騒ぎ立てた。そして5月19日、殺された警官の追悼と称して、警官組合は国民議会前でのデモを呼びかけた。折しも国会では司法改革が討議されていて、警官組合のチラシは「甘すぎる司法」を糾弾する内容だったため、このデモは立法と司法機関への明らかな圧力である。驚いたことに、国民連合の議員や極右の有名コメンテーター(ゼムール)などが参列したこのデモに、警察の指導を司どるはずの内務大臣までが参列したのだ(三権分立の無視)。
さらに驚愕させられたのは、デモに極右と保守議員だけでなく社会党の第一書記長、パリ市長のアンヌ・イダルゴ(社会党)、緑の党のヤニック・ジャド、共産党書記長のファビアン・ルッセルまで参列したことだ。唯一、「屈服しないフランスLFI」だけがこの警官デモをボイコットし、警官組合が国会前で圧力をかけるのは共和国と民主主義の原理からの逸脱だと批判した。現に、警官組合の代表たちはデモで「警察にとって問題は司法だ」、「多数を動員できれば防波堤は決壊するだろう、防波堤とはつまり憲法による拘束だ」などと述べたのだから、そんな集会に参列した政治家の政治倫理は地に落ちたと言っていい。
「グローバル治安」法案によってフランスの民主主義は重大な危機を迎え、この警官デモの前にも民主主義の防波堤の決壊は始まっている。マクロン大統領は昨年12月に週刊誌「レクスプレス」のインタビューで、ナチス・ドイツに協力したヴィシー政権の長ペタン元帥や、反ユダヤ主義の作家シャルル・モラス(王党派右翼団体アクション・フランセーズで活動)を評価する発言をし、啓蒙時代と大革命以来の平等理念を疑問視する発言をした。今年の2月には、ダルマナン内務大臣と国民連合党首マリーヌ・ルペンの討論が公共テレビ局で行われ、その討論ではマクロン政権の内務大臣の方がルペンより過激な発言をした。マクロン政権と主要メディアが「ルペン化」し、あるいはさらに極右化をエスカレートさせる流れに、保守と与党のみならず「左翼」を自称する政党や人々も追随していった。5月の警官デモへの保守・左翼政党議員の参加によって、民主主義の防波堤の決壊はさらに進んだと言えるだろう。
極右勢力はますます図に乗ったようで、6月6日、ネット上有名な極右人物が「メランション(「屈服しないフランス LFI」代表、大統領選候補)に投票する極左」をもじった人形を銃弾とナイフでズタズタにする衝撃的なビデオが流れた。しかし、メランションへのバッシングには熱心な主要メディアの反応は鈍く、大統領や内務大臣からは一言のコメントもなかった。その2日後、地方巡回中のマクロン大統領が極右系の男性にビンタをくらうという前代未聞の出来事が起きるが、メディアは「極右」という言葉を使わず、大統領自身も極右を問題視するコメントをしなかった。
一方、民主主義の原理を擁護し、その強化を望む市民団体、人権団体、労組、政治運動体などは、極右の蔓延に対抗するための統一行動を実現させるために連絡を取り合い、6月12日、100以上の団体が共同で呼びかけた「極右に対抗する自由のためのデモ」が全国140か所で行われた(下の写真)。パリではクリシー広場からレピュブリック広場へのデモ行進に7万人、全国で15万人(主催者発表)が路上に繰り出した。その直前、コンセイユ・デタ(国務院)がダルマナン内務大臣が昨年秋に発布した「国家治安構想」について、ケトリング(デモ参加者を狭い空間に囲い込んで閉じ込める)やジャーナリストの自由侵害の項目を棄却したせいか、パリのデモでは久しぶりに治安部隊の姿が見えず(遠巻きに待機したため)、気持ちよく行進できた。

ところが、このデモの出発直前にインタビューを受けていたジャン=リュック・メランションは、走りよった男に小麦粉をふりかけられた。犯人はすぐに逮捕されずにメディアのインタビューを受け、その映像からのネット上検索で彼が極右系の人物であることが判明した。
その翌週には、緑の党のパリ市議でフェミニスト・LGBT活動家の女性がルーアンでの講演会で嫌がらせを受け、ヌヴェル・アキテーヌ地域圏では「屈服しないフランス」と緑の党の選挙候補のポスター貼りをしていたボランティアが、国民連合の活動家にナイフで脅された。マクロン政権が極右系の威嚇や示威行動に対してきっぱりとした批判をせず、環境・社会運動家や政権に批判的な左派には過度の弾圧やバッシングを続けてきた今、極右系による攻撃が増加・エスカレートしている。フランスの民主主義の危機を打開するために、市民の奮起が求められている。
そんな中、6月20日に行われた地域圏と県議会選挙の第1次投票では棄権率が66,7%、有権者の3人に2人に至った。棄権はしばらく前から増え続けているが、前回(2015年)の地域圏選挙(第1次50,1%)や昨年の市町村選挙(第1次55%)を大幅に上回る史上最高記録である。今回はコロナの影響も少なく、政治(家)に幻滅した有権者がいかに多いかが示されている。また、これまで不満票を集めていた国民連合は、メディアや世論調査が予測したよりずっと低い得票率だった(前回の地域圏選挙27%から18,7%に減少。投票率自体が下がったため、得票数の減少も大きい)。そして、マクロンの与党「共和国前進」の得票率も低かった。極右のテーマである治安やイスラムを騒ぎ立てても得票にはつながらず、政権への拒絶反応は明らかだ。最初から大統領選をマクロン対ルペンの二者対決に絞った報道しかしないメディアは、民主主義の基本に戻って市民の実態と社会問題に目を向けるべきだが、その兆候はない。(飛)
2021年6月6日に掲載したものを、2022年4月26日に再掲載。