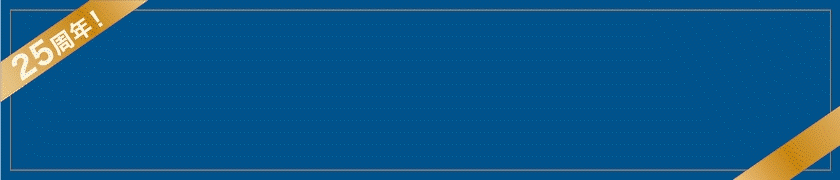©Nuri Bilge Ceylan films
前作『雪の轍』(2014)がカンヌ映画祭の最高賞パルムドールを受賞したトルコのヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督。今年のカンヌに出品した本作もまた、相変わらずの完成度の高さだ。閑古鳥が鳴く夏の映画館で、ひとり孤独を抱きしめ向き合いたい、188分の濃密な実存ドラマに仕上がっている。
大学を卒業した青年シナンは、バスに揺られ田舎の実家へ。未来ある若者の帰郷のはずが、すぐに停滞した空気に取り囲まれる。とりわけ借金を重ね、周囲から相手にされぬ教員の父にはうんざりだ。
シナンの夢は作家になること。書き溜めた草稿の印刷代を捻出すべく、町長や地元の会社のボスに会い行く。あるいは同級生やイスラムの導師、地元の作家とも偶然出会う。人と顔を付き合わせれば、その度に長い対話が始まる。望まぬ結婚を控えた女友達との会話は意味深だ。「君の心はどうしたい?」とシナンが聞けば、「もう長らく私の心は聞こえない」と彼女。そして風が立ち、木々が騒ぐ。ジェイラン作品において、鬱屈した人間世界を包み込む物言わぬ自然は、その存在感が圧倒的に雄弁だ。
では女友達とくらべ、シナンが自由かと言えば、実はそうでもない。次第に彼のエゴや未熟さ、深い孤独が露わとなり、軽蔑の対象だった父の姿にも重なってゆく。これは運命から逃れられぬ人間の物語。人間の本質を見据えるドストエフスキー的な眼差しや、悲劇と喜劇のチェーホフ的な表裏一体性など、偉大な文学遺産を養分にしながら、完全に自らの映画芸術に血肉化してみせる。デジタルカメラのブレだけは惜しい気もしたが、どんなに平凡な空間を切り取っても、自ずと映画然とした風格が漂うのはさすが。やはりジェイランは現代最高峰の映画作家のひとりなのだ。(瑞)