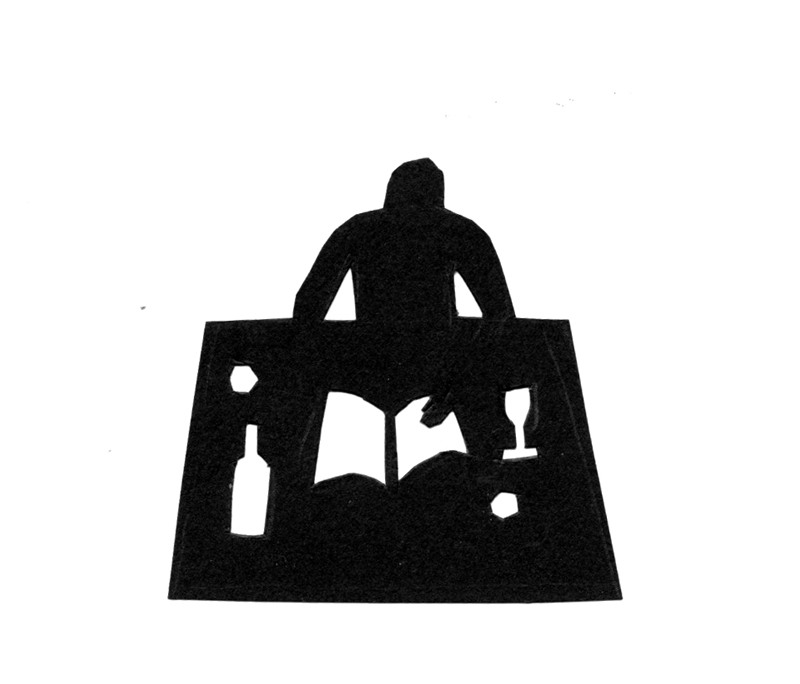母親を知らずに育ったルソーだったけれど、その人生は多様な女性たちにいろどられている。何人か挙げられる重要な女性の中でも、孤児同然だったルソーの人生をすっかり変えてしまったのがヴァラン夫人だった。
母親を知らずに育ったルソーだったけれど、その人生は多様な女性たちにいろどられている。何人か挙げられる重要な女性の中でも、孤児同然だったルソーの人生をすっかり変えてしまったのがヴァラン夫人だった。
出会ってから程なく「ママン」「坊や」と呼びあうようになったふたりの関係は約10年間続き、その間に、少年だったルソーは青年に成長する。サヴォワの田舎にあるレ・シャルメット邸で暮らした数年について、ルソーはのちに書いている。「ここでわたしの生涯の、短い幸福の時がはじまる。真に生きたといいうる資格をさずけてくれた、平和だがつかの間の時が、ここにやってくる」。(桑原武夫訳)
恋人であり保護者である年上の女性が整えてくれる愛の巣は、ルソーにとってまたとない学び舎でもあった。図書室にはギリシア、ローマの古典から、ライプニッツやデカルトなどの哲学本、自然科学にいたるまであらゆる本がそろっていた。音楽を学びはじめたのもこの頃で、のちに楽譜の記述法についての論文を書いたり、オペラを作曲するようになったりするのも、この時代があったからこそ。
トリノでカトリックに改宗したてのころは、ナシや乳製品、パン、そしてワインを口にする「もっとも幸福な美食家」だったルソーが、この時期なにを食べていたのかは分からない。分かっているのは、朝食のメニュー。
「ふつう、わたしたちの朝食はミルク・コーヒーだった。これが一日中でいちばん気分がおちつき、くつろいで話のできる時間だ。これにはかなり時間をかけたが、おかげでわたしは朝食がたいへんすきになった」。
また、「(料理が冷めないと食事をしない癖のある)ママンがたべられるようになるのを待つ間、自分たち二人のことをしゃべりながら、たのしい食事をした」ともある。この時期のルソーにとって、ママンとの会話がなによりのご馳走だったようだ。(さ)