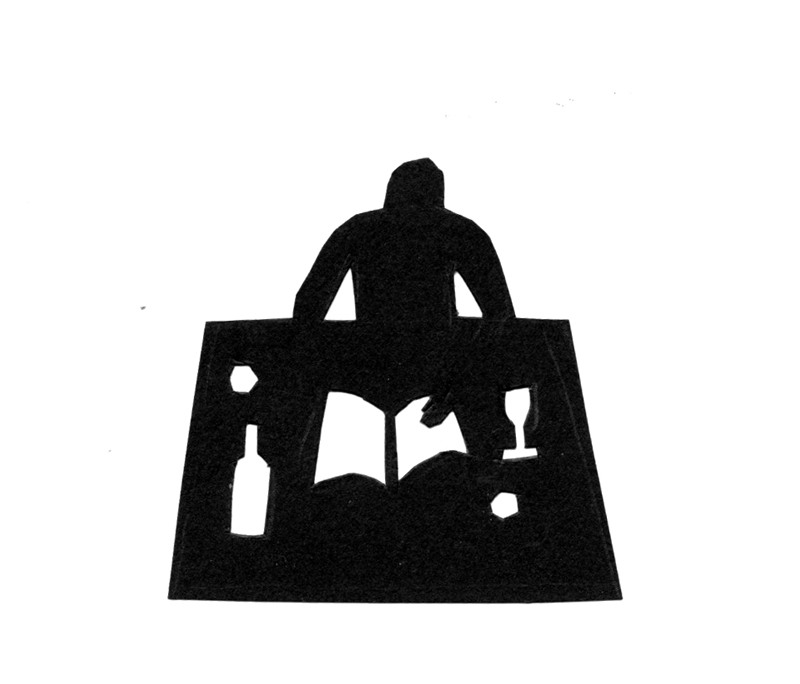18世紀に書かれた一種の教育書『エミール』(1762年)において、触覚、聴覚、視覚といった感覚の中で、わたしたちにもっとも重要なのは味覚だとされている。著者である哲学者ルソーにとっての好ましい味覚とは、自然に近いもの。「結局、わたしたちの味覚は単純であればあるほどいっそう普遍的」(今野一雄訳)とするルソーが、子どもに食べさせたいと考えるのは「果物、乳製品、ふつうのパンよりやや微妙な味がするオーヴンで焼いた菓子のようなもの」。
ルソーがそのようなシンプルな食事をすすめる理由は、子どもを「口ぜいたく」にするのを避けるため。「運命が子どもにもたらすものをだれが確実に知ることができよう。どんなことにおいても、子どもにきちんときまった形式をあたえて、必要が生じたときにそれを変えることにひどくつらい思いをさせるようなことはしまい」。たしかに、一度ぜいたくに慣れてしまうと、ごくふつうのものでは心が満足しなくなってしまう。小さい時から当たり前のようにぜいたくをしてそれが習慣として身につくと、それを失った時の喪失感もそれなりだろう。
そんな考えもあってか、一時は話題の人物としてパリの社交界でもてはやされたことのあるルソーは、「食べることを知らないのはフランス人だけだ」と切り捨てる。そして、それは「フランス人が口にすることのできる料理をつくるにはまったく特別の技術が必要なのだから」と説明している。たかが料理のこととあなどるなかれ、フランス革命の主役たちがルソーに共鳴した背景は、こんなくだりにもにじみ出ているように思う。
口がいやしい著者などは、そんな「特別の技術」で作られた18世紀のフランス料理を食べてみたいものだと夢を見る。(さ)