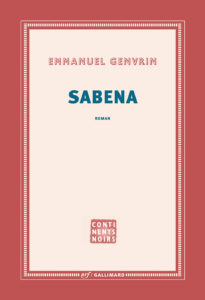
『 サベナ(仮題) 』
SABENA
エマニュエル・ジャンヴラン著
Éditions Gallimard刊
アフリカの島々、その歴史と多様性。
私たちはよく「アフリカ」を一つの塊のようなものとして語りがちだ。料理、映画、文学、音楽…。それがどの国の、どの地域から由来したものであろうと、そこには「アフリカ」という一つの名が与えられる。一見して無害なこうした呼び名に、もちろん悪意はないが、他者の多様性をないがしろにしている点で、それはとても暴力的な行為にもなりうる。しかしこう書いている私もまた、こうした本を読むときにはいつでも、自分がいかに無知であったかを思い知らされるのだ。
アフリカ南東部、モザンビーク付近には、フランス旧植民地のマダガスカルやコモロ連合と現海外県のレユニオンとマヨット、旧イギリス領セーシェルやモーリシャスなどが集合する。個々の島々で違った歴史的経緯をたどったことは、少しは知っているつもりでいた。しかし互いの島々で、あるいは一つの島の内部でさえ、時に敵対的な関係があることは、あまり知られていないのではないだろうか。その背景には植民地時代から現在も続くフランスとの緊密な関係があるのだが、この小説では、この歴史から生まれた親子三世代が、その島々を渡りながら生きた様が描かれている。
「サベナ」、虐殺の生き残り。
「サベナ」、この名を聞いてピンとくる人は、フランスにも、コモロにも、そして事件が起きたマダガスカルにさえおそらくほとんどいない。コモロは植民地体制下でマダガスカルに行政的に併合されていたことがあり、その関係で後者には前者から多くの人々が労働力や学生として移住していた。そんななか1976年12月、マダガスカルの都市マジュンガで、コモロの人々が大量に虐殺される事件が起きる。犠牲者はわずか3日でおよそ2000人に上ったと言われる。マダガスカルの人々は彼らを鉈で切り刻み、女性たちをレイプし、家々を焼き払った。原因は民族的対立とも、貧困層から比較的裕福な層への怨恨とも言われるが、いずれにせよこの時期までに「外国人」とみなされたコモロの人々に対するマダガスカルの人々の憎悪は、頂点へと達していたのだった。
コモロ政府はこの件に対応して、77年1月に16,000人ものコモロの人々を自国へ帰還させる。このとき彼らを運び出す助けをしたのがベルギーの航空会社「サベナ」(現在は廃業)であり、以降、この会社の名がそのまま、この事件をきっかけにコモロへと帰還した人々、虐殺の生き残りを指すために使われるようになったのである。
父も母も無き娘たち。
この本の一人目の主人公、ファイーザはその「サベナ」の一人だ。まだ高校生の頃に事件で家族を失った彼女は、その類い稀な美貌のために、ある大物軍人の目にとまる。このボルドー生まれの仏人傭兵ボブ・ドナールは、60年代からアフリカの数々の紛争地域で軍事作戦に加わった実在の人物。その彼がとりわけ深く関わりを持ったのがコモロだった。彼はこの国で複数のクーデターを行い、大統領の警護隊を組織し、かの地で強大な権力をものにした。
ドナールの数多い愛人の一人となったファイーザは、彼との間に娘ビビを生む。しかし彼女は失った愛人を求めて、ビビを置き去りにする。そしてビビもまた、母がかつて自分にそうしたように、自分の娘シャティを一人残して旅立つのだ。その行き先のレユニオンで、ビビは不動産詐欺で一財を築くことになるが、彼女に憧れ追ってきたシャティと共に、最終的に悲惨な末路を辿ることになる。
売春、ドラッグ、窃盗、レイプ、暗殺、詐欺、誘拐…。あらゆる犯罪のオンパレードであるこの物語に、およそ「善人」と呼べるような人は登場しない。しかし結局、父も母も失った女たちがこの汚れた世界で求め続けたのは、お金でなはく、誰かからの深い愛情だけだった。それがはっきりと分かる小説の最後の場面で、少しだけ、読者は救われた気持ちになる。(須)

[著者]
エマニュエル・ジャンヴラン
52年フランス中部シャルトル生まれ。マダガスカルに叔父を持つ。79年レユニオンにヴォラール劇場を創設、同地で数々の戯曲を書き上演する。小説は本作で2作目となる。







