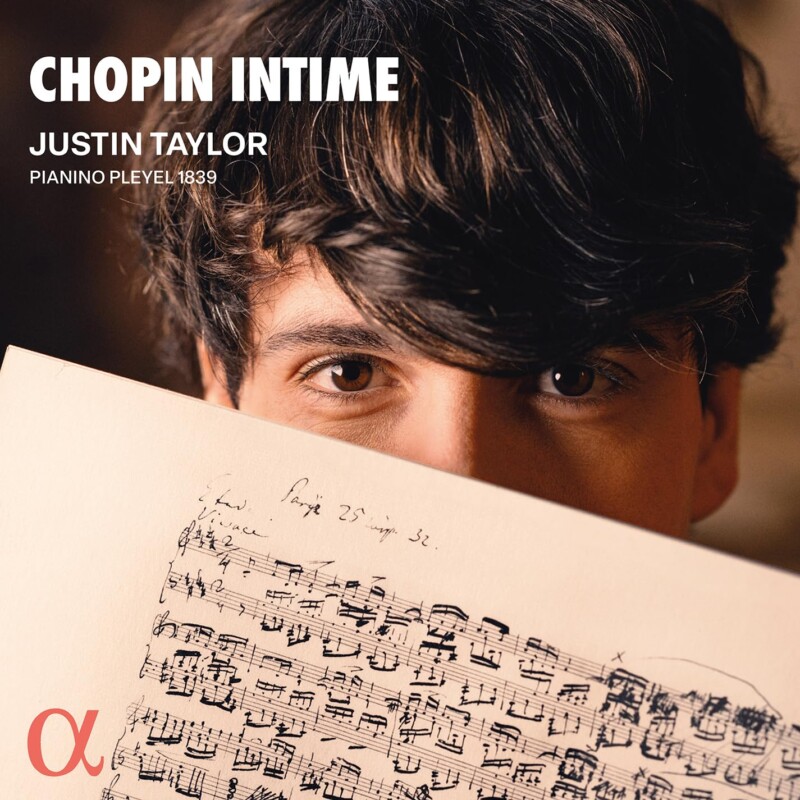Maurice Ravel, complete works for solo piano
モーリス・ラヴェルは、ひとまわり年上のクロード・ドビュッシーと並び、20世紀初めに革新的なピアノ曲を書いた。ラヴェルのピアノのソロのための曲は、10分に満たないものがほとんどで、それぞれ『古風なメヌエット』、『悲しい鳥』、『洋上の小舟』といった詩的な題がついている。こうした曲を聴くには、ベルトラン・シャマユ―のラヴェル・ピアノソロ全曲アルバム(2枚組)がうってつけだ。
1曲目は『水の戯れ』で、シャマユ―の澄み切った音色と流れるようなアルペジオによって、水の動きにつれて反映する光の踊りが目に浮かぶようだ。次いで『なき王女のためのパヴァーヌ』。フォーレのピアノ曲を思わせるような、シンプルで心にしみいる悲歌だが、シャマユ―のおさえのきいた内省的なタッチが美しい。そしてこのリサイタルの頂点は、『オンディーヌ(水の精)』、『絞首台』、『スカルボ』の3曲からなる『夜のガスパール』*だろう。それぞれの曲の性格を、ときには印象派的にときには暗く沈んだ表情で、あざやかにとらえている。『スカルボ』は、高度の技巧を必要とする難曲だが、シャマユ―は、今そこで音楽が生まれ出ているかのように、みごとなダイナミックで弾き通す。
ラヴェルは晩年に2曲のピアノ協奏曲を並行して書いた。『左手のための協奏曲』**は、第一次世界大戦で右手を失ったピアニストに依頼されたもので、戦争の暗雲ただよう風景を感じさせる響きではじまり、ピアノが力強く入りこむ。こういう曲は単に上手に弾かれてもなにかが欠けてしまう。少し古いが、力強いタッチでドラマ性あふれるサンソン・フランソワの熱演が忘れられない。

もう1曲は『ピアノ協奏曲ト長調』***で、第1楽章はパシッというむちのひと打ちではじまり、どこまでも軽やかでリズミカル。つづくアダージョの美しさは比類がない。フルートやオーボエなどの木管楽器が奏でる繊細な旋律を、ピアノがオブリガート風に装飾していく。この曲を得意とするのはマルタ・アルゲリッチだが、彼女の最初の録音で、クラウディオ・アバドが指揮するベルリンフィルとの競演を超えることはなかなかむずかしい。Compact Disc/12€前後。(真)