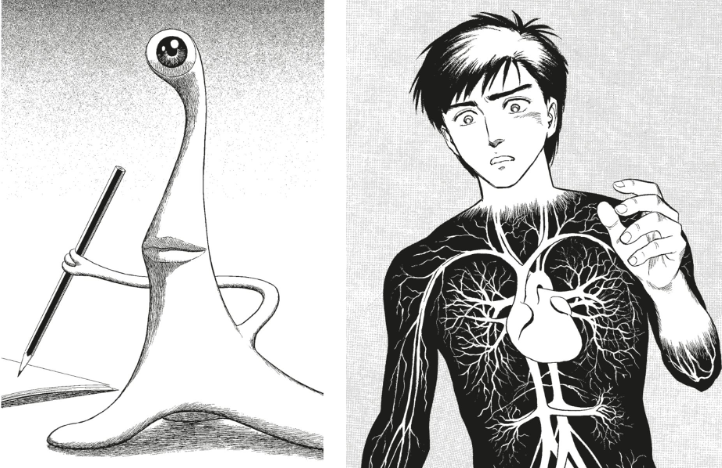2006年7月8日、仏北部の町で交際2年後にモスレム系カップルが結婚式を挙げた。が、初夜の純白のシーツは血で染まらなかった。 新郎は、処女だと言っていた新婦にだまされたと憤慨し、リール裁判所で婚姻取消訴訟を起こした。
2006年7月8日、仏北部の町で交際2年後にモスレム系カップルが結婚式を挙げた。が、初夜の純白のシーツは血で染まらなかった。 新郎は、処女だと言っていた新婦にだまされたと憤慨し、リール裁判所で婚姻取消訴訟を起こした。
4月1日の婚姻取消判決をリベラシオン紙(5/31)が暴露。イスラム原理主義国ならまだしも共和国フランスで、処女性を新婦の「本質的資質」とみなす新郎の言い分を認めた判決に国民が「女権の侵害」と動転。日本ならバツイチのレッテルを張られ、生涯記録が残る離婚でなく婚姻取消に双方が同意した。
ダチ法相も同判決を容認。同裁判是非論争の嵐の中、6月3日、 国会で野党陣営に法相が放った激しい答弁は、移民2世として男性が支配する郊外で育ち、1990年にアルジェリア人と結婚後、婚姻を取り消した体験をもつ同相の本音ととられる。「婚姻取消によってこの女性は守られたのです。(この種の裁判が起きるのは)元社会党政権による郊外対策の結果であり、私がその罠にはまらなかったことが不満なのでしょう!」と法相は、80年代に元左派政権が郊外地区の兄貴分の青年らに監視を任せたためにイスラム式男尊女卑化を強めたと矛先をずらし反撃に出る。
が、同日法相は自らの言明を返すように同判決に対し控訴する決断を発表した。共和国でまかりとおるイスラム宗教令Fatwa、イスラム共同体の圧力に屈した女性蔑視の判決とまで批判されている同判決は、「新婦の虚言が原因」では国民感情は収まらず、法相はサルコジ大統領の命令に従いざるをえず控訴に踏み切ったよう。
新郎がイスラムの伝統・習慣に従い新婦の本質的資質とみなす処女性が、はたして民法180条が認める婚姻無効原因(年齢・健康状態・地位などの錯誤)ととれるかが争点に。婚姻取消で、処女膜にこだわる男と結ばれずにすんだとほっとしたのも束の間、控訴は新婦にとって傷口に塩に等しく、数年茨の道を歩むことに。
婚姻数約27万のうち約80件が取り消され、例えば新郎が被保佐人、性的不能、エイズ患者であることを新婦が知らなかった、新婦が売春をしたことを新郎が知らなかったなどが原因で同意による婚姻取消が成立している。新婦が処女であると偽った故の婚姻取消は初めてで、男女平等を実際に生きている女性たちは、「婚前に新郎が童貞かどうか問うのか」とイスラム共同体に詰問する。女性団体活動家たちは、男女平等を貫徹させるため、新婦の処女性を本質的資質とみなすことを禁止すべきと主張する。
多民族社会の中で、新婦の処女性を重視するイスラムの伝統・社会的風習が守られている家庭と西洋社会に挟まれて、モスレム女性の処女膜形成手術の需要が急増しそうだ。(君)