| ●Philippe Forest « SARINAGARA » 本書はフィリップ・フォレストの三作目の小説だ。1997年にフェミナの処女作賞をとった『L’Enfant eternel』とそれに続く『Toute la nuit』(1999)は、4歳の娘の死から生まれた小説であった。また著者はナント大学の文学部教授でもあり、フィリップ・ソレルスが創刊した文芸誌『Tel Quel』の歴史についての本や、短い文学理論に関するエッセーも出している。 切れがよく、叡智に満ちた文体は「俳句」的といっても過言ではないだろう。一茶、漱石、そして原爆直後の長崎の写真を撮った山端庸介についての章は、端的にまとめられた伝記的描写であるが、これらの三つの人生の物語からは言葉では表すことのできない何かが見え隠れする。確かに、幼い子供の死というモチーフがあるが、それだけにはとどまらない。そして、京都、東京、神戸と異なる都市で日本に接する…作家(?)、語り手がいる。そこにもやはり亡くした子供の影は常にある。しかし…。 本書はおそらく、異国情緒をもとめるフランス人や、別の意味での異国趣味でフランス語のできる日本人にも読まれることだろうが、しかし…。 しかし、表面的な異国情緒を越えて、本書から感じられるのは「生」に対するある種の感受性だ。この感受性、この言葉にすることのできないものにあえて言葉をあてるなら、憂愁(melancolie)だろう。これはボードレール的な憂鬱ではなく、小林一茶的な憂鬱だ。つまり、本書がそこからタイトルをとった俳句から感じられるような憂愁。つまり、 霧の世は 霧の世ながら さりながら この一茶の一句が見事に響く作品だ。(樫) |
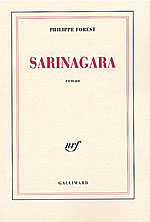 
Gallimard, 2004, 288 p. 16,50 €
|
|
|
|







