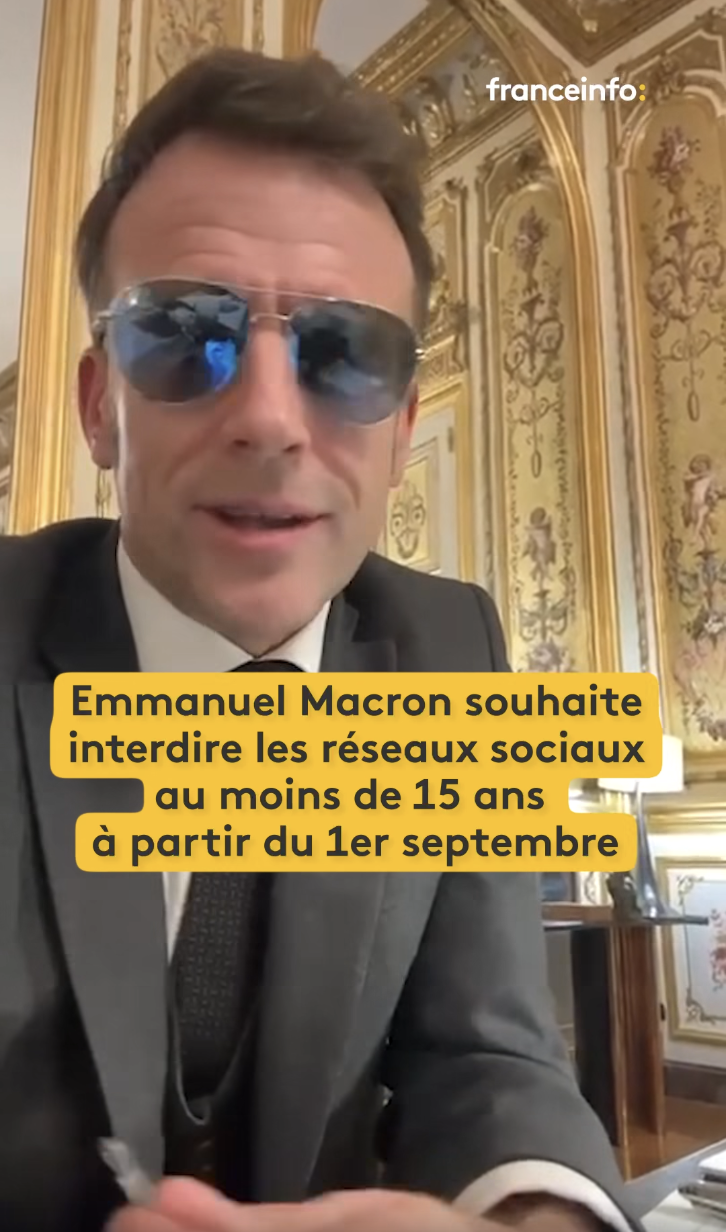「Non, c’est bon, chef(もう撃たないでくれ)」。シャルリー・エブド編集部襲撃の直後、クアシ兄弟の銃弾を受けた警官のアフメド・メラベさんが、腹部を押さえてもだえながら、脳天を打ち抜かれる寸前に口にした、命ごいの言葉が耳を離れない。この「chef」という語、植民地時代には現地人がフランス人を呼びかけるときに使われ、今も大都市近郊の若者が「ムッシュ」に代わって用いている。
事件の翌日、メラベさんが倒れた場所を通った。ロウソクや花束の狭間には、彼を悼む言葉でも、写真でもなく、「Je suis Charlie」のプリントが散らばっていた。怒りにも似た悲しみと、得体の知れない薄ら寒さを感じた。11日のデモの群衆にも、疎外感を感じた。家族連れが笑顔で「自由万歳」と叫ぶ光景は、お祭り騒ぎにしか見えなかった。一体、この感情は何か。
答えは翌週のシャルリー・エブド誌の風刺画にあった。遠い過激派の本拠地に着いた若者二人に、戦士が言う。「お前ら « 93 » 出身か? なら便所掃除をやれ」。つまり、セーヌ・サンドニ県のようなパリ辺隣に住んでいる「Bicots(アラブ野郎)」は、どこに行こうが、他人の嫌がる仕事をさせられる、という意味だ。
このような境遇にあったのは犯人だけではない。殺されたメラベさんもそうだ。93県出身の彼は8年前、34歳で警察官の試験にパスした。一家の大黒柱でよき兄、伯父、そして警官だった。だがリベラシオン紙に載った近親者の話では、本人はどこかで恥じていたのか、あるSNSで「職業は社長」と偽っていたらしい。
3人はスラムの貧困という運命に抗おうとした。そして、一人は警官、二人はテロリストとなり、あの日の歩道で対峙(たいじ)した。テレビやネットで我々が見たのは、育った環境を同じくする者が、社会の下部構造の中に押し込められた果てに、上部構造のご都合で、互いに殺し合わさせられるという、この国の悲劇である。また、猫も杓子も無批判に「挙国一致」、「表現の自由」、「私はシャルリー」と叫ぶ、ファシズムまがいの集団ヒステリーの陰で忘れられているのは、様々な偏見を受けながらも、多くの移民やその2世たちが清掃員や工場労働者、土木作業員として国の底辺を支えているという事実だ。幸せで尊厳ある社会を望む者は、まず「シャルリー」という曖昧な仮面を捨て、現実を見つめ、考えることから始めなければならない。(浩)