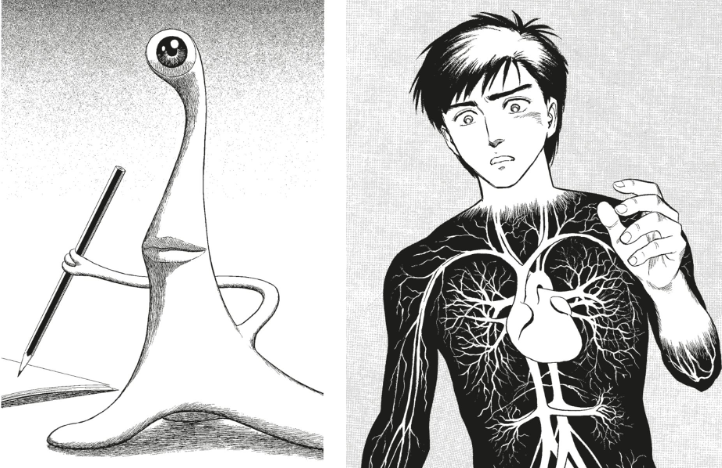前号の「豊胸用に工業用シリコン !?」という記事に「乳房を女性美の一つとみなす現代社会への痛烈な詐欺行為であり」という箇所があったけれど、乳房が女性美というか女性のシンボルとして重要だったのは、「現代社会」に限らず古代からのことだし、豊かな乳房が好まれたのか小さめが好まれたのかも、時代やそれぞれの国、文化によって異なりそうだし、多くの女性たちが、豊胸を求めてリスクがあるにもかかわらず手術をするのは、男のパートナーの影響なのか、それとも女性自身の願望なのか、などといろいろ考えさせられた。そんな時、リベラシオン紙に3頁にわたる記事が掲載された。
『100 000 ans de beauté 10万年の美』の著者で民族学者のエリザベット・アズレの話が興味深い。「(…)1920年代からは、シャネルのデザインに代表されるように、小さな乳房を持ったスポーティーで男性的な女性像が、女性の地位向上を示すシンボルとなったけれど、第二次世界大戦に入ると米国にピンナップが登場する。(…)砲弾のような乳房、細いウエスト、盛り上がった尻、今にも爆破しそうな腰。乳房の授乳としての役割は後退し性的な面が強調されてくる。(…)70年代になると、女性たちはどんどん肌を見せ、細い体を持つようになる(ツイッギー、ジェーン・バーキンのごとく)。細い腰、すらりとした体、でもきれいな乳房が望まれた。女性は乳房を持っている男性といってもいいくらいになり、乳房が女性であることの核になる。(…)今度のスキャンダルがあっても、豊胸手術は増加の一途だが、それは、仕事に就き、子供はたくさんつくらず、授乳するかどうかにかかわらず性生活を大切にする女性たちにとって、女であることの価値を高めようとすることだから」
男性が望むから手術をするのかという点に関し、パリのある整形外科医は「男性パートナーが付き添って手術の相談に来るのはわずか20%。女性の友人や時には母親が付き添ってくる方が多い」と語る。男性パートナーが付き添ってくる時は、ほとんどがボリュームありすぎの乳房を求めるので、説得に苦労するという。そして手術を受けた女性のほとんどが、その動機は「何よりも私自身の問題だ」と言う。リベラシオン紙のインタビューを受けたオードレさんは「麻酔からさめたら90Bになっていました。私が頭の中で思い浮かべていた乳房よりは小さかったけれど、とてもきれいでした。生まれ変わったような気持ちでした。他人の視線も変わったように感じられ、自分を見つめることがようやく喜びになったのです」(真)