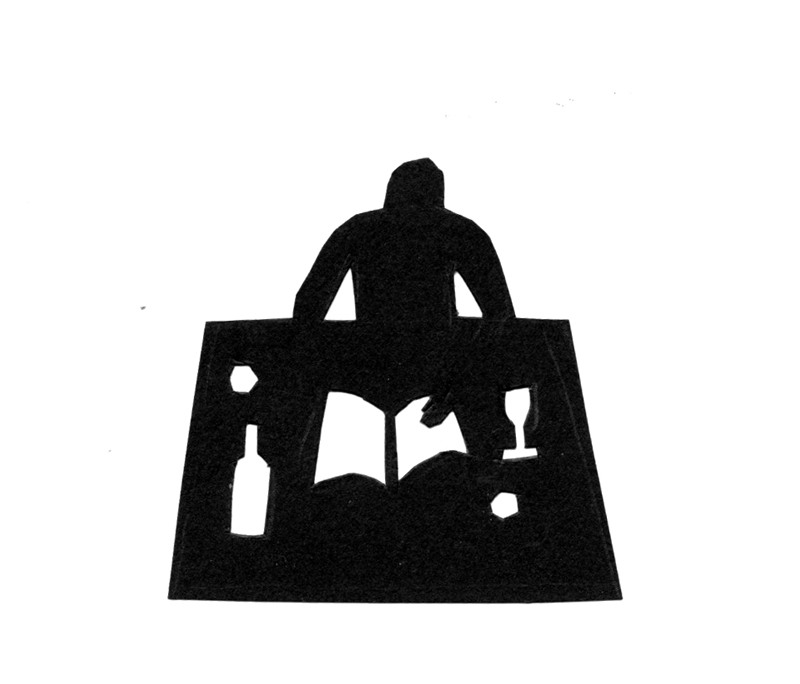根っからの頑固さや被害妄想のせいで多くの友人たちと仲違いしたルソーが、亡くなる2年ほど前に書き始めたのが『孤独な散歩者の夢想』(1782年)。「こうしてわたしは地上でたったひとりになってしまった」(今野一雄訳)と書き出したルソーのかたわらには、しかし、妻のテレーズがいた。ある時期親しくしていたかけだしの作家に、ルソーはこんなことを語っている。「昔は、わたしたち、わたしと妻は、夕食に一本の四分の一のぶどう酒を飲んでいた。それから二分の一になり、いまでは一本あけてしまう。そのおかげで若返った気持になる」。
パリ郊外のエルムノンヴィルでその最期をみとったのもテレーズだった。「愛する妻よ、窓をあけておくれ。もういちど緑をこの目で見たいから」と言ったルソーは、太陽の下に光り輝く美しい緑に見守られ、ごく静かに旅立ったという。
世間から見放されたルソーの評価はその死後じわじわと高まり、1794年には遺骸がパンテオン(偉人廟)に移される。19世紀初めには、フランス革命に影響を与えた思想家としてだけではなく、ロマン主義のパイオニアとしても崇められた。批評家のサント=ブーヴなどは、小説家のジョルジュ・サンドへ宛てた手紙の中で、ルソーを「現代社会の父」だと評価。祖父母の友人でもあったルソーの著作に若い頃から親しんだサンドの作品には、その精神が色濃く反映されている。未完に終わったものの、ルソーの子孫を主人公に設定した小説執筆に取り組んだこともあった。
日本では、中江兆民や島崎藤村がルソーに感銘を受けてその考えを広めた。ところで、童謡の「むすんでひらいて」のメロディーは、若かりし日のルソーが作曲したオペラの一節だということはご存じだろうか。奇才ルソーが残した文化遺産は、現代を生きる私たちの暮らしのあちらこちらに、素知らぬ顔でひっそりと溶けこんでいる。(さ)