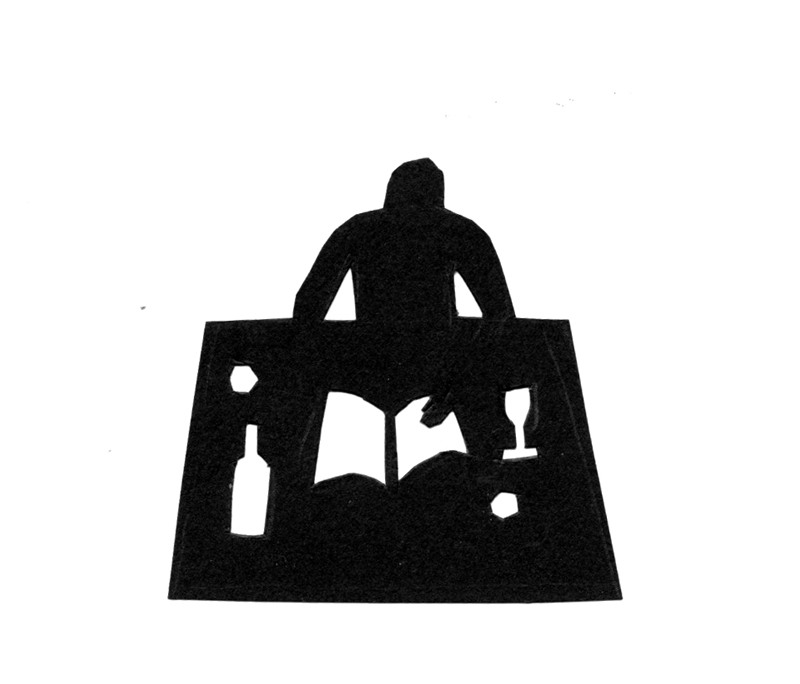哲学者ルソーの代表作とされる『エミール』(1762年)は、他に類をみない不思議な書物だ。それはエミールという男児が成人するまでの過程をなぞる物語ではあるけれど、小説というカテゴリーを明らかにはみ出ている。作者独自の哲学や宗教観、また、社会や教育についての意見がたっぷりと盛り込まれていて、まるで専門書が何冊も詰め込まれたよう。読者の感性しだいで、いかようにも楽しめる。
哲学者ルソーの代表作とされる『エミール』(1762年)は、他に類をみない不思議な書物だ。それはエミールという男児が成人するまでの過程をなぞる物語ではあるけれど、小説というカテゴリーを明らかにはみ出ている。作者独自の哲学や宗教観、また、社会や教育についての意見がたっぷりと盛り込まれていて、まるで専門書が何冊も詰め込まれたよう。読者の感性しだいで、いかようにも楽しめる。
その中でも、最終巻の第五巻は必読だろう。たびたび顔を出す女性蔑視の記述には辟易するけれど、そこで展開されるのは、人々がいかにして幸せになれるかという幸福論。フランス革命前夜、差別が当然のようにのさばるなか、独学で得た知識を武器に突き進んだルソー。恵まれない家庭環境にも負けずに一度は社会的成功を手に入れながら、真実を追うことをやめなかったからこそ生まれた傑作が『エミール』なのだと思う。
この本が完成したのは、パリに嫌気がさしたルソーがモンモラシーで暮らすようになってから。最終巻を執筆した場所は、庇護者であるリュクサンブール元帥が所有している庭園の一画にある離れだった。「わたしの選んだのは台所の上にあるいちばん小さな、いちばん簡素な部屋だ。台所も使える。その部屋は清潔で気持がいい。調度は白と青だ。この深い、こころよい孤独のうちに、森と水とにかこまれ、あらゆる種類の鳥の合唱を聞き、オレンジの花の香をかぎつつ、わたしは『エミール』の第五巻を書いたのである。わたしは始終陶酔境をさまよっていた。その巻のあざやかな色彩は、主としてこれを書いた場所のいきいきした印象によるものである」(桑原武夫訳)。その台所で具体的に何を作ったかは語られていないけれど、「台所も使える」という短い一文からは、放浪生活が長かったルソーの暮らしぶりがしみじみと伝わってくる。(さ)