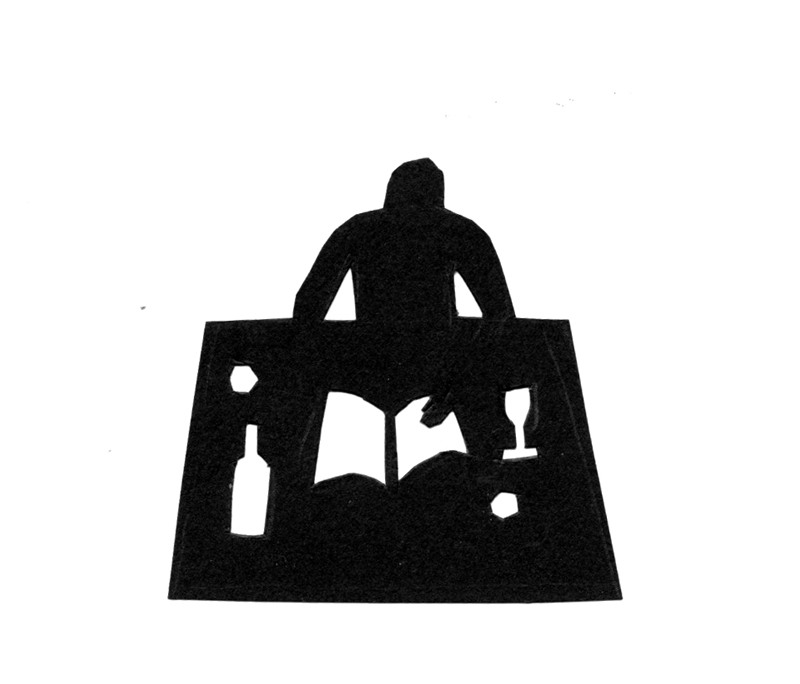楽園のようだったサヴォワの田舎での暮らしは、ルソー最愛のヴァラン夫人が新しい恋人を見つけたこともあって終わりを告げる。その後のルソーは、パリでディドロをはじめとする文学者と交流するようになったり、論文が認められたりと、30代後半には社交界でも知られる存在になっていった。ところが、その心は、いつもむなしく自然を追いかけていたよう。「パリで、大社交界の渦のなかにいるときも、晩餐のうまみに酔い、観劇のはなやかさにつつまれ、虚栄心にのぼせていたときも、いつも、わたしの森のしげみ、わたしの小川のせせらぎ、わたしの孤独な散歩が、思い出によみがえり、わたしをぼんやりさせ、深い悲しみにおとしいれ、ためいきと願望をおこさせずにはおかぬのだった」。(桑原武夫訳)
1756年春、ルソーは埃っぽくて騒がしいパリを離れて、モンモランシーに暮らしはじめた。パリから15キロほどのところにあるその地に身を落ち着けたルソーは、まずは散歩に出かけて近隣の自然に親しんだ。そして、静寂の中で構想中の大作に取り組む暮らしが始まった。
モンモランシーには、そんなルソーに興味を持って何度も自宅の城に招こうとする夫婦がいた。リュクサンブール元帥とその妻だ。なかなか首を縦にふらないルソーに業を煮やした元帥は、ルソーが暮らすモン・ルイ館に自らやって来る。そして、ひどい状態だった家の修繕を命じた上、工事中の住まいまであてがった。それ以後、ルソーは城を訪ねては、執筆中の自作を夫婦に読んで聞かせるように。昼食をごちそうになったあとには、森を一緒に散歩したという。理解者が自宅でふるまってくれる食事、そしてうまい空気を吸いながらの食後の散歩は、孤独に浸りがちな哲学者にとって何よりの栄養になった。(さ)