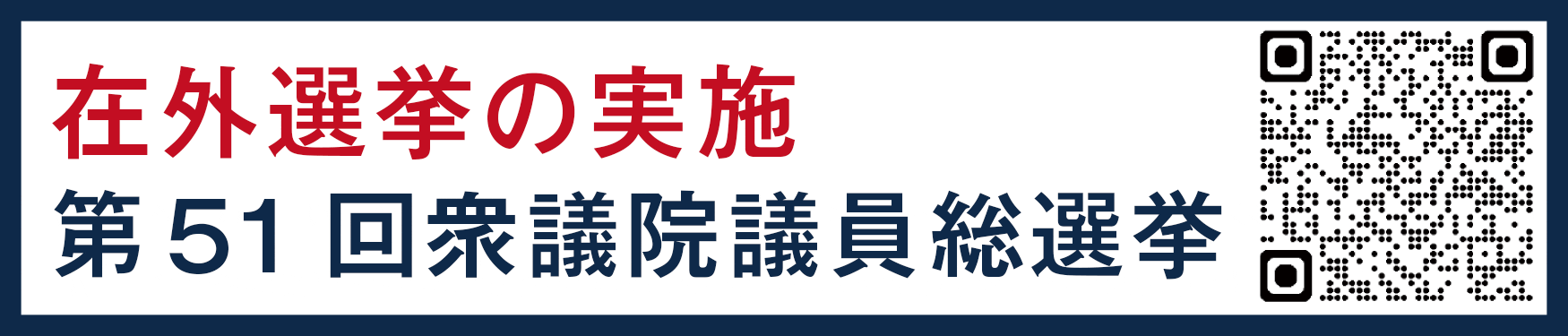1990年代から2000年代に日本でフランス語を学んだ者なら知らぬ人はいない、そんな顔、声である。長年NHKの語学番組で講師をつとめたミカエル・フェリエさん。来年3月までパリに滞在されていると聞き、話を伺った。
「日本の生活も長いですね」と言うと、かつてのブラウン管の恩師は「今年はハタチ、やっと大人になれた」と笑った。
父親が軍人で、アフリカ諸国で育った彼が日本に出会ったのは、高等師範学校(ENS)を卒業し文学のアグレガシオンを取得後、兵役のかわりに、「ガボンの小学校教師、バーレンのフランス学院長、京都の関西日仏学館の講師」という16カ月の奉仕義務を選択したときだ。受験勉強で学んだ程度で、とくに日本に興味を持ったことはなかったが、彼は京都に行くことを決意する。しかし、そのとりことなるのに時間はかからなかった。奉仕義務期間が終わる頃には、日本に残る術(すべ)を探していた。そんなある日、一本の電話が運命を決める、東京外大とNHKの講師にならないかとの誘いを受けたのである。
ミカエルさんは今や中央大学の教授、そして10冊もの著書を持つ作家だ。3月に上梓(じょうし)された『Fukushima』はフランス人の目を通して見た震災と原発事故の、精緻な描写と生死に関する深い洞察に富み、読者の関心を集めた。日本語版は来年9月に出版予定だ。
関東のフランス人の6割が避難し、テレビ記者たちですら大阪からレポートを行っていた最中、あえて被災地に旅立った理由を聞くと、「震災後に帰国した外国人をフライ人(fly + 外人)と揶揄(やゆ)する人たちがいるが、生死の危機に直面したら、避難しようとするのは当然。僕は友だちや恋人を見捨てたくなかった以上に、物書きとして、あの場所に残って書かなかったら救われないと直感した。この本が僕を呼んだ。やるべきことをやっただけさ」。現在は戦中のマダガスカルが舞台の小説を執筆中。主人公は17歳で家を飛び出し、曲芸師としてインド洋を渡り歩いた自身のお祖父さん。
スペイン内乱に従軍したマルローやボリビアでゲバラと共に闘ったドゥブレではないが、彼にはフランスの「行動する知識人」の系譜と、もうひとつ、お祖父さんゆずりの常に旅を続ける不思議な遺伝子が宿っているのかもしれない。(康)

Michaël Ferrier