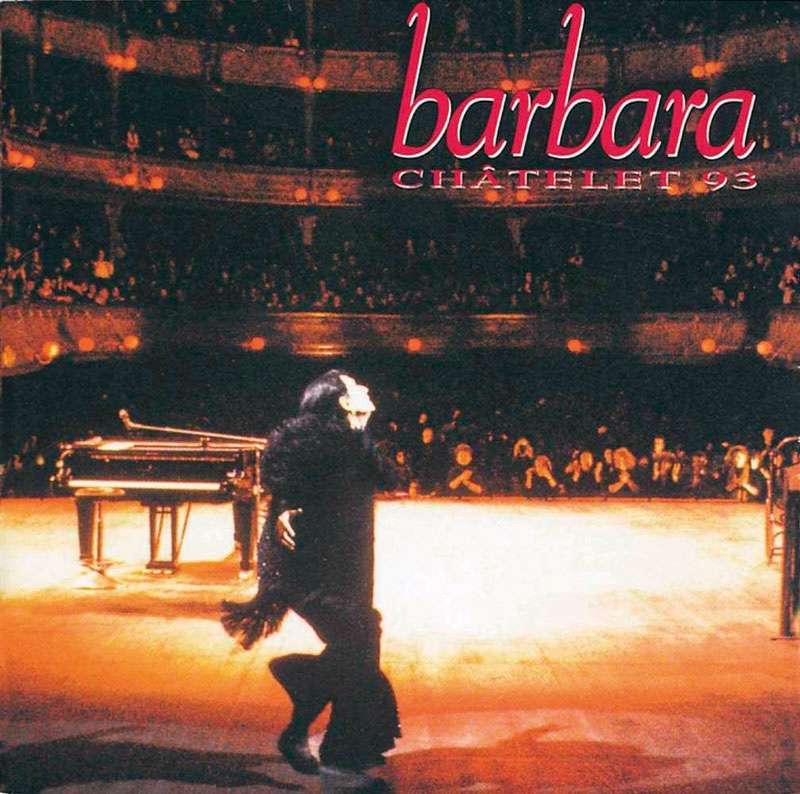「面白いものをつくるために、必ずしも多くのものは 必要ではないのですよ」

アート・ディレクターや装飾家としての仕事を経てきたフレデリックさんが、マレに花屋を開いたのは2005年のこと。季節の花、野原の草花、そして蚤の市などから集められた懐かしいオブジェで飾られたウインドーや店内はいつも詩情に満ちていて、それを見るだけのために遠回りをしても損はないと思わせる。例えば、取材に訪れた日に店内を飾っていたのは、イチジクの枝、ニンジンの花、イネ科の植物など、森からやってきた緑を基調にしたデコレーション。花瓶には、蚤の市で見つけてきた古本のページがくるりとまかれ、そこには鍵がかかっている。こんな演出にすっかり魅入られてお店に入って来た北欧からのお客さんに、「鍵を誰かに渡すということは、その人を信頼しているという、特別な意味があるんですよ」と、フレデリックさんはやさしく声をかけていた。
19世紀のアメリカの思想家、ヘンリー・デイビッド・ソローを好んで読み、中でも「あなたが何かをしっかりやっているその間、他にどんな良いことができるというのでしょう?」「私は途方もないことではなく、普遍的なことについて描写する。そこにこそ最大の魅力があり、詩の本当のテーマがひそんでいる」というフレーズを大切にしているという、地に足のついた花の演出家だ。
地元の住民たちや観光客、皆に愛されるこのお店が営業形態を変えたのは去年の秋のこと。「平日は催し物などの装飾クリエーションのために時間を割き、週末は花屋としてオープンするというのが僕の個人的な選択でもあるんです。多くの種類の花を仕入れて店を盛大に飾れば、それは確かに見栄えはするけれど、それだけの花を新鮮に保つことは難しくなってしまう。そこで、平日は、お店を開ける代わりにお客さんからの電話やメールで注文を受けて、その時にある新鮮な花を使って、予算に合わせたものをつくるようにしたんです。そうすることで、より新鮮で良い質の花を届けられるようになりました。それに、フラワー・レッスンの時もよく言うことですが、何か面白いものをつくるために、必ずしも多くのものは必要ではないのですよ」とフレデリックさん。「今年に入ってからは、フォンテーヌブローの森近くのバルビゾンの生産者に頼んで、ポピーやスカビオサ、キンレンカといった「田舎の花」を直に取り寄せることになった、と言って目を輝かしている。その、シンプルながら洗練された花の世界は、今後ますます生き生きと変化を遂げていきそうで目が離せない。