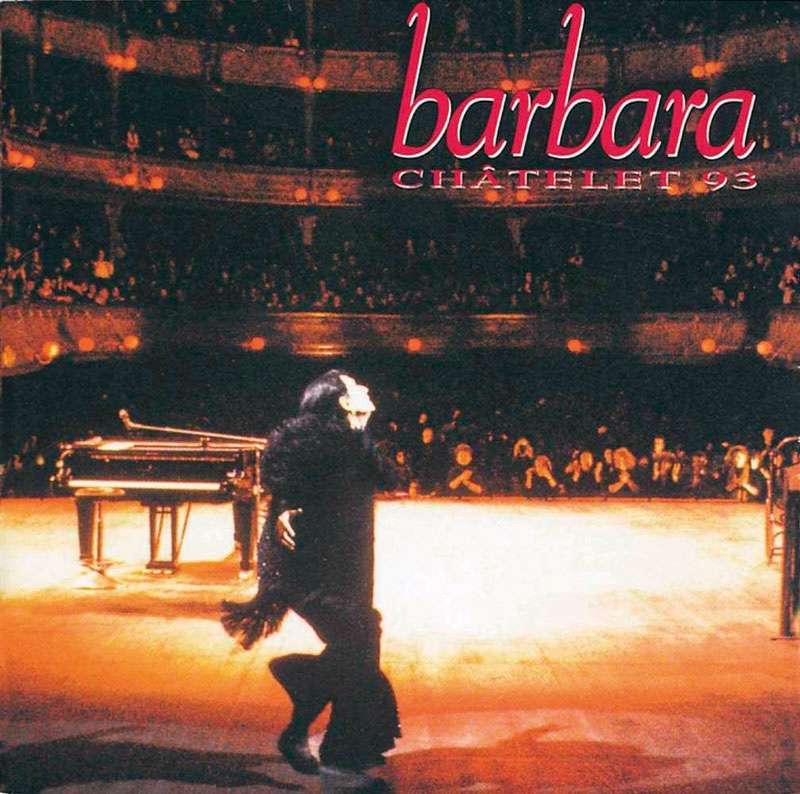「お客様をリフレッシュ、リラックスさせる、 それが理髪師の仕事です」

ユーゴスラビアに生まれたミシェルさんは、まだ連邦人民共和国だったチトー大統領時代に青春期までベオグラードで過ごす。「チトー大統領の政治方針は、自己管理社会主義autogestionに基づくもので、国民一人一人が職に就くということが自ずと重視されていました。学校を卒業した時に、テレビや映画などのメイクアップのアシスタントに、という話があり、とても憧れました。これを仕事にしようと心に決めていたのですが、この話は流れてしまい、時に流されるままに工場で働いたり、さまざまな職に就いたりした末、理髪師になったのです」
1964年、ミシェルさんはフランスへやってくる。「ユーゴスラビアはソ連との距離を置き、東欧諸国の中でも国境が開かれた国でした。そしてフランスには、幼少の時から、何か親しみを感じていたのです。第一次世界大戦終結の時に、セルビア人の祖父は、あるフランス人を助け、その後、彼とは友人となり、フランスに祖父を呼んでくれたそうです。小さな頃から祖父の話を聞き、フランスに憧れのようなものを抱いていたのでしょうね」
パリに着いてから職場を点々とするが、本来やりたかった仕事の延長ともいえる、床屋で働く機会が訪れ、そこから理髪師への道を進み始める。今までに何軒かサロンを持つ。そしてこの東駅の店は10年目。「以前はもう少し規模の大きい店を持ってて、女性、男性両方をカットしていましたよ。ただ、私自身は女性のカットをすることを敬遠しています。3年間美容院にも勤めましたが辞めた経験もあります。女性は理髪師の仕事に対し、決して満足しないからですね。ある日、女性をカットした際、耳の周りをすっきりさせたいという要望に応えるべく、切り整えました。すると、仕上がった後に『こうではない』と言われ、もめてしまいました。僕はお客様にリフレッシュ、リラックスしてもらうことが理髪師としての仕事だと思ってるのに…」。以来、男性のみを相手にしている。
チトー没後の80年代から祖国で紛争が始まり、今では6カ国に解体してしまったが、「もう既に私はユーゴスラビアにおいて外国人だったのです。遠くから行方を見るしかなかったのです」というのがパリに留まる彼の心境だ。その後祖国には帰っていない。ユーゴスラビアという名前も消えてしまった今、彼は現状況に対してあまり口を開かない。
現在パリでは、ミシェルさんのような小規模の理髪店が次第に減り、かわりに廉価店とチェーン店舗が増えている。「それは時代の流れだから仕方がないこと。ただ、そのような店で働いている人たちの状況はどうなのでしょうね」と、これから理髪師として経験を積む人々のことも危惧している。「若いからということで、彼らは決して満足できる給料をもらってはいないのではないでしょうか。また、彼らは往々に、仕事して一つのことしか与えられていないように見てとれます」。理髪師になるためのディプロム数が増えていること、またサロンも経営している理容学校がこうしたディプロム制度を支えていることに対しても異議を唱える。「私立の学校を出て、ディプロムをたくさん取得しても、それに比例して仕事の選択肢が増えるわけではないですね。ディプロムの数には関係なく、良い仕事ができることが大切なのではないでしょうか。これは理髪師だけでなく、社会全体の問題かな」
*ミシェルさんの店 : 131 rue du Fbg Saint-Denis 10e

バリカン。 角刈りの時に使用する。

角刈り用のくし。 水平をキープするための 水準器がついている。