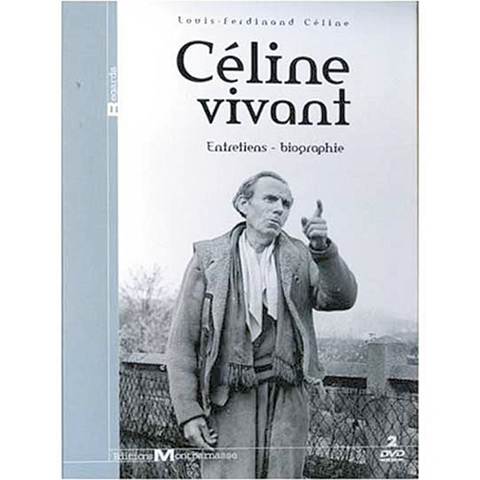
『夜の果てへの旅』や『なしくずしの死』を書き、プルーストに次いで世界で一番訳されているというルイ=フェルディナン・セリーヌ。今年は、そのセリーヌが亡くなってちょうど50年。文化省が選んだ「2011年フランスが祝う人 célébrations nationales」のリストの中に挙げられていたが、〈フランスから強制移送されたユダヤ人の息子と娘の会〉のセルジュ・クラルスフェルド会長が「セリーヌは、文才があっただろうが、ユダヤ人の虐殺を呼びかけたということを忘れることはできない。そんな彼を国が祝うということは恥ずべきこと」と抗議。
実際、セリーヌは『虫けらどもをひねりつぶせ』(1937)などで、過激で偏執狂的な反ユダヤ主義をあからさまにしている。このクラスフェルド会長の抗議にあわてたミッテラン文化相は「熟考の末、セリーヌを、国が祝う人のリストから外した」と急きょ声明する。
20世紀文学の専門家アンリ・ゴダールは「セリーヌは読むに耐えられないような反ユダヤ主義の文章の書き手である」とし、「『祝う』というコトバが誤解のもとになった」としながらも「セリーヌは、フランスの散文を革新したことによって、そのコミカルな記述の才能によって、そして二つの世界大戦についての描写によって、この2011年のリスト
に挙がって当然である」とする。さらにアンドレ・マルローの考えを引用しながら、「芸術的な創作は、それが真正である場合、それだけで一つの秩序をなし、他の価値観とか道徳観とかの秩序とは混同しないものだ」と反論する。そして20世紀最大の作家としての業績を、彼の極端な反ユダヤ主義を持ち出して除外するのではなく、セリーヌのこの二つの顔がどうやって生まれてきたのかを、彼の没後50周年をきっかけに再検討しようと呼びかけている。徹底的なスターリン崇拝者であったからといって、恋人エルザに捧げる詩を書き続けたアラゴンを枠外に置くことはできない、ということにもつながっていくだろう。
セリーヌ自身『夜の果てへの旅』で痛烈に書いている。「完全な敗北とは、要するに、忘れ去ること、とりわけ自分をくたばらせたものを忘れ去ること、人間どもがどこまで意地悪か最後まで気づかずにあの世へ去っちまうことだ。(…)何もかも逐一報告することだ、人間どもの中に見つけ出した悪辣きわまる一面を、でなくちゃ死んでも死にきれるものじゃない。(生田耕作訳)」(真)
偏執狂で人間嫌いといわれるセリーヌの、歯に衣着せぬ毒舌は、じつに興味深い。
「同性愛者でなくてもプルーストの作品を愛読できるように、反ユダヤ主義者でなくても、セリーヌの作品を好むことができる」2008年にインドを訪問した時のサルコジ大統領の迷言。よほどセリーヌ好きらしいが、「同性愛者」と「反ユダヤ主義者」を同じレベルで扱っていいものなのか、と憤る人も多かった。







