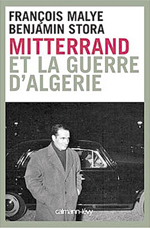 1994年、ジャーナリストのピエール・ペランが『Une jeunesse française』を出版。フランソワ・ミッテラン元大統領(1916-1996)が、南仏ヴィシーにあった親独(ナチス)政権のペタン元帥に政治的に近づいて、高級官僚の職に就いていたことを暴露し、ミッテランの名声に汚点をつけた。そして最近発刊された『François Mitterand et la guerre d’Algérie』の中では、歴史家のバンジャマン・ストラとフランソワ・マリが、アルジェリア戦争中のミッテランの、彼の支持者があ然とするような反人道的な政治的態度を追っている。
1994年、ジャーナリストのピエール・ペランが『Une jeunesse française』を出版。フランソワ・ミッテラン元大統領(1916-1996)が、南仏ヴィシーにあった親独(ナチス)政権のペタン元帥に政治的に近づいて、高級官僚の職に就いていたことを暴露し、ミッテランの名声に汚点をつけた。そして最近発刊された『François Mitterand et la guerre d’Algérie』の中では、歴史家のバンジャマン・ストラとフランソワ・マリが、アルジェリア戦争中のミッテランの、彼の支持者があ然とするような反人道的な政治的態度を追っている。
1954年を境にアルジェリアの独立派は武装蜂起し、フランスは大規模の軍隊を投入する。1956年2月、ミッテランはギ・モレ内閣の司法相に就任し、アルジェリアに駐屯するフランス軍に、警察、裁判の領域にまで広がる特別権を認める法令を施行する。以来モレ内閣が解散するまでの16カ月間、ミッテランは、フランス軍の独走をバックアップしていく。マシュー大佐に率いられたフランス軍は、アルジェを中心に掃討作戦を繰り広げ、ポンテコルボ監督の『アルジェの闘い』やゴダール監督の『小さな兵隊』に見られるように、抜き打ち的に家宅捜査し、FLN(アルジェリア民族解放戦線)の一員やテロの容疑者とおぼしきアルジェリア人を大量に逮捕し、水責めや電気ショックによる拷問で自供を引き出し、物的証拠なしに次から次へと死刑の判決を下していった。政治家のフランス・マンデスやミシェル・ロカール、作家のアルベール・カミュ、文化人類学者のジェルメーヌ・ティヨンらが、ゲシュタポを思わせる、こうしたフランス軍の行き過ぎに反対し世論に訴えようとしたが、ミッテラン司法相の耳には届かなかったようだ。
著者のストラとマリは、これまで知られていなかった資料を手に入れ、バダンテール、デュマといったミッテランの周囲にいた人たち、FLNの当時の指導者たち、独立派の被告たちの弁護にあたって死刑執行に対する恩赦を求めたジゼール・アリミ弁護士らとのインタビューを重ねながら、ミッテランの真意を探っていく。これまでは、ミッテランは死刑執行に対し、迷いに迷い動転していた、というイメージが一般的だった。ところがこの一冊で、アルジェリア共産党に属していたフランス人、フェルナン・イヴトンも含め、45人の恩赦願いに「拒否」の決断を下して、全員ギロチンで処刑された、という事実が明らかにされた。こうしたミッテランの盲目的ともいえる権力への執着の裏には、モレに次いで内閣を率いたいという政治的野望があったと、著者は結論を下している。
皮肉にも、大統領に選ばれた1981年に、ミッテランは死刑を廃止している。(真)







