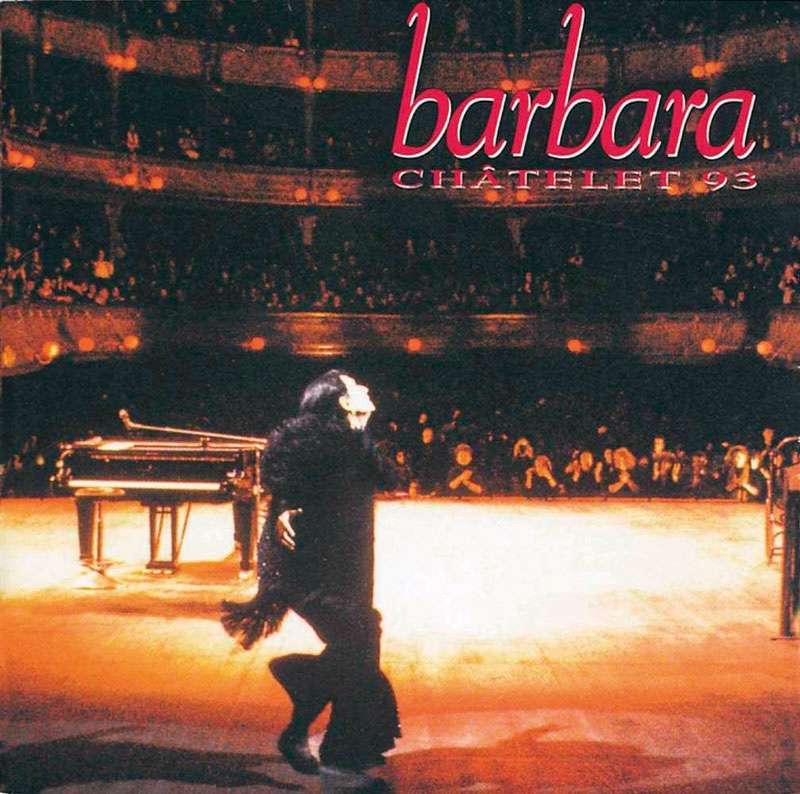「〈脚本は大事でない〉 というイデオロギーが 映画人に蔓延(まんえん)」
Michel Ciment
 国立映画センターによる〈映画資金の前貸し avance sur recettes〉制度は、60年代にドゴール政権下の文化相アンドレ・マルローによって作られたもの。これは左派にも受け継がれ50年間続いています。私はこの制度を全体的には大変ポジティブに捉えています。若手監督作品への助成に多く使われますので、常に映画界の新陳代謝が活発です。
国立映画センターによる〈映画資金の前貸し avance sur recettes〉制度は、60年代にドゴール政権下の文化相アンドレ・マルローによって作られたもの。これは左派にも受け継がれ50年間続いています。私はこの制度を全体的には大変ポジティブに捉えています。若手監督作品への助成に多く使われますので、常に映画界の新陳代謝が活発です。
たしかにこの援助システムには批判もあります。審査方法が「脚本至上主義」に偏っているという声もあるでしょう。しかし「良いかどうかは結果を見ろ」という諺(ことわざ)があります。この制度のおかげで、ヨーロッパ中でフランスだけが半世紀にわたり常に興味深い作品を作り続けていられたという結果を見るべきなのです。前貸し金を受けるには脚本やその前に撮影した短編映画が審査対象になります。良い脚本が良い映画になるという保証もありません。しかし他にどんな判断基準を採用できるというのでしょう。審査委員会メンバーたちは監督に会い、彼らが撮った短編を見てシナリオの質を検証します。そしてある意味でリスクを冒すのです。1975年に私が審査委員会メンバーだった時は、ロベール・ブレッソンの脚本がありました。私は彼に「書き直して」などとは言いませんでした。なぜなら彼はすでに13本もの素晴らしい映画を発表していたので、次も素晴らしい映画になるチャンスが高かったからです。つまりブレッソンとまだ名を知られぬ新人監督との間には、審査基準に違いがあるということ。ブレッソンやレネ、ゴダールのように作家の個性が認知されていない人の場合、脚本が大きな役割を果たすのはある程度仕方がありません。
それに現在のフランス映画の問題のひとつに「脚本の弱さ」があることは否定できません。ヌーヴェル・ヴァーグ以降、カイエ・デュ・シネマが提唱してきた「脚本は大事ではない」というイデオロギーのようなものが映画人に蔓延しているのです。今の若い監督たちは監督業も脚本業も全部自分でこなせると思い込んでいます。たしかに監督の中にはロメールやソーテのように脚本家としても才能豊かな人もいます。しかしトリュフォーはいつも脚本家と仕事することを好みました。脚本の質を上げるために書くことのプロと組み、監督は「自分は本当の脚本家ではない」ということを謙虚さとともに受け入れるのです。レネは一行たりとも自分で書きませんが素晴らしい監督です。アメリカにも自分で脚本を書かない監督が大勢いますね。ヒッチコックは自分で書いたことはありません。キューブリックはいつも誰かと書きました。マンキーウィッツはほとんど一人で書きました。要はすべての可能性があるということです。
脚本はその時々の経済的状況など外部の影響を色濃く受けます。現在ならテレビ局が映画に多く出資している以上、テレビの審査委員やプロデューサーの希望に合わせて書かれます。『去年マリエンバートで』、『気狂いピエロ』、『5時から7時までのクレオ』、『鬼火』などの脚本は、今なら援助は受け入れられないでしょう。資金提供の半分を担うテレビ局の担当者が嫌がります。映画に出資した後に自局で放映しても、一般人は20時半にテレビでこのような作品は見たがりませんから」(聞き手/瑞)
ミシェル・シモン
フランスを代表する映画評論家。
1963年以来、カイエ・デュ・シネマのライバル誌と目されるポジティフで執筆。
ラジオ番組の映画紹介でもおなじみ。インタビューの名手としも定評あり。

シモン氏についてのドキュメンタリー
『Michel Ciment, le cinéma en partage』も話題に。