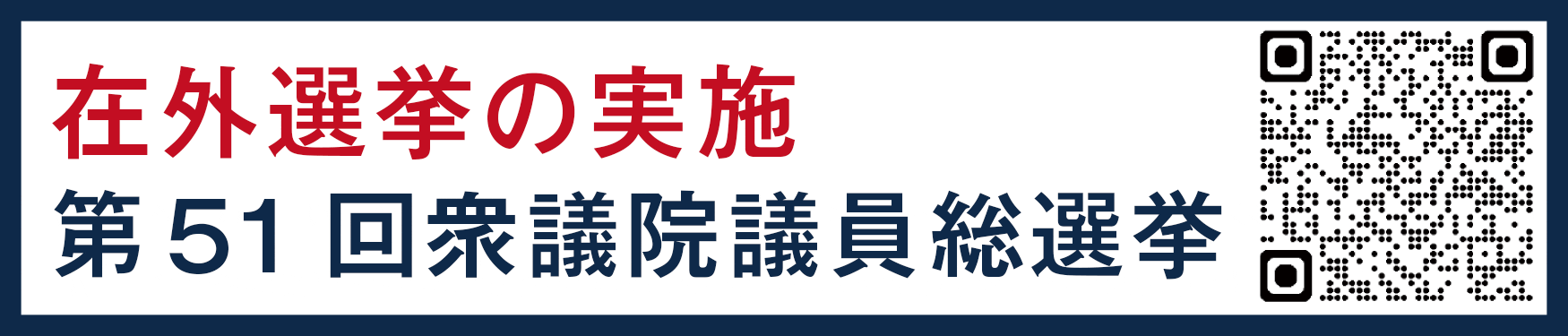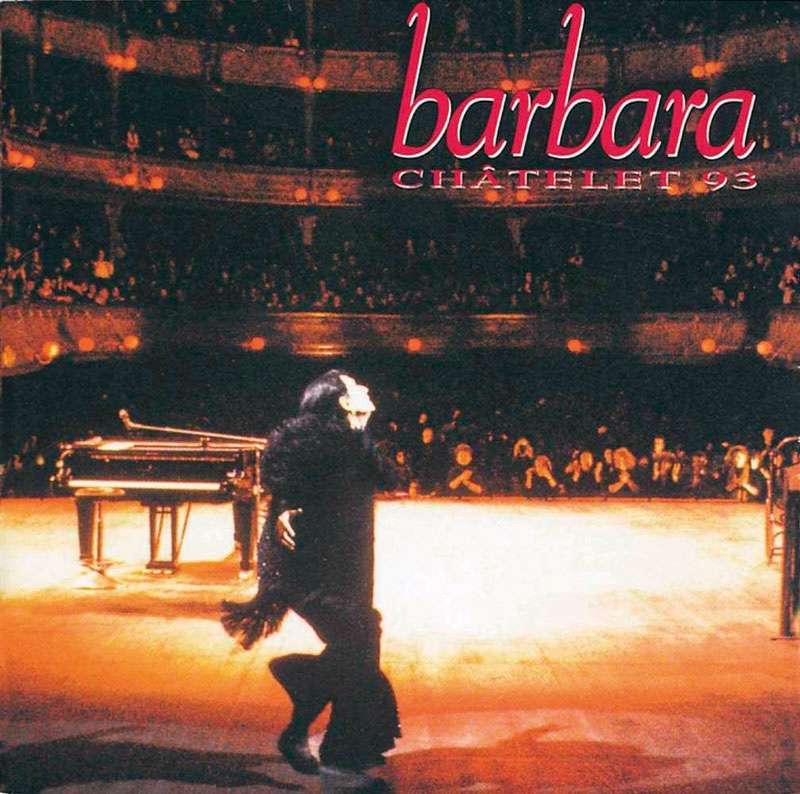とれた作物はBIOの朝市へ。
 畝(うね)の間を耕すジルさん。「トラクターのような重い機械は使えない。
畝(うね)の間を耕すジルさん。「トラクターのような重い機械は使えない。
土が圧縮されて、水が上がってこなくなる」
そこが、パリから東に60km、チーズで有名なクロミエCoulommiersの町のはずれにある、1.8ヘクタールの農地だ。もうひとつ、近くの町シャイイ・アン・ブリーChailly en Brieにも畑があり、合計3.2ヘクタールの畑を持っている。どちらの畑も、そばに川が流れている。川に通じる自由地下水が上がってくるので、水撒きは必要ない。しかし、そのため、トラクターのような重い機械は使えない。土が圧縮されて、水が上がってこなくなるからだ。あれっ?2軒先の普通の畑では、スプリンクラーで水を撒いているではないか。「あれは、農業のやりかたがヘタだから」とジルさんは言う。ジルさんのところの農機具はすべて小型だ。草刈機、耕運機、土の攪拌機、ジャガイモを掘り起こして選別する機械、畝(うね)の間を耕す機械を使っている。有機農業を選んだ理由は、「化学肥料や農薬を使いたくなかったから」
1年に180種の作物を栽培する。春の終わりから初夏にかけては、大きなフキのようなルバーブrhubarbe、アーティチョークartichaud、イチゴ、葉の大きいフタンソウblette、ソラマメ、白タマネギなどがとれる。有機農業では、普通の農業よりも種類を多く、量を少なく栽培する傾向が強い。一種類の作物が病気にかかったときに、共倒れにならないようにするためだ。
雑草もふんだんに生えていて、どれが雑草でどれが作物なのか、植物を知らない人には区別がつかない。ここも普通の農業と大きく違うところだ。もちろん除草するが、あまり気にしない。特に背の高い雑草の一角は「ここには野生の鴨が住んでいるんだ」。だから、わざと残しておく。イチゴ畑は、地面が黒いビニールで覆われている。あまりBIO的ではないなぁと思って聞いたら、「ビニールではないよ。トウモロコシのアミドンから作った袋で、イチゴの苗の寿命とともにそのまま土に帰るんだ」。イチゴは、ハリネズミやナメクジの大好物だ。
5月半ばから10月末までが季節のルバーブは、2カ所に植えてある。「病気にかかったとき、一部が離れたところにあると全滅が防げる。ルバーブが多いのは、うちのような湿気の多い土地で育てやすいから」植物同士の助け合いも大事にする。ジャガイモ畑の間に、インゲン豆があった。「豆が空気中の窒素を取って、土に定着させるんだ。だから、こうして豆と一緒に植えると、窒素肥料をやる必要がないんだよ」
化学肥料や農薬を使わずに栽培する知恵が、いたるところに見られる。葉を土の中に入れて腐らせて堆肥を作る。また、5年おきに、馬糞30トンを加える。「牛より馬の糞のほうが、軽くて空気が通るんだ」ジルさんの畑には果実類も豊富だ。ブドウの季節に実るモモpeche de vigne、スグリ、フランボワーズ、カシスなど。秋にはクルミも採れる。
ハウスでは、キュウリ、サトウダイコン、カブ、ナス、トマト、ピーマン、メロンを作っている。種はできるだけ自分の畑から採るようにしている。伸び放題のフタンソウは、種子を採るためにわざと残してある。
消費者の目から見ればBIO野菜は高価だが、BIOの市が唯一の販路のジルさんは言う。「季節によっては、自作農作物だけじゃなくて、よそのBIO作物も売らないとやっていけない。農業者保険に、兄と二人分で月に800ユーロも払わなきゃならないし。だから高いんだよ。BIOの発展のために、政府は、援助金を払うよりもこういう社会保障費を一部肩代わりしてほしいなぁ」
雑草もふんだんに生えている。

「ここには野生の鴨が住んでいるんだ」ジャガイモ畑の間に、インゲン豆。

「豆が空気中の窒素を取って、土に定着させるんだ」

みごとなルバーブを手にするジルさん。
ハウス内では、キュウリ、カブ、トマト、ピーマンなどが栽培されている。

まだ実が青いスグリgroseille。

やはりまだ実が青いカシスcassis。

おいしそうに赤く熟してきているイチゴ。

ブドウが熟す季節に実るというモモ
pêche de vigne。

パリには、BIO専門の朝市が3カ所ある。一番古いのが、地下鉄駅Sevres-BabyloneとRennesの間に立つラスパイユの市。後からできて少し規模が小さいのが、地下鉄RomeとPlace de Clichyの間に立つバティニョルの市。バティニョルには地元の人が多い。最後にできたのが、14区のPlace Brancusiに立つ市だ。バティニョルの市のジルさんのお客は、ほとんどが常連。「ラスパイユは客単価が低い。売り上げはバティニョルのほうがずっといい」この市場にスタンドを持っている人は、野菜を保冷庫に保存する生産者や販売者がほとんどだが、ジルさんは、木金土日に収穫して、そのまま市に持ってくる。「市に出す店の中で、保冷庫を使わないのはうちだけ。採りたてだから、買って家の冷蔵庫に入れたとき、野菜の生命力が長持ちするんだよ」パトリシアさんは、ジルさんの店の売り子さんで、テキパキ働く、大きな黒い瞳が印象的な美人。毎週野菜を買いにくるたびに口説く男性がいるほどだ。パトリシアさんは、客の知らない野菜があると、とてもていねいに説明してくれる。ついでに料理方法も教えてくれるから、客はついつい冒険して買ってしまう。
野菜のことをよく知っているので、最初は農家の人だと思っていたが、それにしてはちょっと雰囲気が違う。「普段はメルセデス・ベンツ社の支店で、販売の管理をしている」と、意外な返事が返ってきた。朝市で働くようになったのは5年前だという。失業していたときに、声をかけられた。今の職が見つかってからも、朝市での仕事が気に入って、土日はここで働いている。
農家並みに野菜に詳しいのは、出身地のブルゴーニュで家族が農地を持っていたのと、休暇を利用してジルさんの畑に手伝いに行くからだという。
パトリシアさんのセンスのおかげで、ジルさんのスタンドには、その日の野菜が彩りよく並んでいる。バティニョルに立つBIOの朝市。

「売り上げはラスパイユの市よりずっといい」とジルさん。朝市のジルさん。右は、週末にジルさんを手伝っているパトリシアさん。

フランソワさん「家がこの近くで、1989年から毎週通っているよ。最初は値段が高いと思ったけれど、質の良さには代えられないね。買うのはいつもの同じ店だ」
ナディアさん「きょう買ったのはルバーブ。コンポートやタルトにするとおいしいの」
71歳の女性「昔からBIOの市の常連よ。味が違うから、もう元には戻れないわね。でも、BIOのスーパーは、競争相手がないから高くて。今は年金生活だから、たくさんは買えないけれど、少量でも良いものを食べたほうがいいわね」

フランソワさん

ナディアさん

BIOの認証とロゴ
BIOの認証は、費用を払って申請しないともらえない。農作物の場合は、政府の有機栽培規定に従い、2年の転換期を経た農家が対象となる。費用は面積や栽培している作物の種類によって違ってくる。ジルさんは毎年365ユーロを払っている。認定されると、フランス政府の有機認証ロゴの〈AB〉が付けられる。
年に1回以上検査が入る。

ジルさんの野菜はレストラン御用達。
昨年ミシュランで1ツ星を獲得した8区のフランス料理店〈ステラ・マリス〉では、10年前からジルさんの野菜を使っている。店の人たちが、毎週バティニョルの市に買出しに行く。「ここの野菜は味が濃いですね。それに、コンフリーconsoude、イラクサortie、ホップの葉houblonといった変わった食材がありますし」と、パリ店の藤本清シェフ。イラクサはどこにでもある雑草だが、ミネラル分が豊富。BIOの市にもめったに出ないため、ジルさんの店では、あっという間になくなる。
イラクサのスープ
イラクサを約二つかみ、ちくちく痛いので手袋をして、丁寧に水洗い。鍋にバターを大さじ1杯とって、イラクサをしなっとするまで5分ほど炒めていく。皮をむいて小さく切り分けたジャガイモ2個とニンニク2片を加え、水(あるいはトリガラのスープ)を1リットル加える。沸騰してきたら、フタをして40分ほど煮込んでいく。最後にミキサーにかけ、塩とコショウで味を調え、好みで生クリームあるいはバターを加える。(このレシピは真)右がイラクサ。

友人たちとBIOの夕食会。
 バティニョルの市に店を出す人たちが、仕事が終わって一杯飲む店が、近くのレストラン〈L’escapade〉だった。ここでは、土曜の昼、BIOの市の食材を使った料理が出ていた。ところが、オーナーシェフが引退して経営者が変わり、ここでの集いは終わる。ある土曜日、ジルさんは、市の仲間や顧客と一緒に、市の近くのカフェ・レストランでBIOの夕食会を開いた。引退した元シェフが、この日、一日シェフとして腕を振るった。アペリティフはBIOのロゼ・ワインと自家製ポテトチップス。前菜は白アスパラのクリームムース添え、主菜は子羊のモモ肉と軽く火を通した夏野菜、デザートはフルーツサラダ。素材を生かしたシンプルな味付けで、野菜のエネルギーが体にしみわたる。仲間同士で打ち解けて、以前のレスカパードのような和気あいあいとした雰囲気が戻ってきた。
バティニョルの市に店を出す人たちが、仕事が終わって一杯飲む店が、近くのレストラン〈L’escapade〉だった。ここでは、土曜の昼、BIOの市の食材を使った料理が出ていた。ところが、オーナーシェフが引退して経営者が変わり、ここでの集いは終わる。ある土曜日、ジルさんは、市の仲間や顧客と一緒に、市の近くのカフェ・レストランでBIOの夕食会を開いた。引退した元シェフが、この日、一日シェフとして腕を振るった。アペリティフはBIOのロゼ・ワインと自家製ポテトチップス。前菜は白アスパラのクリームムース添え、主菜は子羊のモモ肉と軽く火を通した夏野菜、デザートはフルーツサラダ。素材を生かしたシンプルな味付けで、野菜のエネルギーが体にしみわたる。仲間同士で打ち解けて、以前のレスカパードのような和気あいあいとした雰囲気が戻ってきた。