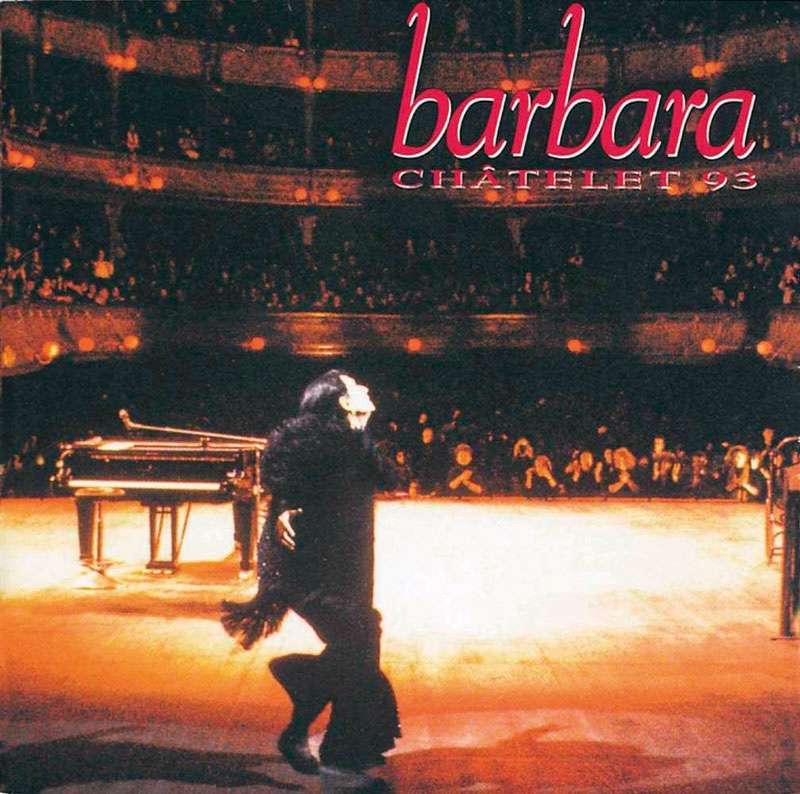メルザギさんとその娘アベドさん
M(メルザギさん):イスラームへの誤解を解くためにインタビューするというのはとてもいいと思います。イスラームそのものが「平和」という意味なのです。わたしは4歳の時にアルジェリアから来ました。今、ラマダーン月です。ラマダーンは新月から新月までのひと月、だいたい28日から29日続きますが、その時期は一年に12日ずつずれてゆきます。今年は秋ですが夏に当たることもありその時は厳しいです。日の出から日没まで食べてはいけない、飲んではいけない、しかし、基本はそうしたことを自らに課すということなのです。強制ではありません。夏のラマダーンの場合には午前3時ごろから断食にはいるので辛いです。秋のラマダーンでは午前6時すぎからなので昼だけ断食すればよいので楽です。
イスラームの特徴は、人が神と直接接することにあります。イマーム(導師)は祈りを導きますが、別に告白を聞くこともないし、人々と神を仲立ちするのでもありません。教会のようなヒエラルキーがあるわけではないのです。
ラマダーンは病人、旅人、妊娠中の女性には課されません。子供は思春期にさしかかる12歳から15歳以後に始めるのが普通です。
A(アベドさん):私の場合は12歳の時に経験したけど辛かったですよ。
M:ラマダーンの終わりには綺麗な服を着て子供は喜びます。終わりの祭りはイードといいますが、その40日後には大きなイードがあり、羊を犠牲にして皆で祝うのです。他の宗教との違いは、クルアーンが、神から天使ジブリール(ガブリエル)を通じた預言者ムハンマドへの直接の啓示であり、神から得た霊感による言葉の解釈ではないという点です。直接の啓示を書き留めたものがクルアーンだとしても、ひとからひとへ直接の伝承によって伝えてこられたものなのです。
A:私はラマダーンはしますが、祈りはしていません。母が強いるということもありません。
M:それぞれが判断すればいいことですし、よきことはおのずからおこなわれるようになるというのがイスラームの考えです。
今、丁度、日没でラジオで日没が告げられるところです。日没が告げられると体を清め、祈り、食事をします。最初にナツメヤシの実を三つ食べるというのは預言者の始めた仕方です。今はいろいろな食材がそろって入っているスープを飲むことからはじめます。
A:ラマダーンの間、日没のあと人々は家の料理を隣近所の人々と分かち合って食べます。たとえばわたしたちも近くのパキスタンの人たちと交換し合いました。こうして皆が知り合うというのがラマダーンなのです。
M:イスラームは普遍宗教つまり異なった民族や部族やさまざまな違いをこえて人々が互いに知り合うためにこそ生まれたものなのです。祈るためには人はそれぞれ自分で選んだモスクに行きます。とりわけ気に入った説教をする人がいるところを選んで行きます。説教のうまさはやはり深く考えさせて感動させるものであるということです。ですからクルアーンの知識はもちろん、さまざまな知識を持った人でなければ人に訴える説教はできません。わたしはタンジェ通りの大モスクの説教師がたいへん素晴らしいと思っています。それにそこではさまざまな興味深い催しもやっていて人を惹き付けます。その点では5区の大モスクはあまり魅力を感じません。
私自身も仕事から身を引いたら是非巡礼はしたいと思っています。費用だってそれほど大してかかるわけではありません。巡礼にいくと、本当に人々が皆兄弟であることに感動して帰ってくるのです。それが巡礼のもっとも大事な点なのです。 
巡礼にいくと、本当に人々がみな兄弟であることに感動して帰ってくるのです。
それが巡礼のもっとも大事な点なのです。
●メルザギさんの理容院〈Antinea〉: 25 rue Bichat 10e 01.4245.0808
M。 République/Goncourt 火~金
9h-19h。
シャンプー+カット+ブロー:25euros。
タハールさん
生まれたのは1964年、パリ郊外のエヴリーだ。学校での生活はごく普通だった。父も母もイスラームの熱心な信者だけど、僕は信者じゃない。無神論者といっていい。ラマダーンもべつに断食は守っていない。家では断食することを強いるわけじゃない。イスラームの信仰はべつに人に何かを強いるというのではないんだ。両親はだから僕に信仰を強いてはいないよ。それぞれが選べばいいのさ。それがイスラームの考え方だよ。母はラマダーンの間でも僕が家に帰って何か食べたいといったらちゃんと用意してくれる。
両親はアルジェリア出身だけど、僕は1974年に一度行っただけ。もちろん親戚やイトコたちがたくさんいるけど、懐かしいという感じはないね。
生まれたのはアルジェリア独立の直後だった。だから、周囲との関係はかなり厳しかったことは確かだな。アルジェリアはその後ひどくなった。今も、宗教的な急進派の少数者が幅を利かせて国はひどいことになっている。ひどいテロがおこなわれたし、政府そのものもからんでいたから。80年代ごろからそのきざしはあった。カビルの人たちにカビル語を使うことを禁止するなど差別と抑圧が強くなった。いろいろなことを起こしているのはほんとうに一握りの連中なのさ。
もともと僕は電気関係の技術を身につけたんだ。だけど僕らは会社の正社員になるのは難しい。臨時雇いということがほとんどだ。リコーやソニーの日本系企業でも仕事したことはあるよ。そういう電気技師の仕事をやっているうちに音楽のミキシングをやった。もともと小さい時から音楽が好きでドラムスをやっていたから、それとミキシングが重なって今の仕事につながったというわけ。
ここは貸しスタジオで、練習したり録音することもある。そこの一番大きなスタジオは客も入れるから月に一度はコンサート会場にもなる。最終の月曜日にミュージシャンが集まってくじ引きで組み合わせを決めたりして演奏するのさ。実際今会費を払っているのは600人くらい。会費は15.25ユーロ。ずいぶん半端な金額だけど実はちょうど100フランなのさ。非営利団体で、国や自治体の補助ももらえる。主な収入は貸しスタジオの使用料で、特に夜と土日は一杯だね。プロのミュージシャンは平日でも入るけど、多くは仕事の後ここで練習したりするんだ。

イスラームの信仰はべつに人に何かを強いるというのではないんだ。
それぞれが選べばいいのさ。
時は1975年、所はベルヴィル。エミール・アジャール(ロマン・ギャリー)著の『La vie devant soi』の主人公モモに架空インタビューしてみた。モモは、3歳の時からユダヤ人のおばあさん、マダム・ロザに引きとられて育てられ、インタビュー当時14歳くらいだった。
「このへんにはアフリカ人も住んでいるけれど、多いのはアラブ人とユダヤ人だ。マダム・ロザもユダヤ人だけれど、アラブ人への差別はないよ。彼女の口癖は『辛い生活をおくっている時にはアラブ人とユダヤ人の違いなんか関係ない』だし、アラブ人のボクをとても可愛がってくれる。他にも何人か娼婦の子供を預かっているけれど国籍もさまざまだ。歳をとって足が弱り太っていて心臓も弱いのに、ボクらのアパートは7階だから、階段の昇り降りがきつそうだ。そして夜中に、アウシュヴィッツの収容所に入れられていた時代の悪夢にうなされて目を覚ましたりするのがとっても可哀想。強制収容所の時に少しも助けてくれなかったような神を、彼女は信じていない。でも、ボクのおとうさんといってもいいムッシュー・ハミルは熱心なイスラーム信者だよ。だから、いつもあの優しい微笑みがあるんだ。ムッシュー・ハミルからはイスラームのことをいろいろと教わっている。ボクにはモロッコ人かアルジェリア人の血が入っていると思うから、イスラームを信じることで、ボクなりの故国を持ちたいからね。いつかマッカにも行ってみたい」(インタビュー:真)

*写真はモシェ・ミズラヒ監督の『La vie devant soi』より。モモ役はサミー・ベン・ユーブ。