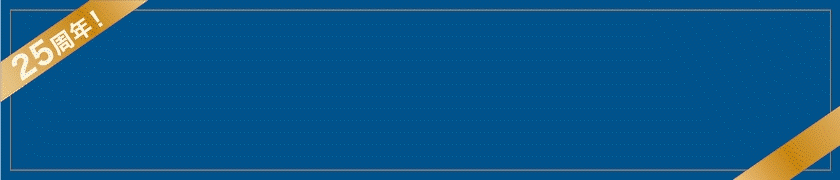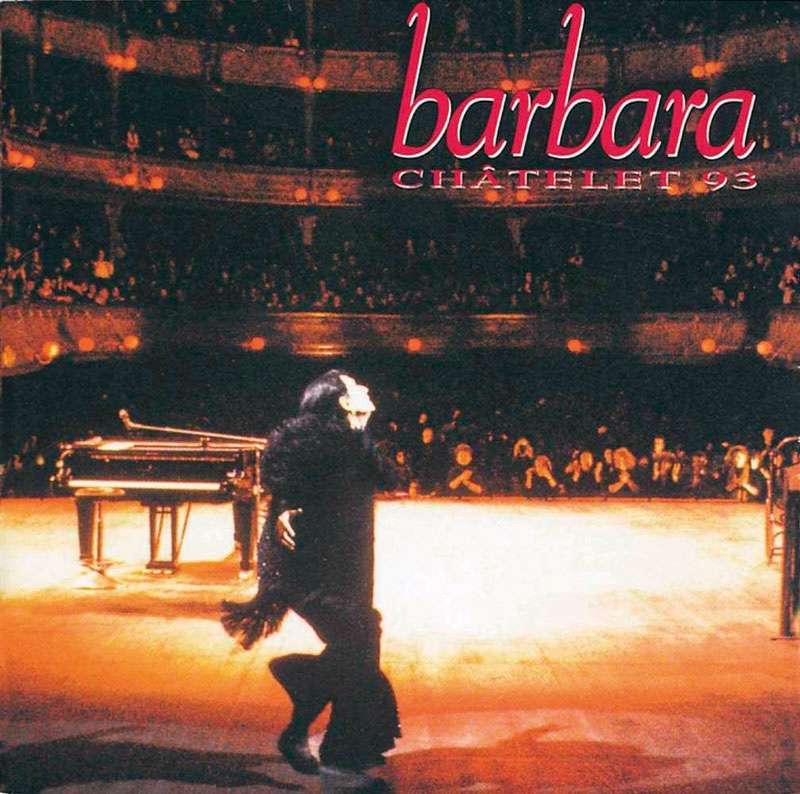| mettre sa main à couper “mettre sa main à couper(手を切られるようにする)”、”mettre sa tête à couper(頭を切られるようにする)”、”mettre sa main au feu(手を火に入れるようにする)”、いずれの表現も「確信をもって断言する、肯定する」という意味の表現で、中世の残酷な試練が思い起こされてしまう。中世には、裁かれている人が有罪か無罪かを一番正確に断定できる当時ならではの「火の試練」という手段があった。被告に真っ赤に焼けた鉄を持たせたり、やはり真っ赤に焼けた鉄の手袋をはめさせたりし、その火傷が三日以内に治った場合は、神の介在があったとして無罪が宣告された。それから歴史も進歩し、手を切られたり、火に入れられてもいいと誓っても、それが本当に実現される心配はなくなったから、安心だ。 |
「本当に切ってもいいのかな?」
「ボクがそう言っているんだから!」
|
 「きちんと返してね」 |
prêter l’oreille “Prêter l’oreille(耳を貸す)”といっても、単に「聞く」、「聞こうとする」という意味だからご心配なく。辞書プチ・ロベールには、”prêter”は、「何かをある期間、誰かの意のままにさせること」と出ている。さらに「返してもらえるという条件で何かを与えること」と付け加えてある。ところでなぞなぞを一つ。耳を貸すことを渋る人は? …答えはメガネをかけた人。 |
| prendre ses jambes à son cou
“prendre ses jambes à son cou(足を首にとる)” というのは大急ぎで逃げること。でも実際こんな格好で走れるのだろうか?足を地につけることだって至難の業だ。じつはこの表現は12世紀までさかのぼるのだが、そのそもそもがコジツケ気味だったのだ。当時 “prendre ses jambes sur son col”という言い回しは、旅に発つことを意味していた。というのも、歩くのに欠かせない「足」が、ここでは旅する時に首に巻いていた荷物の意味で用いられている |
 |
 |
bouche en cul de poule メンドリの尻の穴を間近でつくづく見たことはなくても、それが顔にあったら口に当たることは想像できる。口笛を吹くように、それをすぼめてほっぺたをふくらませれば、メンドリの尻なら、それは卵を産む時。”avoir la bouche en cul de poule(メンドリの尻の穴のような口をする)”という表現は、何かがほしくて、こびを売るような表情をすること。話はちょっと変わるけれど、例えば、警察署で尋問を受けることになったとする。あなたを責める警官は、梅干しをしゃぶっている時のように “avec une bouche en cul de poule(口をすぼめて)”、”tirer les vers du nez(あなたの鼻の穴からミミズを引っ張り出す=巧みに秘密を聞き出す)”ことに力を尽くすけれど、驚いてはいけない。彼は “poulet(ニワトリ=警官)” なんだから。 |
| pied de nez 「ママン、水の上を行く船は足があるんだよね?」、「おばかさん、当たり前でしょ。なかったらどうやって前に進むの」。子供たちの想像力には限りがないけれど大切にしたい、ということをこの童謡は教えてくれる。でも、”pied de nez(鼻の足)” ってなあに?そりゃ鼻には穴が二つあって鼻毛がのぞくことはあるけれど、足は見たことがない! そんなものが出てくる鼻の身にもなってごらんなさい。この”pied de nez” という言い回しの本当の意味は、辞書リトレによれば、「片方の手の親指を鼻先にあてて、その手をいっぱいに開いてから、その小指にもう一つの手の親指をあててその手を開く仕草」と出ている。その二つの手の全長が、ちょうど、昔の長さを測る単位のピエ(約33センチ)に一致するのだそうだ。”faire un pied de nez” というのは、話し相手に希望と現実の間の隔たりを気づかせるように、からかい気味に顔をしかめ、いびること。 |
 |
 |
les bras m’en tombent フランス語ではすごくビックリすると腕が落っこちてしまう。ビックリして身動きできない様子だ。驚きを表すオリジナルな言い回しは他にもいろいろとある。”être bouche bée(口をぽかんと開ける)”、”être sur le cul(尻もちをつく)”、”avoir le souffle coupé(息が切れる)”、”se faire scier la nouille(ヌードルをのこぎりびきされてしまう)”…。どれをとっても、コトバ、足、息、ヌードルと、なにかを切られてしまうのが共通していて、ビックリですね。 |