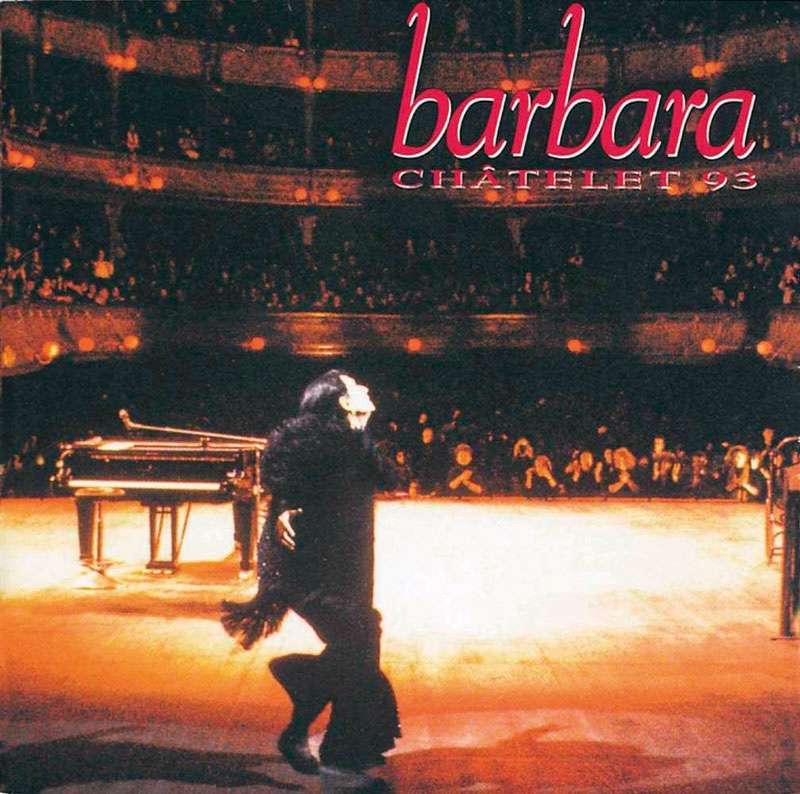peigner la girafe
フランス人にはキリンはあまりなじみではありません。あの背の高さでは、せいぜい動物園かテレビの動物番組で接するくらいです。そのせいか、キリンが登場する表現は、 »peigner la girafe » 一つだけ。あの長~い首が、 »un torticolis de girafe »、 « le long de la girafe »、 »du haut de la girafe »、 »avoir le cou long »といったような面白い表現にならなかったことには驚かされます。とりわけ、19世紀に初めてキリンがやってきた時、あれだけ騒がれたというのに…。1826年にエジプトを出航し、マルセイユで寒い冬を避け、1827年の春になって徒歩で上京。6月にパリに到着した際には大歓迎されました。その18年後に亡くなるまで、キリンを見るためにパリの植物園に群衆が押し寄せました。その剥製は、今でも、ラ・ロシェルの自然博物館に保存されています。 »peigner la girafe(キリンをくしですく) »というのは「ムダ仕事をする」という意味です。その起源には諸説がありますが、いつまでもキリンをくしですいているわけにはいきませんね。

「お値段は…」
「バナナ2本です」

フランスでウサギは、赤ワイン煮、マスタードソース風味、パテ…と、大切な食材です。また、ウサギは森の中を走り回り、町ではペットになり、ウサギを使った表現が多いのは驚くことではありません。 »un chaud lapin(精力絶倫の男) »、 »le coup du lapin(後ろからの一撃、ムチ打ち症、裏切り) »、 »pattes de lapin(短いもみあげ) »、 « courir comme un lapin(素早く逃げる) »…。こじつけ表現の代表は、 »poser un lapin » でしょう。昔は、 »lapin » という語には、「嘘の話」、「誇張」といった意味合いがあり、それが少しずつ「失望」というニュアンスになりました。また、19世紀の売春界では、 »lapin » は「やみ払い」と同義で、そこから « poser un lapin(ウサギをおく) »というのは、「娼婦たちのサービスを無料で受けること」を意味するようになりました。その少し後で、学生たちによって、現在の「約束をすっぽかす」という意味になりましたが、当時の学生たちは、ひまな時間、何をしていたんでしょうね。
「彼女、なにしてるんだろう?」


「自分の舌をネコにやる」…なんて野蛮! とはいえ、この表現は、これでも時とともに和らげられたものになりました。というのも、以前は、 »jeter sa langue aux chiens(イヌに自分の舌を投げやる) »といっていたからです。自分を切り刻むことは、敗北や放棄を認めることかもしれませんが、舌をもらったネコの気持ちまではわかりません。もしネコが人間の舌が好物だとすると、それは知れわたっているはずですよね? 言い回しを文字通りにとると、 »la chair de poule(鳥肌) » が立ちます。 »donner sa langue au chat »というのは、子どもたちがなぞなぞをやっていて、わからなくて降参したときに使う表現です。フランス人最大の残酷性が、子どもたちの口から出るというのは皮肉ですね。