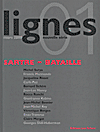●Lignes, nouvelle serie, « Sartre-Bataille », mars 2000
今年の頭からフランスのメディアにサルトルがよく登場している。サルトルについての本がいくつも出版され、雑誌・新聞での特集はもちろん、サルトルの名が付く広場までつくられた…。もちろんすべては、サルトル没後20年を記念している。
サルトルとB、といっても、その広場に共に名を連ねているボーヴォワールでもなく、サルトルの弟子、ベルナール (アンリ・レヴィ) のことでもなく、サルトルと同じく没後20年の批評家、ロラン・バルトのことでもない。「新たなる神秘家」、バタイユのBだ。
やたらと生誕何年とか、没後何年とかで盛り上がるフランス文学=思想をめぐる一般のディスクール、こうしたある種の「制度的」な波の中で、 »Lignes » の刷新第一号、サルトル—バタイユ特集は深いところをついている。
「戦後30年は、サルトルの時代であったとしかいえないのだろうか? 今日ではバタイユ的ともいえるのではないか」と序文で示唆するのは、バタイユ研究で知られるミシェル・シュリヤ。そして数々の執筆者の中で、ジャン=リュック・ナンシーは「我々は全て、ある意味、 »サルトルとバタイユ » であったし、今でもそうである」と述べる。
この雑誌は、単にサルトルだけ、あるいはバタイユだけの思想に親しんでいる者たちに新たな地平を広げるだけではなく、この一見両極端の二つの思想を通して、戦後思想、つまり現代、「もはや人間のイメージをガス室から切り離すことの出来ない*」我々の時代の思想を思考しようとしている。(樫)
*Georges Batailles, »Sartre », Critique, 1947, n。12