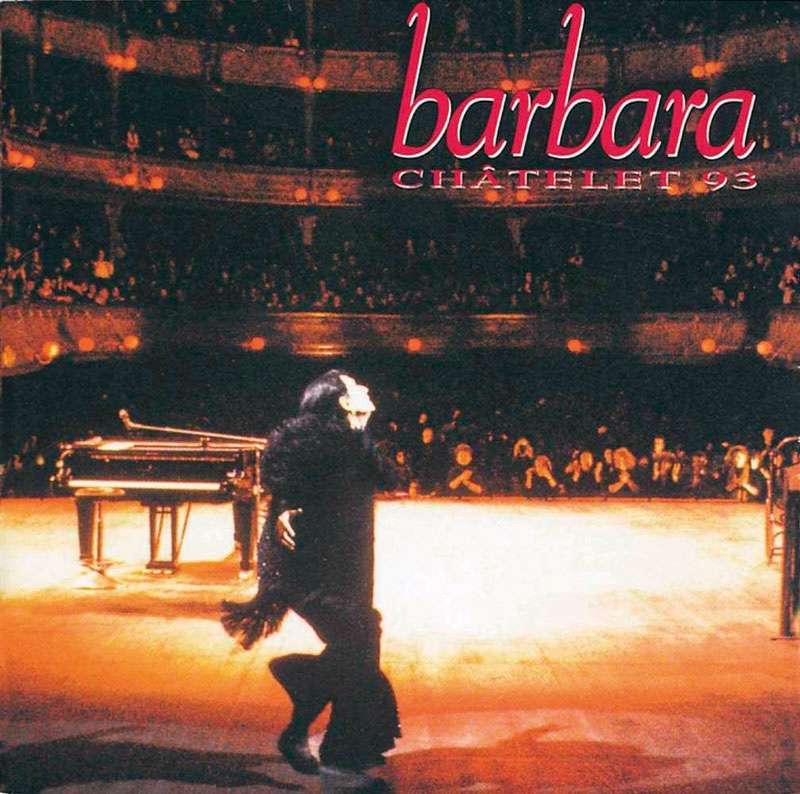ゲランドの天日塩
「塩」というのは塩化ナトリウムだけでできているもの、そう思っているひとは少なくない。というのも、売られている大半の食卓塩は、99%塩化ナトリウムでできているからだ。日本では1997年4月1日に、92年間続いた塩の専売制度が廃止されたのをきっかけに、様々な海外の岩塩や海塩が紹介販売されるようになり、昨年からはゲランド塩も少しずつ輸入されるようになった。
 いのちを育んできたエキス。白い結晶と純粋さ。その塩を作り出す海は塩の無尽蔵の倉である。海は生命の起源だから、塩を摂取することはとどのつまり、生命の源である海を体内に取り込むことなのだ。
いのちを育んできたエキス。白い結晶と純粋さ。その塩を作り出す海は塩の無尽蔵の倉である。海は生命の起源だから、塩を摂取することはとどのつまり、生命の源である海を体内に取り込むことなのだ。
塩分は、人間の血液の中に1リットル中8gほど含まれていることからも、人間の生命の存続と不可分な関係にあり、最低1日に0.5gから10gは摂取しないと、ひとは生きてゆけない。日本の北部では1日40g以上摂取している地方もある。フランス人は、1日平均約20gほどの塩をとる。その四分の一は食品自体から、残りは塩による味付けから塩分を取っている。生理的な必然性とは別に、塩は味覚をかき立てるのに疑いなく最適な食材である。フランスでは、諺で「塩のない食卓は、唾の出ない口」と言うほどだ。
 塩は、二千年以上の歴史を持つ。塩にまつわる話は実に豊富だ。給料、サラリーの語源は塩である。古代ローマ時代に兵士に与えられた給料は塩(サラリウム)だったからだ。サラダも元は塩から来ている。
塩は、二千年以上の歴史を持つ。塩にまつわる話は実に豊富だ。給料、サラリーの語源は塩である。古代ローマ時代に兵士に与えられた給料は塩(サラリウム)だったからだ。サラダも元は塩から来ている。
太陽と風によって作られた海の塩は天日塩と呼ばれる。そして、この塩が最近は、静かだが深く広がりのあるブームを呼んでいる。なぜか? それを解くために、現地を訪れてみた。
ゲランドはどこ?
モンパルナス駅からTGVに乗ると、ロワール河沿いに西へ下り、約3時間でエビ漁業ではフランス第一を誇る漁港で有名なル・コワジックに着く。大西洋に突き出た岬町だ。その岬の入り江の内側がゲランド塩田である。
グエン・ラン。聞きなれぬ言葉はブルトン語で「白い国」。その名の由来を持つゲランド市は、塩田を見下ろす小高い台地の上にある中世の城塞町だ。塩田は、14世紀から建設されている27キロにおよぶ石垣の防波堤にしっかりと保護されている。現存する塩田の中には中世から変わらずに何世代にもわたって耕されているものもある。
ゲランド塩田の製塩法
ゲランドの塩田活動はあまりに古いので、ここで行われている塩田法が、いつごろからのものなのかについては、はっきり確定できていない。ルドン僧院に残された古文書によると、9世紀以前のローマ化されたものが基盤になっているらしいと、塩田博物館学芸員ビュロン氏は語る。その後、この地にブルトン人達が定着してから、彼らがこの伝統を引き継いで、塩田の開発を続けたのだろうと考えられている。というのも、塩田の一つ一つにはブルトン語の名が付けられており、塩田や工具を定義する固有名詞は多くが古ブルトン語であることからも、塩田がかなり古い時代に由来していることがわかる。
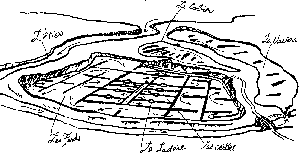 ゲランドでは、塩職人のことをパリュディエと呼ぶ。接頭語のパリュスはラテン語で「沼」の意。つまり、 »沼の人」を意味する。
ゲランドでは、塩職人のことをパリュディエと呼ぶ。接頭語のパリュスはラテン語で「沼」の意。つまり、 »沼の人」を意味する。
塩田は、太陽の光と風によって水を蒸発させて、塩分濃度を濃縮してゆき、飽和状態になったところで結晶した塩を収穫するのである。だから、多くの点で自然条件に依存した一種の農業であるとも言える。しかし、水位を利用して給水路から取り入れられた水は5つの異なった領域を巡回するのだが、その塩田構造を作り上げるのは人間だし、採塩池の床を平らにし、それぞれの領域に導入する水量の調節をするのも人間である。この水量調節も実は大変微妙で、一日の中でも風向きは変わり、たとえば、「塩の花」の収穫の時を例に上げると、西から吹く海風の時は、風は湿り気を帯び、結晶が遅く粗いし、東から吹く陸風の時は、風はからっとしていて乾燥も早く、結晶は早く進行しキメも細かい。そうした事態に応じて、水門の開閉を敏速にし、一日に数度の収穫をするときもある。人間は何もしていないようだが、実際には重要な役割を果たさなければならない。塩田作業はいわば、自然と人間の営為との競演なのである。こうしたコラボレーションがうまくできなければ、良質の塩を生産することはできない。
潮の満ち引きをうまく利用して水を取り込み、いくつかの水田を通過させながら塩分を徐々に濃縮してゆき、最後の採塩池で塩が結晶するのを待つのである。
以下にその構造を記そう。
それらは大きく三つに区分けされる。給水路、貯水池、塩田の中心部だ。最後の中心部が蒸発池と採塩池に分けられる。
エチエ=給水路。入り江から海水を取り入れる。これは、潮の干満によって満ちたり干されたりする水路で、常に貯水池を満たしておく役割がある。
ヴァジエール/コビエ=貯水池。入り江から取り入れた海水を常時ストックしておく最初の溜め池。深いところで60 cm~1 m、浅いところで25 cmほどある。
この溜め池は実にまちまちの形をしているが、おおよそ0.5ヘクタールから3ヘクタールの大きさだ。ここで、海水は初めて温められ、濃縮し始める。ここから、位相の低い塩田の中心部へと水は流れてゆくが、その流れの量を調節するのは、塩職人の知識と経験だ。ロティ=塩田の中心部。塩生産の要である。この部分がいくつもの水田群で成り立っていて、それらはすべて幅50~60cmほどの粘土が乾燥した、硬くてしっかりした細い畦道で結ばれ、ここでの水の流れはあたかも迷宮の道順を当てるようなものだ。この畦道がそれぞれの役割
を持った水田間の防水性の境界を形成する。その中心にオイエと呼ばれる最後の水田がある。このオイエの数で、ファール、アデルヌ(予備の塩田)の数が決まってくる。
ファール=水田。水嵩が4~5 cmで蒸発を促進させる。塩分の濃度は50g/l ほどで、オイエにたどり着く最後のファールでは200g/l ほどに濃縮される。
アデルヌ=予備の水田。オイエの水量を定常的に保つためにここへ海水を流し込む。各オイエ毎に1日に1000リットルほど給水する能力がないといけない。ほぼ400平米で、水嵩は2~3 cm。塩分度は250g/l。この濃度になると塩は結晶し始めるが、塩職人はオイエだけで結晶が始まるように水量を調節する。
オイエ=採塩池。塩田で最後に水がたどり着くところで、ここが、実際に塩を収穫するところである。一つのオイエは70平米くらい。水嵩は0.5~1 cm。オイエの床は完ぺきな防水性の粘土で、水温は摂氏37度に達し、塩分濃度は250~300g/l 。採塩池の中心に円形の場所があり、そこが要である。それをラデュールと呼ぶ。塩職人はそのラデュールを軸に塩のかき集め作業をする。塩を長い棒のついたラスと呼ばれる一種の木製のスキージでかき集めておき、あとでトロッコで畑の横に運ぶのである。
塩田活動の実際
ゲランドの天日塩製法は二千年にわたって改良された点もあるが、今日使われている技術や工具は前世紀のものとほとんど変わらない。ラスの棒の部分は木製からグラスファイバーになったが、スキージ部分はやはり木製である。いってみれば、何世紀も変わらずに来た過去のプリミティブな製法がそのまま生き延びていることになるが、前の章で述べたとおり、南仏に比べて弱点になっている量産困難な点、つまり太陽の光線がさほど強くなく、少しずつ結晶が進む点こそが、最良の質の塩を作りだす秘訣となっている。
とにかく、自然を熟知していないと仕事にならない。太陽の加減、風向き、その強さ、湿度、天候の移り具合、潮の満干などにたいして、適切な対応をしてゆかねば、塩田を運営することができない。毎日定期的に塩田の水位の確認をしておかねばならない。天候に非常に依存した生産方法なので、年間の収穫量は平均10,000トンだが、200トンから22,000トンと変化が大きい。気候の悪い年は組合全体で2000トン(1980年)、大収穫の時などは20,000トン(1990年)と平均年の倍になる。そのため、現在では「ゲランド塩生産者連合」は、三年間の塩を貯蔵して、非常時でも販売が一定 であるようにしている。