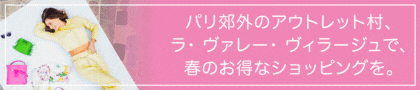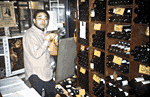アラカルト? 「本当はどこでもよかったんですよ。たまたまパリに友人がいたから…でも途中で生活費がなくなってきてね…」新薬開発のための人体実験の5行広告をオヴニーで見てミュンヘンまで出稼ぎに行ったのが15年前。その時知り合った仲間とパリで「便利屋」を始めた。「便利屋って、ちょっといかがわしい響きがあるのか、信じられないような注文を受けたことは数知れず…」 87年に映画化された“アラカルト・カンパニー”は、そんな小川さんのさまざまな経験をおもしろおかしく写し出す。
アラカルト? 「本当はどこでもよかったんですよ。たまたまパリに友人がいたから…でも途中で生活費がなくなってきてね…」新薬開発のための人体実験の5行広告をオヴニーで見てミュンヘンまで出稼ぎに行ったのが15年前。その時知り合った仲間とパリで「便利屋」を始めた。「便利屋って、ちょっといかがわしい響きがあるのか、信じられないような注文を受けたことは数知れず…」 87年に映画化された“アラカルト・カンパニー”は、そんな小川さんのさまざまな経験をおもしろおかしく写し出す。
「基本的には何でもやるんですよ」 電化製品、コンピュータの修理以外なら何でもやる…掃除の依頼は、バケツ一杯のハエの死骸と遺品の処理…精神病院で治療中の日本女性のアパートのしまつ…よく吠える日本犬のしつけ相談(この犬がネコを飼う???ことで問題落着)…もちろん「便利屋」の主な仕事、水漏れ、ペンキ塗り、照明器具、食器棚取り付け、住居紹介…。便利屋ゆえに見てしまった人間ドラマの数々は我々の想像以上に重いだろう。「あれは、すごかったね」と各々の感動、衝撃を語る反面、「それでも、けっこうおもしろいんですよ」と包み込むように微笑む。何年間か続いた読売新聞ヨーロッパ版のリレーエッセーでも“そんな小川さん”がうかがえる。
彼の家のバルコニーから修道院の窓が見える。「修道女たちはけっこういいもの食べているんだよ。タバコも吸うし、院内でバドミントン、ドッジボールもしてるし、我々俗人とかわらないね」 そんな姿に親近感を覚えると言う。
「お客さんのリストが3500にもなると、その数だけの家の深いところを見たってことかな」「仕事減ってきてるね。不況だからかな。でも静かになって、時間的余裕がでてきたよね」「もともと静かな生活がしたくて日本を出たんですよ。基本的に一人でやっているのは、楽だからね、そのほうが」 最近は、永年の経験で鼻が利くようになったのか“信じられない依頼”は幸か不幸かあまりないそう。でも話せない話もたくさんあるのだろう、と俗な質問は控えた。(麦)