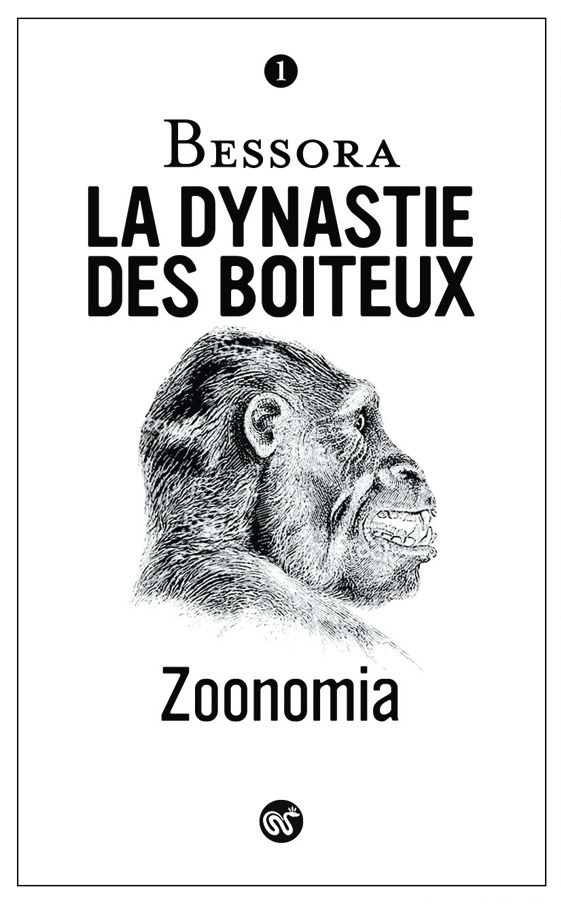
『 ズーノミア:足なえの一族 』(仮題)
Zoonomia : La Dynastie des Boiteux
著 ベソラ / Le Serpent à Plumes 社
未だ見ぬゴリラを求めて。
ヨアンはフランス人の父とレユニオン島人の母から生まれた「バタール(私生児)」だ。15歳になった彼は、はるばるパリに渡り、継母の住むアパルトマンを訪れた。ここから彼の夢を成就するための物語が始まる。夢、すなわち父のような冒険家になること、そして「白人」として最初に「ゴリラ」を発見すること…。
時は1846年、ヨーロッパでは奴隷貿易が次第に廃れ、その代わりとしてのアフリカにおける植民地政策は既に始まっていた。 ゴリラを見る、殺す、ひとかどの人物になるという夢に取り憑かれ、彼はガボンのジャングルで暗躍する。一見ただの冒険物語だが、むしろこれはゴリラという動物の姿を借りた、他者を征服するという植民地主義的欲望の寓話とでも言うべきものである。そしてなぜか、それが遺伝でもあるかのように、一族では 「Boiteux/足なえ」が、綿々と受け継がれている。
「見る」ものと「見られる」もの。
狩る、捕える、調べる、名付ける、分類する、博物館で展示する…。自然学者たちが行うこれらの行為は、時として、そこから権力と支配の関係が生まれるものとなる。1931年、植民地の住民たちを見せ物として「展示」したパリ植民地博覧会は、そのことを良く示している。あるいは記憶に新しいところでは、2014年に南アフリカのアーティストによる「Exhibit B」という展示に対してパリで大きな抗議が起きた。作家の意図は人種差別の歴史を批判することにあったが、生身の人間を「黒人」として展示することが植民地主義的眼差しの再生産とみなされたのだ。それほどに、「見る」という行為それ自体には力があるのである。
ヨアンはそのことをよく知り、だから彼は「見られる」側でなく「見る」側に立つことを至上命題とする。ただし、彼にとって「見る」とは「発見する」ことにほかならない。彼の母はレユニオンに住むが、その島を「発見する」のは彼女ではない。アフリカの原住民がゴリラを既に見たとしても、それは本当に見たことにはならない。それができるのは白人たちだけなのだ。
不完全なものたちへの讃歌。
奴隷制がいまだ残る時代、「見られる」側にいるということは、狩られ輸送される動物と同じく「モノ」になることを意味した。ところがモノではない、つまりこの場合は純粋な「白人」となるため、ヨアンは母と、そして理想とした父とも断絶しなくてはならなかった。ある偶然から、ヨアンは父の祖先にアメリカの黒人がいたことを発見するのである…。
血の神話を信奉するヨハアンは、自身をモノとみなす世界を否定せず、ただそれを再利用する。ただ面白いのは、彼がそこに完全には適合できないところだ。豚の剥製方法を教わる彼は、吐き気を催し、自分がその豚だと感じる。彼は一人前の白人男性の視線を共有できない。彼は、忌まわしき「遺産」である、彼の黒人の祖先が遺した聖書と時計をなぜか手放せない。彼はしばしば謎の亡霊を目にする…。
「Boiteux」は身体的な特徴を指すだけでなく、物事の不安定さ、一貫性の無さも意味する。何かが彼の中で上手くいっていないのだ。しかしこの不純さ、不完全さにこそ、このヨアンという人物の憎み切れない人間らしさがある。その意味でこの物語は、しがらみの中でもがく人々のたくましさを描いた一種の人間讃歌とも言えるだろう。驚くべきは、1667年英国コーンウォールから始まり1903年ヨアンの死に至る400頁以上にも及ぶ一族の物語は、まだ4部作の第一章にすぎないということだ。今後の展開にも期待したい。(須)

ベソラ
1968年、スイス人の母とガボン人の父のもとブリュッセルに生まれる。ガボンの石油の研究で人類学の博士号をパリで取得、その後1999年に自身のフランスでの経験をもとにした最初の小説「53 cm」を出版。







