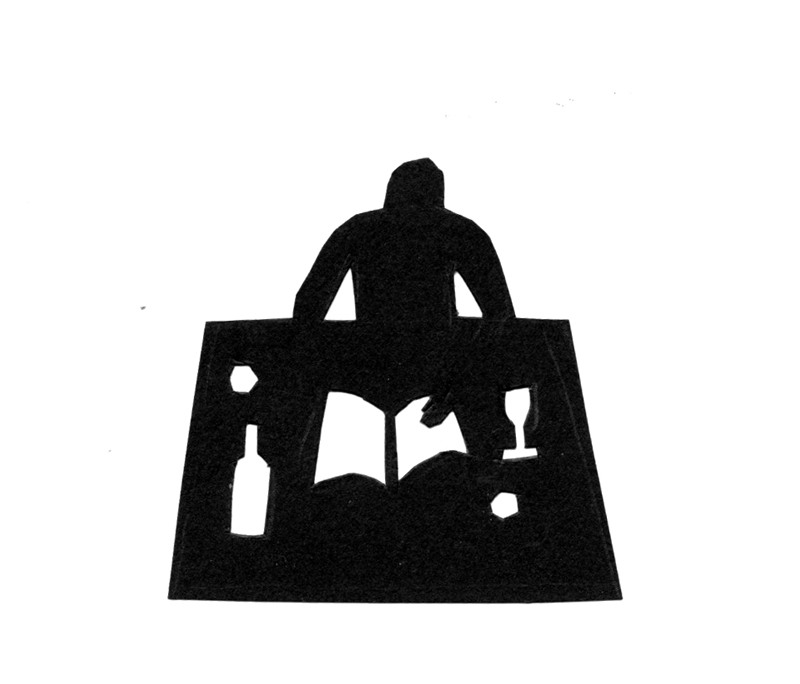
何においても「節制」を美徳とする哲学者ルソーだけれど、何も、日常の小さな悦びを否定しているわけではない。ごく若い時から、甘いものとワインは暮らしの中のささやかな慰めだった。『告白』(1770年)に、こんなくだりがある。「いったん大事な菓子パンを手に入れ、部屋にとじこもり、戸棚の奥からブドウ酒のびんを取り出すとき、小説を読みながらひとりでちびちびやる、その味のなんとすばらしいことか」(桑原武夫訳)。ちなみに「大事な菓子パン」は、原文では「ma chère petite brioche」とある。つまり、「わたしの」「親愛なる」「かわいらしい」「ブリオッシュ」。そんな愛しいブリオッシュは、一緒に酒を酌み交わす相手がなかなか見つからないルソーにとって、「社交仲間のかわり」にもなるのだった。この本が発行された同じ年には、ジャムとワインを贈ってくれた女友だちに礼状を書き送っている。「ジャムは大きな喜びを、ワインは心地よさをもたらしてくれています。(中略)このすばらしいワインを飲んで、わたしは胃と心とを温めているのです」。
経済的・思想的な理由から高級酒を買い求めたりはしなかったけれど、その食卓にはいつもワインがあった。パンとチーズ、果物にワインがあったら十分に幸せを感じられた。
ところで、『エミール』(1762年)には、家庭教師が生徒のエミールに悪質なワインを見分ける方法を説明するくだりがある。まっとうなワインを飲むための知恵は教育の一環、と考えていたのだろう。ところが、エミールの理想の恋人として描かれるソフィーには、あろうことか女性だからという理由でワインをたしなむ権利はない。時代のせいもあるだろう。でも、ルソーには、昔の恋人を神格化したかと思えば、苦労を共にする妻をまるで家来のように扱うような一面もあった。そんな矛盾は、こうやって代表作にも色濃くにじんでいるように思う。(さ)







