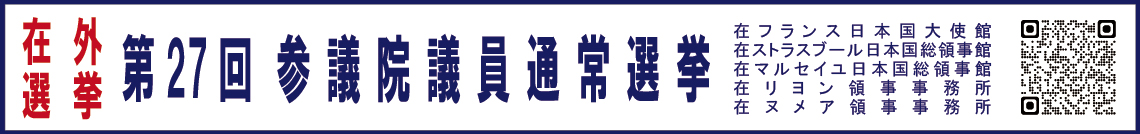『 世界は私の言葉である 』
著 アラン・マバンクー Grasset社/Points社から文庫
旅から生まれたエッセイ。
今回は小説でなくエッセイを紹介。小説家で詩人のアラン・マバンクーは、2016年にコレージュ・ド・フランスの教授職に抜擢されたことも話題となった。コンゴ共和国発祥のエレガントな「サップ」スタイルで学問の最高峰で教壇に立つ姿を一目見ようと、大講義室には毎週大勢の聴衆が詰めかけた。 最新エッセイはそのタイトルが示すように、著者が世界各地を横断しながら自分の、そして他者の言語を通じて世界を(再)発見する過程を綴ったものだ。
パリから始まり各都市の名を冠した21の説話から構成され、それぞれはその都市と深く関係する人物へと捧げられる。そのほとんどはアフリカ・カリブ文学の作家たちであり、著者は個人的な思い出とともにユーモアを交えつつ彼らを紹介してくれる。こうして生まれたのは他者との対話を通じた親密な個人史であると同時に、マバンクー流に書かれた小さな文学史でもある。
ソニーとの思い出。
どの話も興味深いが、特に印象深いのはマバンクーと同じくコンゴ出身の作家ソニー・ラブ=タンシとの思い出を綴った箇所だ。彼は79年に出版された『一つ半の生命』によって国際的な名声を得たが、この本を当時の現地の人々はすぐに読むことができなかった。本が高価過ぎたからだ。図書館に3部しかなかった本の完全な複製に成功した者たちから、他の人々は2日間だけ借りるために代金を支払ったという。 著者はまだ無名の学生時代、ソニーの居所を訪ね、彼からこの小説の草稿を借り受けた。世界に一つしかない草稿を初対面の自分に渡され、駆け出しの作家は困惑する。「私は感動に胸を締め付けられながら原稿をめくり、そして自問した。彼は訪問者それぞれに、彼らがそれを失くしたり改変させたりすることも恐れずに、それを貸していたのだろうか、と」。
マバンクーがそれを持ち主に返せたのはそれから数年後のことであり、ソニーが亡くなる2年半前のことだった。結局これが最後の出会いとなる。偉大な先輩が与えた無償の友情に助けられ、無名の若者はいまや仏語圏文学を代表する作家となった。著者から今は亡き先人への感謝の念が込められたこの挿話は、とりわけ感動的なものとして映る。
「アフリカ」から見る世界。
象徴的なのは冒頭の話だろう。パリ、J・M・ル・クレジオの講演会。隣り合った一人の女性に登壇者がアメリカの俳優に似てないかと尋ねられ、シドニー・ポワチエに似ていますねとあしらった著者は大変驚かれる。「冗談でも言っているの?シドニー・ポワチエは黒人、ル・クレジオは白人ですよ!」。
しかし彼にとって、年長の友人の肌の色は問題ではない。重要なのは、ル・クレジオが「もし私がアフリカについてこの肉感的認識を持っていなければ(…)私はどうなっていたであろうか?」と書くまでに、アフリカでの日々(8歳の時にナイジェリアに移住)が仏人ノーベル賞作家に深い跡を残したということなのだ。異境での経験は少年ジャン=マリ(ル・クレジオ)に他者の苦しみへと目を開かせ、やがて少年は作家となりアメリカへと向かった。
マバンクーにとってもまた、アフリカとは地理や人種(ブラック・アフリカ)によって既定される概念ではなく、他の世界と繋がり合う回路のようなものなのだ。 こうして大陸それ自体が再定義されるとき、セネガルの作家アミナタ・ソウ=ファルが言うように、アフリカ文学もまた「普遍的」なものとなるだろう。それは単なる文学的論争の問題ではない。「世界は私の言葉である」、は世界の見方を作り変えるという宣言でもあるのだから。(須)
Alain Mabanckou
アラン・マバンクー 1966年生まれ、コンゴ共和国出身。詩作からキャリアを始め、10作以上の小説を出版、数々の賞を受賞。人種問題を扱った 『黒人の嗚咽』(2013)など、エッセイストとしても優れた才能を発揮。