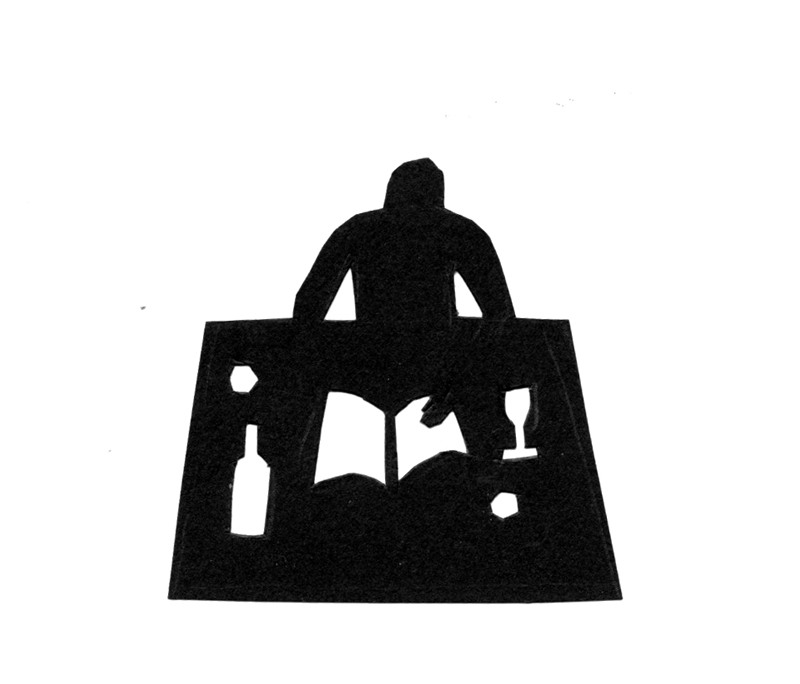18世紀に活躍した哲学者ルソーは、自らがもっとも重要な著書としていた『エミール』(1762年)で、「節制と労働、この二つこそ人間にとっての本当の医者だ。労働は食欲を増し、節制はそれが過度になるのをふせぐ」(今野一雄訳)と書いた。飽食にまみれた現代人には耳が痛いこんな一節を書いたルソーは、一方で、人生で味わうことの出来るあらゆる悦楽に敏感な人物でもあった。
中でも、自然がもたらす幸福感は、幼少期から晩年まで決して平坦ではない人生を歩んだルソーの慰めであり続けた。ルソーが自然愛に目覚めたのは少年時代のこと。母親を生後すぐに亡くして父親とジュネーヴに住んでいたルソーは、頼りにしていた父親とも10歳頃に離れて暮らすことになってしまった。血の気の多い父親が決闘騒ぎを起こして、ジュネーヴから逃亡することを余儀なくされてしまったのだ。
父親に代わってルソーの後見人になった母方のおじガブリエルは、ルソーと自分の息子をサヴォワ地方の小村にいるランベルシエ牧師の元に預ける。ボッセというその村の教会は、その当時はジュネーヴの統治下にあったという。そこでの暮らしは、10歳のルソーにとって一種の楽園だった。両親はいなくても、牧師とその妹は子ども達の面倒をよくみてくれた。山に囲まれた静かで牧歌的な風景の中でいとこと思い切り駆け回ったり、牧師に内緒で木を植えたりするのは最高に楽しかった。この時のことを振り返って、ルソーは「自然がたまらなく好きになり、それ以後、その想いが消えることはなかった」と書いている。
また、小さな頃から読書に親しんだせいか、人並み外れて早熟だったルソーは、いたずらをして牧師の妹にお尻を叩かれた時に快感を覚えたそう。その自伝で、無垢な少年時代はこのお仕置きで終わりを告げたなどと告白している。(さ)