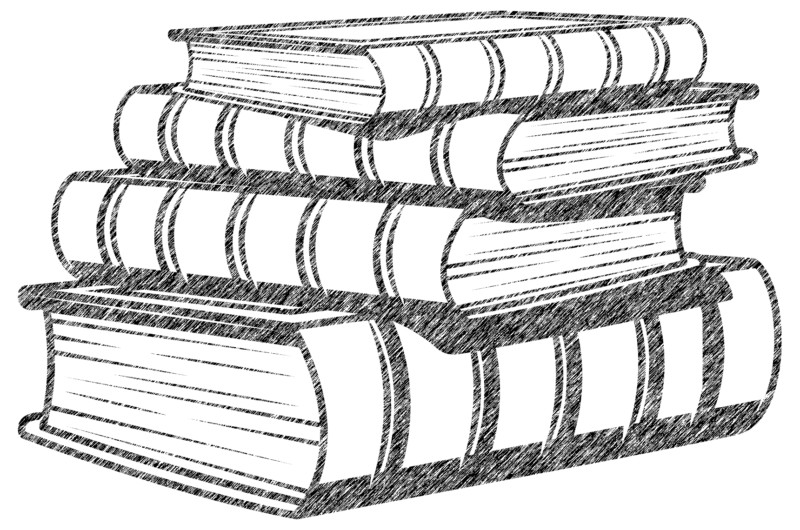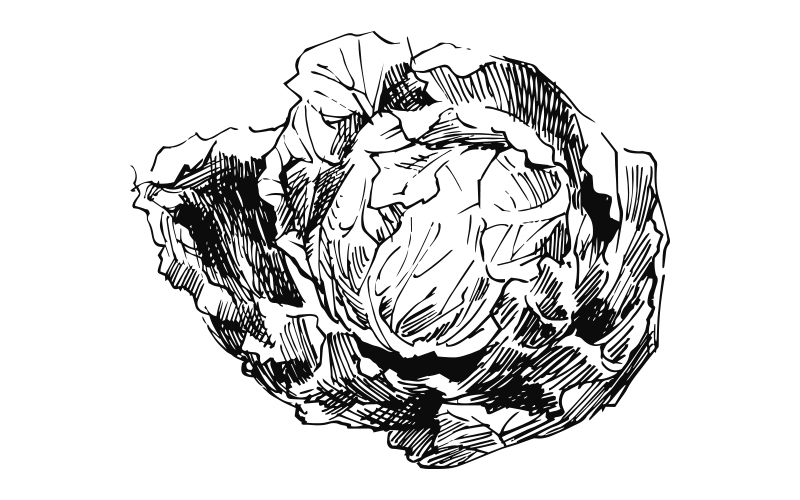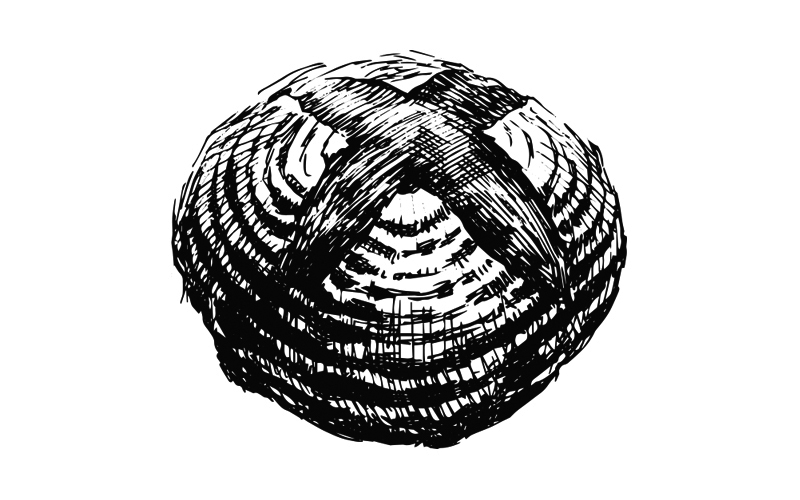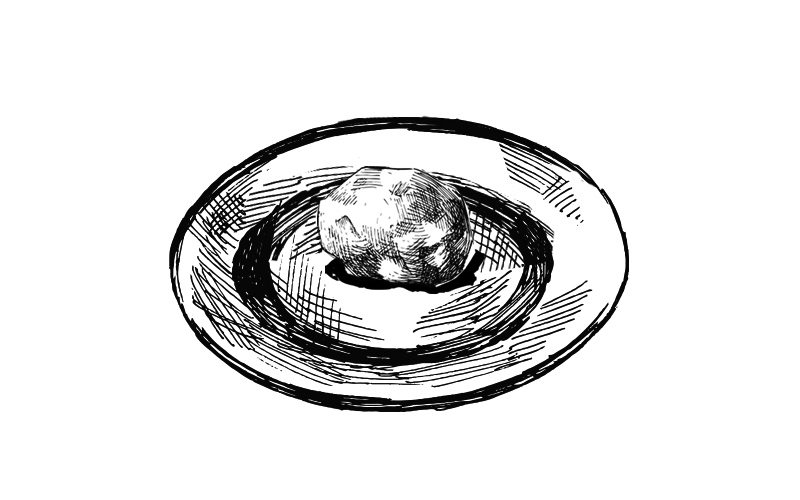モンテーニュの父親は、時の王フランソワ一世が文芸に寄せる愛着に大いに影響されていた。自らに高い学識はないものの、いや、むしろないからというべきか、知識人に強い憧れを抱いていたこの好人物は、愛する息子にはぜひ立派な教養をつけてやろうと考えた。そこで、当時の知識人が共通言語として使っていたラテン語を覚えさせるため、お守りはラテン語が堪能なドイツ人に託すことに。城内では、両親のみならず使用人までもが幼子に片言のラテン語で話しかけたため、フランスでフランス人の両親の元で育てられながらも、モンテーニュの母国語はラテン語となった。
そうやって努力することなしに自然にラテン語を学んだモンテーニュは、机に無理やり座らされて勉強するのは苦手だったよう。はやくも6歳でボルドー市の名門校コレージュ・ド・ギュイエンヌに入学し古代文芸に親しんでいったものの、堅苦しい規律にはまったくなじめない。おおらかに育ったモンテーニュにとって、教育の場でまかり通っていた「暴力と強制」は受け入れがたいものだった。
親戚の女性に向けて書かれた教育論という形をとった章で、モンテーニュは当時主流だった「権威で押さえつける」教育法を真っ向から否定している。「もしも彼らの教室に、血のにじんだ柳の小枝〔鞭〕のかわりに、花や木の葉を撒き散らしてあったら、どんなにかふさわしいことでしょう。私だったら、そこにスペウシッポスがその学校でしたように、喜びの女神と歓喜の女神とフローラ〔花〕の女神と美の女神の絵を描かせるでしょう」(原二郎訳)。食べ物についてもしかり、「彼らの利益があるところには、楽しみもなければなりません。子供たちには、体のためになる食物を甘くし、害になる食物を苦くしなければなりません」と子育てに喜びを取り入れる大切さを力説している。(さ)