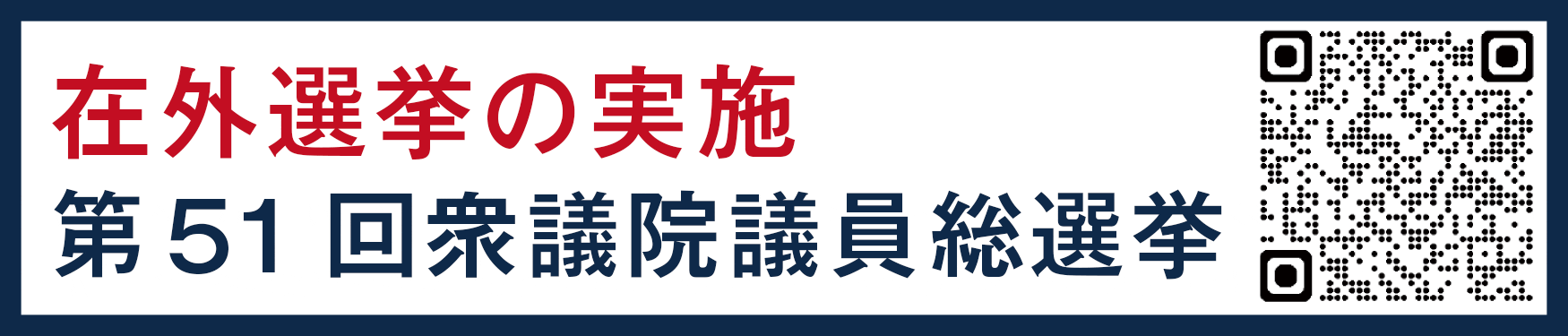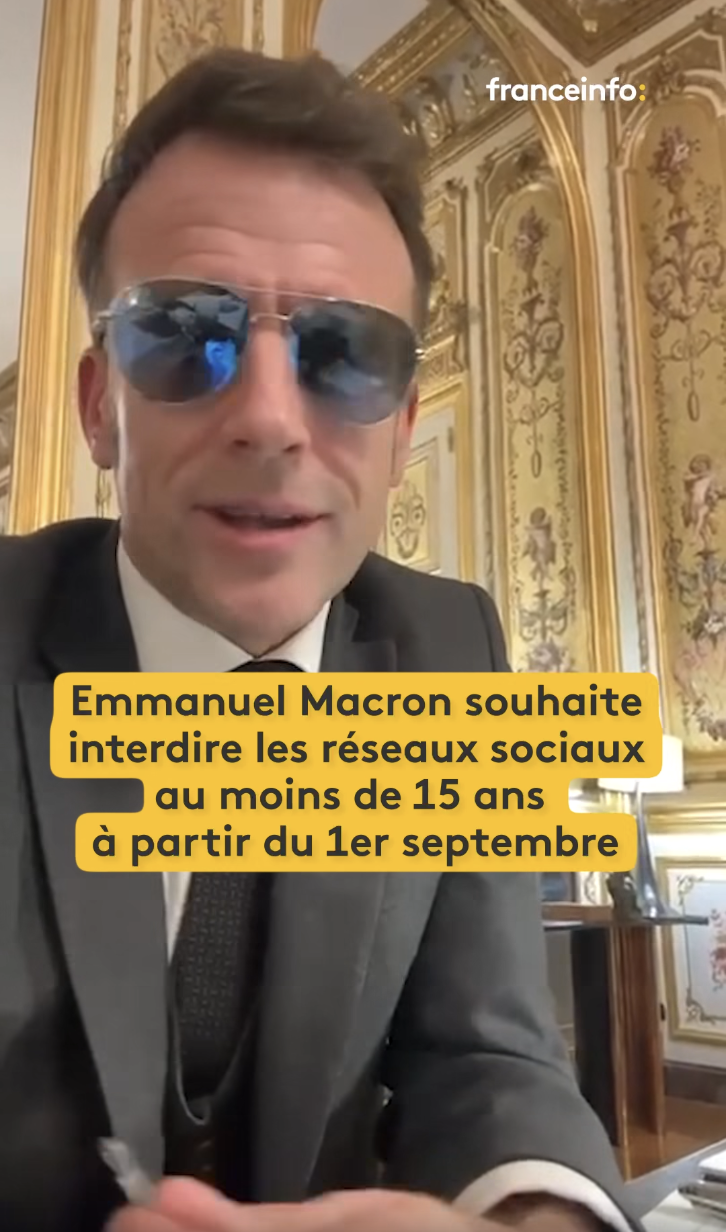佐伯祐三や藤田嗣治に憧れ、何人の日本人が「パリの画家」を目指してフランスに渡ってきただろう。そして、そのうち何人が「パリの画家」として認められ、画家として暮らし、そして画家として生涯を終えただろう。多くの者が成し遂げられなかった夢を生きた、正真正銘の「パリの日本人画家」赤木曠児郎(あかぎ こうじろう)さんが2021年2月15日、一時帰国中の故郷岡山で他界された。87歳だった。
赤木さんの作品を「パリの風景画」という言葉で一括りにしてしまうのはあまりに残念だ。キャンバスに浮き上がる緻密な線が描き出す花の都は、一見斬新でありながらも、クラシカルなイメージを失っていない。それは、時代を背負った建物への敬意を、作者がその対象物のフォルムの正確さと圧倒されるほどの精密さとをもって美に還元したからこそできた技だろう。美術書であると同時に、エッセー本でもある『AKAGI- CENT VUES DE PARIS/アカギの版画パリ百景』(2019年、Les Editions de la Galerie de Paris)の中で赤木さんは、自らが描いたパリの街角ひとつひとつに文章を添えている。そのほとんどが自身の体験から得た知識やエピソードが中心で、いかに彼がパリに根ざし、そしてその時々の場景を尊んできたのか伝わってくる。

物理学を専攻した岡山大学を卒業後、赤木さんは上京してファッション業界に飛び込んだ。洋裁の仕事をしていた同郷の香与夫人に出会ったのはこの頃だ。その後、デザイナーとして生計を立てつつも、好きで描いていた絵の道に進みたいという気持ちもあった。「先のことは、パリを見てから考えよう」。1963年、夫人とともにマルセイユの港に降り立ったとき、赤木さんは28歳だった。
ふたりはパリでモードの仕事に就き、オートクチュールの世界にも入っていく。赤木さんは次第に、日本の媒体にモード情報を書いて送るジャーナリストとしても活躍するようになる一方で、美術学校にも入り、絵を一から学ぶことにした。
「アカギの赤」で知られる「線」が生まれたのは、1968年。学生運動に端を発した五月革命の影響でアトリエが閉鎖され、屋外で絵を描き始めたのがきっかけだった。その3年後に美術サロンに出展した水彩画が金賞を受賞して以降、生涯で約150点の絵画がカルバナレ美術館など仏国内の美術館や国立機関に収蔵された。また早期にサロン・ドトーンヌなどの美術展の会員となり、160年の歴史を持つSNBA(フランス国民美術協会)では 名誉副会長に就任。2014年には芸術文化勲章シュバリエを受勲し、画家・赤木曠児郎は「日本人」という枠を超えたフランス画壇の重鎮となっていく。

2017年出品作 赤木曠児郎「パリ市庁舎」
けれども、赤木さんは普段、そのような権威を感じさせる人ではまったくなかった。高齢になっても、連日道端にイーゼルを設置して黙々と絵を描き、SNBAの展示設営中は金槌を持っていそいそと歩き回る姿が印象的だった。移動はいつも徒歩と地下鉄。イベントの招待状を出すと、香与夫人と手を取り合って気さくに足を運んでくれる人だった。無理にフランス的であろうともせず、かといってフランス生活への愚痴も聞いたことがない。勤勉でおおらか、そしてとても元気だった。2019年に先立たれた香与夫人が、90歳を超えても最期まで自宅で暮らし、病床に伏すことなく息を引き取ったように、赤木さんも亡くなる前日まで絵を描いていたという。
作品より前に出るスターになろうとせず、地についた暮らしを営みながら健康を維持し、画業を全うした赤木さんらしい最期だったように感じる。

2020年、赤木さんは長年の付き合いがある画商のジャン=ルック・マッソン氏と共に設立した「Kojiro Akagi 寄付基金」に自身の作品を寄与することを決めていた。基金の資産は、アーティストの支援や、フランスに暮らす日本人美術学生の奨学金のために使って欲しいというのが赤木さんの最後の願いだ。
岡山で永遠の眠りについたパリの日本人画家の作品は、これからも自身が描いた街で愛され続けるだろう。
赤木曠児郎さんがいたパリに暮らせたことを誇りに思いながら、この偉大な日本人画家を忘れないでいたい。
赤木さん、香与さんの傍でゆっくりとお休みください。
フランスにおけるお別れの会は、決定次第「Kojiro Akagi 寄付基金」会長ジャン=ルック・マッソン氏より発表されます。
お問い合わせ先:
Jean-Luc Masson, Président du Fonds de Dotation « Kojiro Akagi »
Tél. : 0646437463 / mail. : jlmasson(a)mac.com