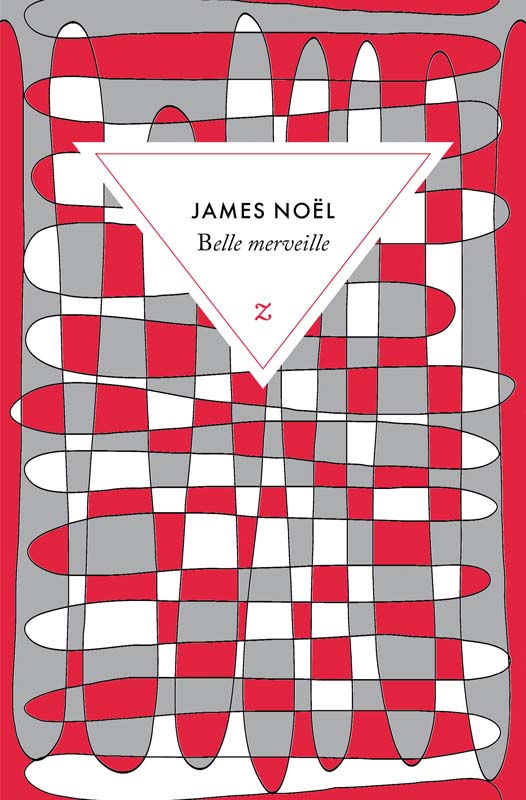
『ベル・メルヴェイユ(仮題) 』
Belle Merveille
ジェームス・ノエル著 / Zulma 社
ハイチ、大震災から7年。
2010年1月12日、ハイチは死者30万人にものぼる大地震に襲われた。この未曾有の災害は、いまだにその国の人々のこころと身体に大きな傷跡を残している。それから7年。この歳月の後で、どのような言葉がそれを語るのに相応しいのか? 自身もまたその生き証人であるハイチの詩人、ジェームス・ノエルによって書かれたこの物語は、私たちがすぐ求めるような同情、怒りや後悔といった分かりやすい感情を煽るものではない。死を見せ物のように撮影しセンセーショナルに報道するメディアに批判的な立場をとりつつ、また民衆の救世主のように他所からやってくる海外の支援にも厳しい目を向けながら、ノエルは首都ポルトープランスの青年ベルナールの姿を通じて、出来事と、そして祖国ハイチとの新たな関係性を模索する。
始まりはこうだ。「グドゥグドゥ」(現地の人々はあの大地震をしばしばそう呼ぶ)の生き残りであるベルナールは、NGOのボランティアとして被災地にやって来たイタリア人女性アモーレと出会う。廃墟と化した都市から逃れ、また崩壊した心身を回復させるため、アモーレはベルナールに、自分と共にローマへと旅立つことを提案する…。
現実とフィクションの間で。
だがここから、大地震の回顧録やローマでの二人の旅路が綴られるわけではない。この本は、小説の内に論理的で筋の通った物語を期待する人には、残念ながらまったく勧められない本なのだ。過去と現在、ここと他所を行ったり来たりするベルナールの思考には、震災の証言者たちの言葉が連なり、そこに島の歴史を見守り続ける蝶の羽音が通奏低音のように挿入される。しかも多くのメタファーに彩られ、時に夢とも現実ともつかないようなそれら言葉の断片たちは、あたかもベルナールの気まぐれな思考の順序そのままのように、ちぐはぐに接ぎ木されるのである。まるで物語それ自体の地盤さえもが崩壊し、その後で、一から再建されたかのように…。
とはいえこの意味でこそ、物語はその語る内容と同様に、その語り方においてもまた、いっそう、ハイチ的なのだ。「ベル・メルヴェイユ」。これは、信じがたいほど途方もない出来事が起きたときに、ハイチの人々が口にするクレオール言語だという。想像を越えたものへの驚嘆を示す言葉。魔術的なもの…。ヴードゥー? 作者はその言葉をこう説明している。「ハイチでは、それはとてもありふれた表現です。それは崇高と恐怖を同時に言うことを可能にします。(…)現実とフィクションの間の境界はとても薄いのです。西洋の目からは離れたものとして映るかもしれない、それら想像上のものたちには、共通の領域があります。ハイチでは、二つの世界には多くの通り穴があるのです」。
ハイチ、絶望と希望。
ベル・メルヴェイユ!崇高と恐怖。日常表現が含み持つこの両義性のうちに、ハイチの民衆が持つ知恵とたくましさを見る気がする。大地震、そのすぐ後に到来したコレラ(国連は6年後にようやく自分たちの責任を認めた)、さらに2016年のハリケーン・マシュー…。度重なる災いに痛めつけられながら、それでも人々は、生きることをあきらめないのだ。「私は地震のときそこにいて、すべてを経験しました。私はその時と同じくらい美しい思い出を持ったことはめったにありません。私は喜びの表現をいくつも聞きましたが、そこにはその日に近しい人を失った人々も含まれていたのです」、そう作者は証言する。苦しみの中に喜びを、生きる希望を見出すこと。アモーレ(「愛」の意)はベルナールを二度救済する。一度は崩れ落ちた廃墟から、次には彼自身の精神の危機から。二人の物語にはハイチの未来という重い荷が託されているのである。(須)

ジェームス・ノエル
1978年、ハイチの都市アンシュに生まれる。詩人として既にいくつも作品集を発表しているが、小説は今回が初。2012年から続くハイチ発の文学・アート雑誌「IntranQu’îllités」の共同設立者。







