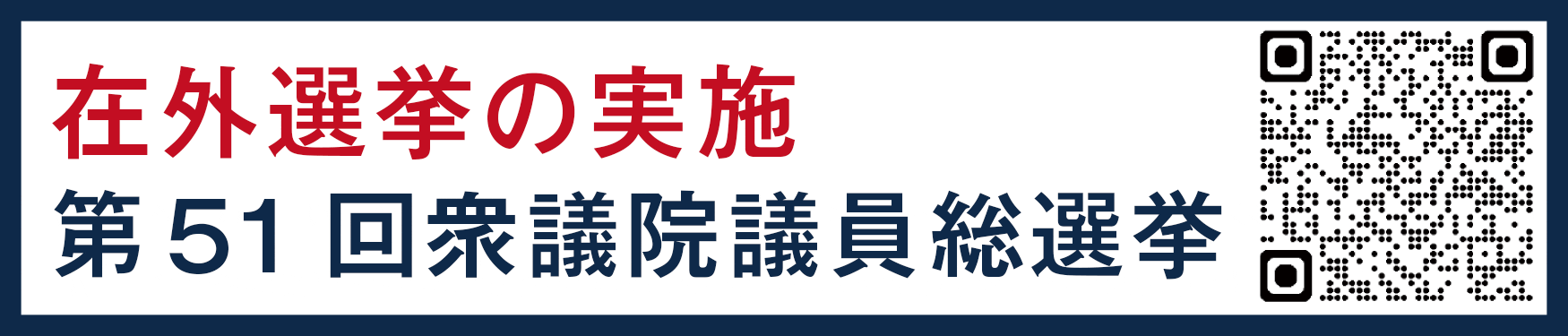『失われた時を求めて』の語り手マルセルに一目置かれていた女中のフランソワーズは、そもそも語り手の叔母レオニに仕えていた。パリに住む語り手一家は、復活祭などの休みになると汽車に乗ってレオニの住む田舎町コンブレーを訪ねるが、この滞在中に一家のために食事を準備するのがこの女中だった。後に語り手はコンブレーの各部屋を「グラニュ糖のような、花粉のような、たべられそうな、敬虔な雰囲気にまみれている」(井上究一郎訳)と思い出しているが、そんな回想はフランソワーズの料理の腕によるものに違いない。
『失われた時を求めて』の語り手マルセルに一目置かれていた女中のフランソワーズは、そもそも語り手の叔母レオニに仕えていた。パリに住む語り手一家は、復活祭などの休みになると汽車に乗ってレオニの住む田舎町コンブレーを訪ねるが、この滞在中に一家のために食事を準備するのがこの女中だった。後に語り手はコンブレーの各部屋を「グラニュ糖のような、花粉のような、たべられそうな、敬虔な雰囲気にまみれている」(井上究一郎訳)と思い出しているが、そんな回想はフランソワーズの料理の腕によるものに違いない。
日曜日のお昼は、特に忘れがたいごちそうの日としてマルセルの記憶に刻まれている。食べた後、思わず「ぐったり」となってしまうほどのそのメニューには、「四季のリズムと生活の挿話とがいくらか反映されて」いる。生きのいい大ビラメ、七面鳥、牛の骨髄をあしらったカルドン・ア・ラ・モワル、羊のもも肉のロースト、ホウレンソウ、アンズ、スグリ、フランボワーズ、サクランボ、クリームチーズ、アーモンドケーキ、ブリオッシュ…。そんなすべてのものは、一家の好みを知りつくした料理人自らが市場などで見つけてきたもの。フランソワーズの心づくしの料理が並ぶ日曜の饗宴は、おいしいものを供し、供される喜びに溢れている。
そして、こういったごちそうの最後にうやうやしく添えられるのが「彼女の全才能を傾倒してつくられた」チョコレートクリーム。そして、このクリームを「お皿のなかに一滴でも残しておこうものなら、曲がおわらないのに作曲家のまえで立ち上がるのとおなじ非礼を示したことになっただろう」。語り手にとって、料理女フランソワーズは一番身近にいる芸術家だった。(さ)