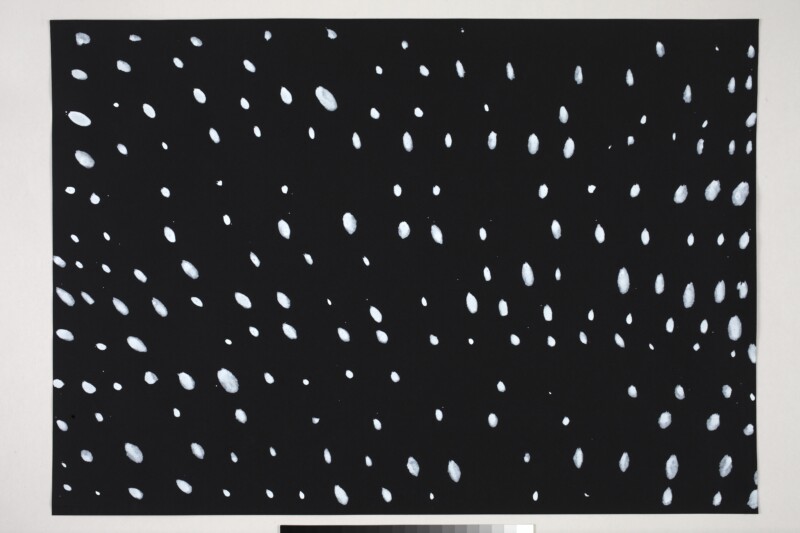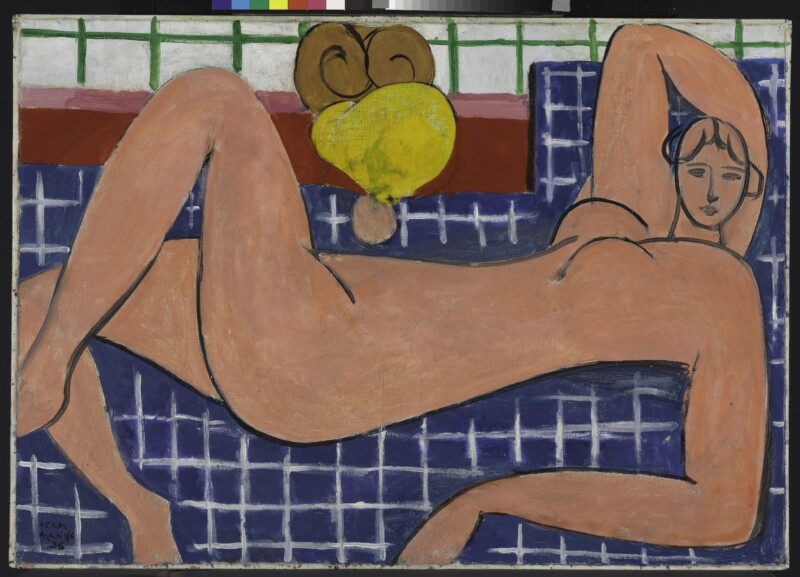Adolfo Wildt
Le dernier symboliste
まつ毛の長い男が目をつむり、額に大きく皺を寄せている。首から胸にかけての筋肉も誇張されており、乳首は花のようだ。この彫刻のポスターを見る限りではなんともキッチュで、行く気がしなくなるが、たった一枚のポスターで判断してはいけない。先入観と実際に見た印象がこれほど違う展覧会はめったにない。凄い、凄いと思いながら見ていった、デッサンも彫刻も、驚異的な巧さである。フランスではほとんど知られておらず、これを逃すとイタリアに行って見るしかない。会期あとわずかだが、時間をやりくりして是非見に行ってほしい。
ミラノで生まれたアドルフォ・ヴィルトは、家が貧しかったため9歳から働き始めた。11歳の時に著名な彫刻家の工房に見習いとして入り、技術を覚えた。アカデミックなアーティストではなく、叩き上げである。それが幸いして、美術学校出身者にはない技巧を身につけた。1894年にプロイセン人のメセナ、フランツ・ローズに出会ったおかげで、生活は保障された。ローズの招きでドイツを旅行し、ミュンヘン分離派展などに出展した。通常、ドイツの美術家は修業を兼ねてイタリアに行くが、ヴィルトはその逆のコースを辿(たど)った。ヴィルトには自己の奥底深くまで降りていくようなゲルマン的な内省と重さがある。旅で触れた文化の影響もあるだろうが、もともと彼にそのような要素があったからこそ、プロイセン人のローズに気に入られたのだろう。
1906年から3年間、鬱(うつ)の時期が続いた。作風が変わり、ヴィルトが現在知られているヴィルトになるのは鬱を抜けた後のことだ。 彫刻もデッサンも様式化されているが、苦悩や感情が表れている。美ではあるが、決して「きれいな」美しさではない。餓死しそうなほど痩せこけた子どもが一組の男女の前にいる「受胎」のように、生と死が隣り合わせになっている。人の顔は能面のようであったり、目が星になっていたり、目の中が不気味に空洞化していたりする。
鬱から抜けた後の1914年の肖像写真を見ると、目がイッている。精神的なものを求めていたヴィルトは、あるときから突き抜けてしまったようだ。
ムッソリーニの愛人の美術評論家からムッソリーニの彫像の注文を受け、彼女が起こした芸術運動「ノヴェチェント」に加わったため、死後、ファシストの芸術家という烙印を押された。それを知ることなく亡くなったことは、本人にとって幸せだったのかもしれない。イタリアで再評価が始まったのはここ10年ほどのことだ。 (羽)
7月13日迄 火休
オランジュリー美術館 1er
画像:Lux (Luce), 1920 Plâtre, 39 x 29 x 10,8 cm Venise, Fondazione Musei
Civici di Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro