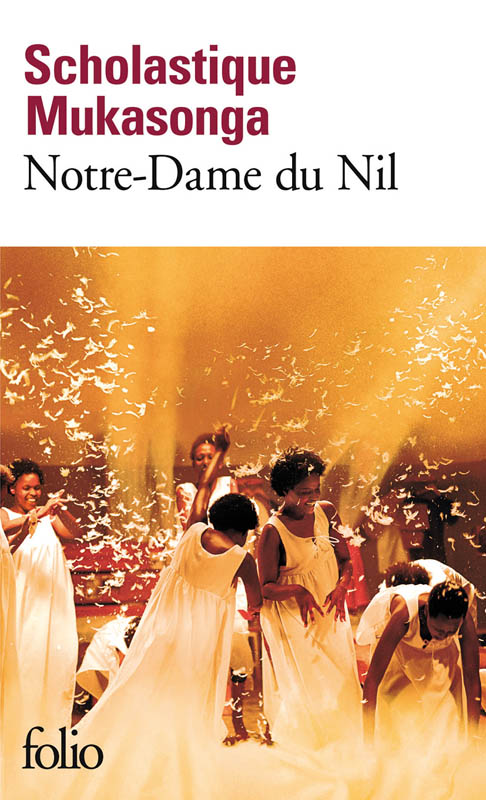
『ナイルの聖母マリア(仮題)』
Notre-Dame du Nil
スコラスティック・ムカソンガ著
Gallimard刊
2012年
ルワンダ、エリート養成高校。
ルワンダの作家スコラスティック・ムカソンガについては過去にも一度紹介したけれど(N°870参照)、彼女がルノドー賞を受賞した作品『ナイルの聖母マリア』(2012年)がこの2月に映画化されると知り、せっかくの機会なのでここで紹介してみたい。
舞台は1970年代ルワンダ。ナイル川の源流近くにある「ナイル川のノートルダム高校」は、善きキリスト教徒として、妻として、また母として、立派なエリート女性を育成すべく特別に設立された学校だ。良家の少女たちは、ときに源流に建てられた聖母像への巡礼をし、敬虔さを保ちながら、ディプロム(学業修了証)のため必死に勉強する。ところが、学校には彼女たちを分かつ一つの大きな溝があった。ツチ族とフツ族という人種の壁だ。94年、この人種的分裂が犠牲者80万人と言われるツチ族の大虐殺へと発展したことはよく知られるが、この対立の歴史は長く、59年にはすでにツチ族虐殺が始まったとされている。この作品が扱うのは、73年にツチ族の生徒たちが学校から追放された事件だ。
またこの年は、ツチ族のエリートたちの大半が国外へ亡命した年にあたり、彼らが政治的に弱体化した重要な時期でもあった。
「人種」による分断。
ルワンダの歴史を見れば、「人種」がいかに「作られた」ものであるかがはっきりと分かる。それは植民地主義(この場合ドイツ、次いでベルギー)の残滓(ざんし)なのだ。人種的対立の大きな原因は、もともとの統治形態を大きく変更し、少数派であるツチ族を優遇したベルギーの植民地政策にあるが、作中にも、「白人たち」がツチ族の人々をいかに自分たちの都合の良いように美化し、利用してきたかについての批判的な描写が何度も見られる。「気狂い老人」として描かれている、ツチ族の少女たちに古代エジプトの女神を見出そうとする白人男性はその象徴のような存在だろう。
修道女、フランス人、ベルギー人の教師たち。少女たちのリーダー的存在で、ツチを徹底的に嫌うグロリオーサ。フツとツチの「混血児」であり、フツへの忠誠を示すがためにそのグロリオーサに気に入られようとするモデスタ。「気狂い老人」の妄想的世界に取り込まれてゆくツチのベロニカ。危機的状況でもディプロムへの希望を捨てないツチのヴィルジニア。すべてのことに反発的なフツのイマキュレ。それぞれの思惑が交錯するなかで、物語は徐々に、人種的憎悪を背景に危険なトーンを帯びてゆき、最終的には学校を台無しにするまでの暴力へと発展してゆく。
ルワンダの縮図。
読み終えて、これはルワンダ社会の縮図なんだな、と思った。カトリック教会が教える清純さや道徳の背後では、憎しみ、裏切り、監視、スパイ、欺瞞がうごめいている。それらを知りながら、何もできない教育者たち。子供たちは自分で行動するしかない。しかし、どうやって?何も知らない少女は、父が吹き込むツチ族への憎悪をそのまま周囲にまき散らす。それは少女を怪物に変える。「全部あなたの嘘で成り立ってるの、ちゃんと分かってるんでしょう」、モデスタのこの言葉に対するグロリオーサの言葉が印象的だ。「それは嘘じゃないの、それは政治なの」。嘘を嘘じゃなくすること、それを政治と呼ぶなら、これほど恐ろしい政治はない…。こうして少女たちの世代に、無意識のうちに、将来のルワンダを準備する土壌が出来上がっていたというわけだ。
映画を監督したのは自身も作家であり、2008年にゴンクール賞も受賞したアフガニスタン出身のアティク・ラヒミ。80年代に祖国の戦争を逃れフランスに亡命。彼が本作をどう解釈するのかにも注目したい。(須)

[著者]
スコラスティック・ムカソンガ
1956年生まれ。73年ブルンジへ亡命、ジブチ滞在を経てフランスに定住、ソーシャルワーカーとして働く。
本年3月に次作『Kibogo est monté au ciel』出版予定。







